「自社の業務効率化のためにチャットボットを導入したいけれど、種類が多すぎて何を選べば良いかわからない」
「AI搭載型とそうでないものの違いが、いまいち理解できない」
「話題のChatGPTは、業務用のチャットボットとして使えるのだろうか」
企業のDX推進や顧客サポート、マーケティングを担当する方の中には、このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
チャットボットは、正しく選んで活用すれば業務効率や顧客満足度を飛躍的に向上させる強力なツールです。しかし、自社の目的や課題に合わないものを選んでしまうと、期待した効果が得られず、コストだけがかかってしまう可能性もあります。
そこでこの記事では、チャットボットの導入を検討し始めた方が知りたい情報を網羅的に解説します。AIの有無といった基本的な種類分けから最新の生成AI技術、目的別の選び方まで、専門外の方にもわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてください。
弊社サンソウシステムズでは月額1万円から利用できる「さっとFAQ」というチャットボットを提供しています。Excelから会話データを簡単に作成できるため、プログラミングスキルも一切必要ありません。
30日間の無料トライアルもありますので、ぜひこの機会に導入を検討してみてください。
チャットボットとは?まず押さえておきたい基本と導入メリット

チャットボットとは、テキストや音声を通じて人間と自動で会話をおこなうプログラムのことです。Webサイトの下に出てくる質問応答ウィンドウや、LINE公式アカウントでの自動返信などが身近な例として挙げられます。
多くの企業がチャットボットを導入する目的は、以下のようなメリットを得るためです。
| 導入メリット | 具体的な効果 |
|---|---|
| 業務効率化とコスト削減 | 定型的な問い合わせを自動化し、担当者の負担を軽減。人件費を削減できる |
| 24時間365日の対応 | 営業時間外や休日でも顧客対応が可能になり、機会損失を防ぐ |
| 顧客満足度の向上 | 待ち時間なくすぐに回答が得られるため、顧客のストレスが減り、満足度が向上する |
| 回答品質の標準化 | 担当者による回答のばらつきがなくなり、常に一定品質のサポートを提供できる |
これらのメリットにより、企業は人的リソースをより専門的な業務に集中させることが可能です。なお、チャットボットの基礎知識については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方は、併せてご確認ください。
【全体像を把握】3つの分類軸でわかるチャットボットの種類一覧

チャットボットにはさまざまな種類があるため、代表的な分類の仕方を知ることが重要です。ここでは、大きく3つの軸でチャットボットの種類を整理しました。
| 分類軸 | 特徴 | 種類の例 |
|---|---|---|
| 1. AIの有無 | チャットボットの賢さや柔軟性を決める基本的な分類 | ・シナリオ(ルールベース)型 ・AI(機械学習)型 ・生成AI型 |
| 2. 対応業務 | 「何のために使うか」という目的による分類 | ・FAQ型 ・処理代行型 ・配信型 ・雑談型 |
| 3. 応答の仕組み | ユーザーとの会話をどのように進めるかの技術的な分類 | ・選択肢型 ・辞書型 ・ログ型 |
これらの分類は、チャットボットを選ぶ際に重要な判断基準です。また、導入後の運用方法も考慮に入れることが成功の鍵です。以降のセクションでは、これらの種類についてより詳しく解説します。
【AIの有無で比較】チャットボットの基本2大タイプ

チャットボットを選ぶ上で重要なのが、AIの有無です。AIはチャットボットの性能やコスト、運用方法を大きく左右します。ここでは、チェットボットの基本となるシナリオ型とAI型の2種類を比較しながら見ていきましょう。
シナリオ(ルールベース)型:決められたルールで応答する堅実なタイプ
シナリオ型チャットボットは、あらかじめ設定されたルールやシナリオにしたがって応答するシンプルなチャットボットです。ユーザーが選択肢を選び特定のキーワードを入力すると、あらかじめ用意された回答を返します。
シナリオ型は低コストで導入でき、回答品質が担保される上、導入も容易です。しかし、柔軟性に欠け、シナリオ作成に手間がかかる点に注意しましょう。
なお、シナリオ型のチャットボットは、質問内容が限定的な場合に最適です。例えば、製品に関するよくある質問への対応や、資料請求の受付などに適しています。想定される質問をシナリオとして準備しておけば、24時間365日対応可能な窓口として機能します。
特に、営業時間外の問い合わせ対応や、人手不足を解消する手段として有効でしょう。しかし、複雑な質問や曖昧な表現には対応できないため、より高度なAIチャットボットとの連携も検討すべきです。
AI(機械学習)型:自律的に学習し柔軟な対応ができるタイプ
AI型チャットボットは、機械学習や自然言語処理といったAI技術を活用し、より人間らしい自然な会話を実現するタイプです。過去の膨大な会話データを学習することで、シナリオにない質問や、ユーザーの曖昧な表現(言葉の揺れ)にも意図を汲み取って柔軟に応答できます。
メリットとしては、登録されていない質問にも学習データに基づいて最適な回答を推測して提示できる柔軟な応答性や、人間と話しているようなスムーズな会話などが挙げられます。デメリットとしては、シナリオ型に比べて初期費用や月額費用が高額になることです。
また、回答精度を高めるために事前に大量の学習データ(FAQや会話ログなど)を準備する必要があるほか、導入後もAIが正しく学習しているかを確認する専門的な作業が必要です。 以上のことからAI型は、問い合わせ内容が多岐にわたるカスタマーサポートや、専門的な社内ヘルプデスクなど、高度な対応が求められる場面で活躍します。
【最新トレンド】話題の生成AI搭載チャットボットとは?ChatGPTとの違いも解説

近年、ChatGPTの登場により、生成AIが大きな注目を集めています。生成AIを活用した新しいタイプのチャットボットも登場しており、従来のAI型とは一線を画す能力を持っています。ここでは、その違いとビジネス利用におけるポイントを見ていきましょう。
従来のAI型と生成AI型の決定的な違い
従来のAI型と生成AI型の大きな違いは、回答を生成する仕組みにあります。従来のAI型は、膨大な学習データ(FAQなど)の中から、ユーザーの質問に近い回答を探し出して提示します。
一方、生成AI型は特定の学習データに縛られず、インターネット上の膨大な知識を基に、その場で人間のように最適な文章を生成します。この違いにより、生成AI型は非常に幅広いトピックについて、まるで人間と話しているかのような自然で創造的な対話が可能です。
しかし、生成される情報の正確性や倫理的な問題、著作権侵害のリスクなど、解決すべき課題も多く存在します。今後の発展と社会への浸透に向けて、これらの課題に対する適切な対策が求められるでしょう。
生成AI活用のメリットと注意点
生成AIをチャットボットに活用する際は、メリットを最大限に活かしつつ、注意点を克服するための対策が不可欠です。ハルシネーション対策としては、生成AIに与える情報源を厳選し、信頼性の高いデータセットのみを使用することが重要です。
また、生成された回答を人間がチェックする体制を構築し、誤った情報を顧客に提供するリスクを最小限に抑える必要があります。情報統制の面では、チャットボットの回答を事前に承認するワークフローの導入や、不適切な表現を検知するフィルタリングシステムを実装することが有効です。
さらに、利用規約を明確に定め、生成AIの利用範囲を制限することも大切です。これらの対策を講じることで、生成AIチャットボットは、顧客満足度向上や業務効率化に大きく貢献する強力なツールとなり得ます。
最新技術「RAG」が生成AIの弱点を克服
生成AIの弱点を克服するRAG技術は、企業にとって非常に有効なソリューションです。社内データという信頼できる情報源を活用することで、生成AIはより正確で、企業のニーズに合致した回答を提供できます。
さらに、RAGは常に最新の情報に基づいて回答を生成できるため、情報の陳腐化を防ぎ、常に最適な情報を提供することが可能です。従業員からの問い合わせや顧客対応、ナレッジマネジメントなど、幅広い分野での活用が期待できます。RAG導入により、業務効率化や顧客満足度向上、そして企業全体の情報活用能力向上に貢献します。
チャットボットの8つの種類

チャットボットは、機能や仕組みによってさらに細かく分類することが可能です。ここでは、代表的な8つの種類とその特徴を見ていきましょう。
1.FAQ型
FAQ型とは、ユーザーからのよくある質問に自動で回答することに特化したチャットボットです。社内外の問い合わせ対応を効率化する目的で多く導入されています。
特に、FAQが充実している企業や、定型的な問い合わせが多い部署での導入効果が高いです。24時間365日の対応が可能になるため、顧客満足度向上にも貢献します。
導入にあたっては、FAQデータの整備とチャットボットの学習が重要です。運用開始後も、回答精度を向上させるために、定期的なメンテナンスが必要です。これにより、担当者の負担を軽減し、より高度な業務に集中できる環境を構築できます。
2.ログ型
ログ型とは、ユーザーとの対話履歴を蓄積・分析することで自己学習能力を高め、回答精度を向上させるタイプです。蓄積されたデータは、ユーザーの質問傾向やニーズを把握する上で貴重な情報源となり、FAQの拡充や改善に役立てられます。
例えば、頻繁に尋ねられる質問に対しては、よりわかりやすい回答を作成し、関連情報を追加することで、ユーザーの満足度を高めることができます。また、データ分析によって、これまで想定していなかった新たな質問や課題を発見し、対応するための情報や機能を追加することも可能です。
このように、対話履歴の蓄積・分析は、チャットボットの継続的な成長と進化を支える重要な要素といえるでしょう。蓄積されたデータは、顧客サポート全体の品質向上にも貢献し、他のサポートチャネルとの連携を強化する上でも重要な役割を果たします。
3.選択肢型
選択肢型とは、ユーザーの入力を受け付ける際に自由記述ではなく、あらかじめ用意された選択肢の中から選んでもらう形式のチャットボットのことです。
ユーザーは提示された選択肢を選ぶだけで会話を進められるため、入力の手間が省け、スムーズな対話が可能です。また、チャットボット側はユーザーの意図を汲み取りやすく、より適切な回答を提供できます。
なお、選択肢型チャットボットは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにさまざまな工夫が凝らされています。例えば、選択肢の提示方法一つをとっても、ボタンの配置や色使い、アニメーションなどを工夫することで、ユーザーの視覚的な負担を軽減し、直感的に操作を実現します。
また、選択肢の文言も専門用語を避け、平易な言葉を用いることで、幅広いユーザー層がストレスなく利用できるでしょう。さらに、会話の進行に合わせて、画像や動画などの視覚的な要素を効果的に取り入れることで、ユーザーのエンゲージメントを高められます。
4.配信型
配信型のチャットボットとは、事前に用意された情報をユーザーの行動や属性に合わせて配信するチャットボットのことです。ユーザーからの質問に答えるだけでなく、能動的に情報提供することでエンゲージメントを高め、特定の行動を促す効果が期待できます。これらの効果を最大化するには、配信タイミングやコンテンツの最適化が重要です。
例えばWebサイトへのプッシュ通知だけでなく、アプリ内メッセージやメールマガジンと連携すれば、より多角的なアプローチが可能です。 キャンペーン情報の発信においては、ターゲットユーザーを絞り込むと、よりパーソナライズされた情報提供が実現できます。
さらに、ユーザーの反応を分析し、改善を繰り返すことで、より効果的なコミュニケーションが実現します。A/Bテストなどを活用し、最適なメッセージや配信タイミングを見つけることが重要です。
5.辞書型
辞書型とは、あらかじめ登録されたキーワードと回答のペア(辞書)に基づいて応答するタイプです。ユーザーが入力した文章に登録キーワードが含まれていると、対応する回答を返します。
辞書型は、FAQのような形式でよく用いられ、特定の質問に対して一貫性のある回答を提供することに優れています。なお、辞書型はキーワードのマッチング精度が重要であり、同義語や類似表現も考慮してキーワードを登録すると、より多くの質問に対応することが可能です。
また、キーワードだけでなく、文章の意図を理解するような高度な自然言語処理技術を組み合わせれば、より柔軟な応答も実現できます。
6.サポート運用型
サポート運用型のチャットボットは、顧客からの問い合わせ対応を支援し、オペレーターの負担軽減や効率化を目的とするものです。チャットボットがFAQの自動回答や一次対応、問い合わせ内容の整理などをおこない、オペレーターがより複雑な案件に集中できるようサポートします。
例えば、問い合わせ件数が多い場合に、FAQの自動回答で自己解決を促進できると、オペレーターの対応時間を削減することが可能です。また、人手不足の場合には、オペレーターの業務負担を軽減し、リソースを有効活用できます。さらに、24時間365日の対応を時間や場所を選ばずに実現できます。
7.雑談型
雑談型のチャットボットは、単なる情報提供に留まらず、親しみやすい対話を通じてユーザーとの関係性を深めることを目指しています。企業の顔として公式キャラクターと連携すれば、ブランドイメージの向上にも貢献します。
具体的には、季節の挨拶やイベント情報の発信、キャラクターの日常を描いたコンテンツの配信などを通じて、ユーザーの興味を引きつけ、継続的なエンゲージメントを促進することが可能です。
また、ユーザーからのフィードバックを収集し、サービス改善に役立てると、よりパーソナライズされたコミュニケーションを実現できます。まるで友人と会話しているかのような、温かみのあるやり取りを提供し、企業のファンを増やしていくことが期待されます。
8.処理代行型
処理代行型のチャットボットとは、ユーザーからの依頼や問い合わせに対して、本来人がおこなうべき処理を自動化し、代わりにおこなうチャットボットのことです。
例えば、予約受付や在庫確認、顧客情報の検索・更新、FAQへの回答などが挙げられます。ユーザーはチャットボットとの対話を通じて、これらの処理を簡単かつ迅速に完了させることが可能です。処理代行型のチャットボットは、ユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させ、時間と労力を節約することにつながります。
ただし、他のシステムとの連携が不可欠であり、APIなどを介して安全かつ効率的にデータをやり取りする仕組みが求められます。また、個人情報を扱う場合には、セキュリティ対策も万全でなければなりません。さらに、さまざまな手続きに対応できるよう、柔軟な拡張性を持つアーキテクチャを採用することが重要です。
【目的・業務別】チャットボットの活用シーンと適した種類

自社に最適なチャットボットを選ぶには、何のために使いたいかという目的を明確にすることが不可欠です。ここでは、代表的な3つの活用シーンと、それぞれに適したチャットボットの種類を紹介します。
1.問い合わせ対応の効率化
チャットボットは、カスタマーサポートや社内ヘルプデスクにおいて、問い合わせ対応の効率化に大きく貢献します。FAQ型やログ型、サポート運用型のチャットボットが特に有効です。AI型であれば、より複雑で専門的な質問に対応でき、自然な会話での解決を支援します。
導入にあたっては、質問内容の範囲や複雑さを考慮し、最適なタイプを選択することが重要です。例えば、製品に関する基本的な質問が多い場合はシナリオ型が適していますが、技術的なトラブルシューティングなど高度な対応が必要な場合はAI型がより効果的でしょう。
チャットボットの導入により、担当者の負担を軽減し、顧客満足度向上にもつながります。
2.見込み顧客の獲得・育成
Webサイト訪問者に対してチャットボットが積極的にアプローチし、見込み顧客(リード)の獲得や商品購入へとつなげるマーケティング活動も重要な活用シーンです。見込み客の獲得・育成には、配信型と処理代行型がおすすめです。
選ぶべきタイプとしては、キャンペーンの案内や資料請求などゴールが明確な場合はシナリオ型が有効で、顧客のニーズに合わせた個別の商品提案などより高度な接客をおこないたい場合はAI型が適しています。
さらに、チャットボットを活用すれば24時間365日顧客対応が可能となり、機会損失を防げます。例えば、営業時間外のお問い合わせや、よくある質問への即時回答など、人的リソースだけでは対応しきれない部分をカバーすることが可能です。
また、顧客データを蓄積・分析すれば、よりパーソナライズされたマーケティング戦略の立案にも役立ちます。このように、チャットボットは単なる自動応答ツールとしてだけでなく、顧客体験の向上や売上増加に貢献する強力なマーケティングツールとして活用できます。
3.顧客エンゲージメント向上
直接的な売上や業務効率化だけでなく、顧客と良好な関係を築き、企業やブランドのファンになってもらうためにもチャットボットは活用できます。企業のキャラクターや世界観に合わせて、親しみやすい対話ができるシナリオ型やAI型を選ぶのが最適です。AIを活用することで、より人間らしい自然な雑談が実現します。
さらに、雑談型チャットボットは、顧客の潜在的なニーズを把握する手がかりにもなります。顧客との自然な会話から得られるデータは、商品開発やサービス改善に役立つ貴重な情報源です。
例えば、顧客が頻繁に特定商品の関連情報を尋ねる場合、その商品に対する関心が高いことがわかります。このような情報を分析することで、より顧客のニーズに合致した商品やサービスを提供することが可能です。
また、顧客との継続的なコミュニケーションを通じて、長期的な信頼関係を構築し、ブランドロイヤリティを高めることにもつながります。
失敗しない|自社に最適なチャットボットの選び方 4つのステップ

ここまで解説した知識を基に、自社に合ったチャットボットを選ぶための具体的な手順を4つのステップで紹介します。このステップに沿って検討を進めることで、導入後のミスマッチを防げます。
STEP1:導入目的と解決したい課題を明確にする
最初に、チャットボットの導入目的を具体的に定義します。目的が曖昧なままでは、適切なツールを選ぶことはできません。具体的な例は以下のとおりです。
- 顧客からの電話問い合わせ件数を半年で20%削減する
- Webサイトからの資料請求数を3カ月で月10件増やす
- 社内のIT関連の問い合わせ対応にかかる時間を1日あたり2時間削減する
このように、具体的な数値目標(KPI)を設定すると、目標の達成度合いを客観的に評価できます。
STEP2:目的に合ったAIの有無・種類を選ぶ
STEP1で明確にした目的に基づいて、どのタイプのチャットボットが最適かを判断しましょう。
| 目的 | 推奨タイプ | 判断理由 |
|---|---|---|
| 定型的な質問への回答 | シナリオ型 | コストを抑えつつ、品質の安定した対応が可能 |
| 幅広い・複雑な質問への対応 | AI型 | 柔軟な応答で自己解決率を高める必要がある |
| 最新技術で他社と差別化 | 生成AI型(RAG活用) | 自然な対話体験で顧客満足度を最大化したい |
チャットボットのタイプ選定は、単に機能だけでなく、運用コストや学習データ準備、メンテナンスの容易さも考慮しなければいけません。例えば、AI型は初期コストが高いものの、継続的な学習により対応範囲が広がり、長期的に見るとコスト効率が良い場合があります。
シナリオ型は、FAQの充実やシナリオ設計が重要であり、定期的な見直しと更新が不可欠です。生成AI型は、RAGの精度が顧客体験に大きく影響するため、データの整備とチューニングに注力すべきです。それぞれの特性を理解し、自社のリソースや目標に最適なタイプを選択することが成功への鍵となるでしょう。
STEP3:導入形態(クラウド型/オンプレミス型)を検討する
次に、チャットボットのシステムをどのように導入するかを決めます。チャットボットの導入方法は以下の2種類があり、それぞれのメリット・デメリットを考慮した上で適切なものを選ぶことが大切です。
| 導入形態 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| クラウド型 | ベンダーが提供するサーバー上でサービスを利用する | ・初期費用が安い ・導入がスピーディ ・メンテナンス不要 |
・カスタマイズ性が低い ・ランニングコストがかかる |
| オンプレミス型 | 自社のサーバーにシステムを構築する | ・カスタマイズ性が高い ・高度なセキュリティ |
・初期費用が高い ・導入に時間がかかる ・自社での保守運用が必要 |
現在では、導入の手軽さからクラウド型が主流です。特別なセキュリティ要件がない限りは、クラウド型から検討するのが良いでしょう。
クラウド型を選択する場合、ベンダーの選定が重要です。各社の提供する機能やサポート体制、費用などを比較検討し、自社のニーズに最適なベンダーを選びましょう。無料トライアルなどを活用して、実際に使用感を試してみるのも有効です。
また、オンプレミス型は、初期投資は大きくなりますが、長期的に見るとコストを抑えられる可能性もあります。特に、セキュリティポリシーが厳格な企業や、独自のカスタマイズを求める企業にとっては、オンプレミス型が適しています。導入にあたっては、専門的な知識を持つ人材が必要となるため、社内リソースの確保も検討しましょう。
STEP4:費用とサポート体制を確認する
チャットボットの料金体系はさまざまですが、主に初期費用と月額費用で構成されます。種類別の費用感の目安は以下のとおりです。
| 種類 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| シナリオ型 | 0~50万円 | 1~10万円 |
| AI型 | 3~50万円以上 | 1.5~10万円以上 |
| 生成AI型 | 5~100万円以上 | 5~100万円以上 |
単純な費用の比較だけでなく、導入後のサポート体制も重要な選定ポイントです。FAQデータの作成支援や定期的な改善提案など、手厚いサポートを提供してくれるベンダーを選ぶと導入効果を最大化できます。
【導入実績多数あり】低コスト・簡単導入なら「さっとFAQ」がおすすめ

「チャットボットの重要性は理解できたが、いきなり高額な費用をかけるのは難しい」
「社内にIT専門の担当者がいないので、簡単に使えるものが良い」
このようなお悩みを持つ企業に最適な選択肢の一つが、株式会社サンソウシステムズが提供する「さっとFAQ」です。「さっとFAQ」は、月額1万円からという低価格で利用できるFAQチャットボットで、Excelで簡単にFAQデータを作成・管理できる手軽さが特徴です。
| 「さっとFAQ」の強み | 詳細 |
|---|---|
| 圧倒的なコストパフォーマンス | 初期費用0円、月額1万円から利用可能。無料トライアルもあり、スモールスタートに最適 |
| Excelで簡単導入・運用 | 普段使い慣れたExcelでFAQデータを作成・更新できるため、専門知識は必要ない |
導入の手軽さとコストパフォーマンスから、大企業から中小企業まで500社以上の導入実績を誇ります。例えば、花キューピット株式会社様の事例では、繁忙期の問い合わせ対応に活用し、500万円のコストメリットを生み出すなど、確かな成果を上げています。導入後のサポート体制も充実しているため、安心してご利用いただくことが可能です。
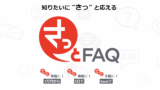
自社の目的に合ったチャットボットの種類を見極めよう

この記事では、チャットボットの種類について、AIの有無や目的別の分類、そして自社に合った選び方のステップまでを網羅的に解説しました。
チャットボットには多くの種類がありますが、最も重要なのは導入目的を明確にすることです。目的さえはっきりすれば、選択肢は自然と絞られてきます。
まずは本記事を参考に自社の課題を整理し、気になるチャットボットサービスの資料請求や無料トライアルを試してみてはいかがでしょうか。
また、弊社サンソウシステムズが提供するチャットボット「さっとFAQ」であれば、Excelから会話データを簡単に作成できるため、プログラミングスキルも一切必要ありません。
30日間の無料トライアルもご用意しましたので、ぜひこの機会に導入を検討してみてください。

