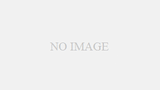人手不足の解消や顧客満足度の向上は、多くの企業にとって重要な課題です。
「スタッフが足りず、お客様への対応が追いつかない」「問い合わせ対応に追われ、本来の業務に集中できない」
このような悩みを解決する手段として、今「AI接客」が注目されています。
本記事では、AI接客の基礎知識から具体的な種類、導入のメリットや成功事例までを網羅的に解説します。さらに、失敗しないための導入ステップも紹介しますので、ぜひお役立てください。
株式会社サンソウシステムズが提供する、月額1万円から始められるチャットボットツール「さっとFAQ」は、プログラミングやAIの専門知識が一切不要で、生成AIを活用しながら誰でも簡単に導入・運用できるチャットボットです。
30日間の無料トライアルも受け付けておりますので、問い合わせ対応にお悩みを抱えている方はこの機会に導入をご検討ください。
AI接客とは

AI接客とは、AI(人工知能)の技術を活用して、顧客対応を自動化・高度化するサービス全般を指します。Webサイトのチャットボットや、飲食店の配膳ロボットなどがその代表例です。
AI接客は業務を自動化するだけでなく、顧客データを分析して一人ひとりに合った提案もおこなえます。従来の顧客対応をより効率的でパーソナライズされた顧客体験を提供できることがAI接客のメリットです。
AI接客が注目されている理由

現代のビジネス環境において、AI接客の重要性が高まる背景には、社会が抱えるいくつかの大きな課題があります。
- 労働人口の減少:少子高齢化により、多くの業界で人手不足が深刻化
- 人件費の高騰:最低賃金の上昇などにより、人材確保にかかるコストが増加傾向
- 顧客ニーズの多様化:時間や場所を問わず、自身のタイミングで即時対応を求める顧客が増加
- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進:企業競争力を高めるため、デジタル技術を活用した業務改革の需要アップ
AI接客は、課題を解決する有効な手段として、多くの企業から期待が寄せられています。
AI接客の主な種類と特徴

AI接客にはいくつかの種類があり、それぞれに得意なことや適した場面が異なります。
本章では代表的な3つの種類を比較し、その特徴をご紹介します。自社の目的や解決したい課題に合わせて、最適な種類を選ぶことが重要です。
| 種類 | 概要 | 主な機能 |
|---|---|---|
| AIチャットボット/ボイスボット | テキストや音声で自動対話をおこなうシステム | ・FAQ対応 ・商品検索 ・予約受付 ・資料請求 |
| アバター接客 | 画面上のCGキャラクターを介し、遠隔のオペレーターやAIが接客する | ・商品説明 ・施設案内 ・専門的なコンサルティング |
| 接客ロボット | 物理的な空間で自律走行し、案内や配膳などをおこなうロボット | ・フロア案内 ・配膳・下膳 ・受付業務 ・簡単な会話 |
AIチャットボット/ボイスボット|テキストや音声で自動応答
AIチャットボットは、Webサイトやアプリ上でテキストを用いて顧客の質問に自動で回答するシステムです。一方、ボイスボットは電話応対などで音声による自動応答をおこないます。
AIチャットボット/ボイスボットは、よくある質問への対応や資料請求、簡単な予約受付といった定型業務が得意分野です。
近年では、自然言語処理技術の進歩により、AIチャットボット/ボイスボットの応答精度が飛躍的に向上しており、より複雑な質問や曖昧な表現にも対応できるようになってきています。また、機械学習によって、顧客との対話データから学習し、応答精度を継続的に改善していくことも可能です。
AIチャットボット/ボイスボットのメリットは、24時間いつでも対応できるため、顧客満足度の向上と業務効率化に役立つことです。特に、FAQ対応においては、顧客が自己解決できる割合を高めることで、問い合わせ件数を大幅に削減できます。
結果、カスタマーサポート部門の負担を軽減し、本来注力すべき業務に集中させられます。
しかし一方で、AIチャットボットやボイスボットは複雑な感情を理解することが苦手で、決まった形ではない質問への対応が難しいというデメリットもあります。
アバター接客|遠隔操作で人間味をプラス
アバター接客は、店舗や施設に設置されたモニターに表示されるキャラクター(アバター)を通じて接客をおこなう仕組みです。
アバターは遠隔地にいるスタッフが操作するため、AIだけでは難しい複雑な質問や相談にも柔軟に対応できます。また、非対面でありながらも、人間らしい温かみのあるコミュニケーションを実現できるのが最大の特徴です。顧客との信頼関係を築くことが重要な場面で効果を発揮できるでしょう。
例えば、高額な商品やサービスの説明、個人情報を取り扱う手続きなどにおいて、アバターを通じて親身な対応を提供することで、顧客の安心感を高めることが可能です。
さらに、アバター接客は場所や時間の制約を受けずに、高品質な接客を提供できるため、店舗の人員配置の最適化にも役立ちます。例えば、繁忙時間帯には複数のアバターを同時に稼働させ、閑散時間帯にはアバターの数を減らすことで、人件費を効率的に管理できます。
一方、システム導入コストがかかることや、オペレーターの人件費が発生することがデメリットになるので、導入前にコストを確認することが重要です。
接客ロボット|物理的な作業を代行
接客ロボットは、実際の店舗や施設内で物理的な作業をおこなう自律走行型のロボットです。レストランでの料理配膳や、ホテルでの荷物運び、商業施設でのフロア案内などが主な役割です。
スタッフの身体的な負担を直接軽減できるため、人手不足が深刻な業界で導入が進んでいます。レストランで配膳ロボットが料理を運ぶことで、ウェイターは顧客とのコミュニケーションや注文受付に専念できるようになります。
また、ユニークなサービスが話題性を生み、集客効果につながることもあるでしょう。
一方、導入コストが高額な傾向にあることや、設置場所に制約があることがデメリットです。故障のリスクも避けられないため、導入前に確認が必要です。
AI接客がもたらす5つの導入メリット

本章では、AI接客を導入することによる5つのメリットを解説します。
人手不足の解消とコスト削減
AIに定型的な業務を任せることで、スタッフはより付加価値の高い業務に集中できるようになります。結果として、限られた人員でも効率的に業務を回すことが可能になることがメリットの一つです。
また、深夜や休日の対応をAIに置き換えられることによる人件費抑制や、採用や新人教育にかかるコスト削減につながることも、嬉しいポイントです。
24時間365日対応による機会損失の防止
時間や曜日を問わず、商品の購入や疑問の解決ができるサービスを求める顧客が増えています。
AI接客を導入すれば、営業時間外の問い合わせや注文にも対応でき、販売機会の損失を防げます。特に、ECサイトやオンラインサービスを提供する企業にとって、大きなメリットとなるでしょう。
例えば、深夜にECサイトを訪れた顧客の質問にAIチャットボットが即座に答えることで、購買意欲を下げることなく購入へとつなげられます。また、AIチャットボットは、顧客の購買履歴や行動データに基づいて、パーソナライズされた商品やサービスを提案することもできます。売上向上にも役立つことは、AI接客を導入するメリットの一つです。
サービス品質の均一化とパーソナライズの両立
人間のスタッフによる接客は、個人のスキルや経験、さらにはその日の体調によって、サービスの品質にばらつきが生じることがあります。一方、AIはプログラム通りに動作するため、常に一定で高い品質のサービスを提供できます。
さらに、顧客の閲覧履歴や購買データなどを分析することで、それぞれの興味に合わせた商品をおすすめすることも可能です。 このように、顧客に高品質で均一なサービスを提供できるだけでなく、一人ひとりに合わせたパーソナライズされた体験を実現できることも、AIの大きなメリットです。
多言語対応でインバウンド需要を獲得
多言語に対応できるスタッフの採用や教育には、大きなコストと時間がかかります。
多言語対応のAI接客ツールを導入すれば、外国人観光客や海外の顧客からの問い合わせにもスムーズに対応可能です。さまざまな言語に対応することでインバウンド需要を取り込み、新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。
また、AIチャットボットは、各国の文化や習慣に合わせた適切な対応をおこなうこともできるため、顧客満足度を向上させることができます。特に、グローバル展開を目指す企業にとって、役立つツールでしょう。
顧客データ活用でマーケティングを強化
AI接客は、顧客との対話データから顧客ニーズや市場機会を把握し、新商品開発につなげられます。例えば、ECサイトのAIチャットボットでは、問い合わせデータから在庫切れの改善や商品情報の充実、FAQ拡充による顧客満足度向上が可能です。
また、顧客データをマーケティング戦略に活用し、パーソナライズされたキャンペーンやキーワード広告で効果を高めることも期待できます。
AI接客導入の前に知っておきたい課題と注意点

AI接客導入には課題や注意点があります。事前に理解し、対策を講じることが重要です。
導入・運用コストが必要なため、費用対効果(ROI)の評価が重要
AI接客の導入には初期費用やライセンス料が発生します。
導入検討時は、人件費削減だけでなく、顧客満足度向上による売上増加や機会損失防止といった多角的な視点からROIを評価することが大切です。例えば、AIチャットボットの導入・運用・メンテナンス費用を考慮し、長期的な視点でROIを評価します。また、顧客満足度向上や売上増加も考慮する必要もあります。
イレギュラー対応が難しく、人との連携が必要
AIは学習データに基づいて応答するため、複雑な問い合わせやクレームへの対応は苦手分野です。そのため、AIが得意なこと、人間が得意なことを明確にし、役割を分担することが重要です。
例えば、AIチャットボットはFAQや簡単な問い合わせに対応させ、複雑な問い合わせやクレームは人間のオペレーターに任せます。AIと人間がそれぞれの得意分野を活かすハイブリッド体制が、顧客満足度維持に欠かせません。
AIから人間へのスムーズな引き継ぎのために、適切なツールやシステム導入も重要です。
顧客の心理的抵抗や倫理的な配慮が不可欠
顧客の中には「人と話したい」と感じる方もいます。AI対応であることを明確に伝え、有人対応への切り替えオプションを用意することが大切です。
また、個人情報収集・利用時はプライバシーポリシーを明示し、顧客の同意を得ることが重要です。セキュリティ対策を万全にし、個人情報を適切に管理することが顧客からの信頼を得るために欠かせません。
AI接客の成功事例から学ぶ活用術

本章では、業界別のAI接客の成功事例を業界別でご紹介します。
株式会社ユニクロ:AIチャットボットでお買い物をサポート

ユニクロは、公式アプリにAIチャットボット「IQ」を導入し、在庫確認や返品・交換といった定型的な問い合わせに24時間自動回答しています。
これにより、カスタマーサポートの対応可能量が2倍に増加しました。AIチャットボットの活用により顧客満足度が向上し、さらにカスタマーサポート部門の負担も軽減されています。
また、AIで解決できない複雑な質問は有人チャットに引き継がれる体制を整えることで、より高品質な顧客対応も実現しています。
参考:株式会社ユニクロ「IQ・チャットサポートについて」
株式会社通販新聞社「【ユニクロの松山真哉部長に聞く AI接客アプリの狙いとは?㊦】 質問対応精度が大幅向上、「パーソナライズ」も強化へ」
株式会社エターナルホスピタリティグループ(鳥貴族):AIスタッフによる予約電話応対

鳥貴族では、AIスタッフ「さゆり」が電話予約を24時間365日自動で受け付けています。実際に人と会話しているかのように対応できるのが特徴のサービスです。
従業員はピーク時の電話対応から解放され、お客様への接客に集中できるようになりました。電話の取りこぼしが減った結果、予約数も増加し、売上向上に貢献しています。
SNSでは、「鳥貴族に予約の電話したらAIさゆりが出た。会話できるタイプで、予約めちゃくちゃスムーズだしこりゃすごいわ」「鳥貴族のAI予約のさゆりちゃんが賢すぎる」という声が寄せられています。
AIが予約受付業務を自動化し、従業員の負担を軽減しながら、売上向上に貢献した事例と言えるでしょう。
参考:株式会社エビソル「【プレスリリース】鳥貴族、直営60店舗で「AIレセプション」を導入〜月間1万件以上の電話を対話型のAIが対応し、人手不足解消へ〜」
株式会社すかいらーくホールディングス:ロボットでレストランでの配膳・下膳

すかいらーくグループでは、全国の店舗にネコ型配膳ロボットを導入しています。
ロボットが配膳や下膳をおこなうことで、従業員の身体的な負担が軽減されました。フロアスタッフの歩数は、広い店舗ではわずか数時間で1万歩超でしたが、ロボットの導入によって歩行数も42%削減しています。
また、ランチピーク回転率が7.5%向上、片付け時間が35%削減するなどの効果も出ています。従業員は他の業務に集中できるようになり、ドリンクバーやトイレの清掃などにかける時間が増えたと報告もあるようです。
ロボットの導入により、店舗全体に良い効果が出ていると言えるでしょう。
参考:株式会社メディアジーン「すかいらーく「ネコ型配膳ロボ」3000台導入を成功させた「特命チーム」に迫る」、 「すかいらーく「時短協力金427億円」の黒字決算。2022年は「生き残りの戦略」かけた勝負の年に」
H.I.S.ホテルホールディングス株式会社(変なホテル):恐竜型ロボットや人型ロボットによるチェックイン・アウト業務

「変なホテル」では、フロント業務を多言語対応ロボットが担当し、省人化を実現しています。ロボット接客というユニークな体験はホテルの魅力となり、他ホテルとの差別化に成功しました。
他にも、人型ロボットとスマートフォンが合体したロボットを客室内に設置し、ホテル館内の説明や周辺情報などを提供しています。読み聞かせ・ダンス・クイズなども可能で、多くの顧客に好評を得ています。
AI接客の活用により、人件費の削減や、顧客への新しい体験の提供など、競争優位性を確立していると言えるでしょう。
参考:H.I.S.ホテルホールディングス株式会社 変なホテル公式HP
株式会社リクルート「フロントはもちろん客室サービスもロボットに。「変なホテル」の次なる進化(HISホテルホールディングス)」
日本調剤株式会社:AI無人受付と遠隔服薬指導

日本調剤の薬局では、AIによる遠隔受付システムを導入しました。新規受付や事前に処方せんを送信した患者、不足薬の受け取りや外出後に再来店した患者など、すべての受付パターンを自動受付できるシステムです。
一連の対応をAIでおこなうため、患者の待ち時間が短縮されています。また、薬剤師は一元管理された情報をすぐに把握できるため、受付業務の効率化や業務負担の軽減にもつながっています。
さらに、薬局が混雑しているときは薬剤師が遠隔で服薬指導も可能です。これにより、薬剤師は服薬指導などの専門性の高い業務に集中できるようになりました。
AI無人受付システムの導入により、医療サービスの質向上にも役立っています。
参考:株式会社サイバーエージェント「薬局特化型の接客AIエージェント「薬急便 遠隔接客AIアシスタント」、 日本調剤へ提供開始」
失敗しないAI接客導入の3ステップ

AI接客の導入を成功させるには、計画的な導入が重要です。本章では、導入で失敗しないための3つのステップを紹介します。
1.目的を明確にし、KPIの設定をする
まず、「なぜAI接客を導入するのか」という目的を明確にします。目的が曖昧だと、期待した効果が得られない可能性があります。
「人手不足を解消したい」「顧客満足度を上げたい」などの目的を、具体的な数値目標(KPI)に落とし込みましょう。例えば、「問い合わせ対応時間を30%削減する」「顧客満足度アンケートの点数を10%向上させる」といった目標を設定します。
KPI設定により、導入効果を客観的に測定し、改善につなげられます。
2.AIと人間の役割分担を設計する
AIにすべての業務を任せることは現実的ではありません。定型的な問い合わせ対応はAI、複雑な相談やクレーム対応は人間など、それぞれの得意分野に応じた役割分担を決めましょう。
AIから人間へスムーズに業務を引き継ぐためのルールやフロー設計は、顧客体験を損なわないために不可欠です。
また、AIから人間へのスムーズな引き継ぎを実現するために、適切なツールやシステム導入も重要です。
3.スモールスタート後、継続的に改善する
最初から全社的に大規模導入するのではなく、特定の部署や業務に限定して小さく始めましょう。大規模導入は問題発生時の対応が難しく、効果を得られない可能性があります。
スモールスタートの成果や課題を基に改善を加え、徐々に対象範囲を広げていくのが効果を高めるポイントです。
本格的な導入後も、顧客からのフィードバックやAIの応対データを分析し、継続的に改善を続けることが重要です。
チャットボットによる自動対応なら業界屈指のコストパフォーマンス「さっとFAQ」がおすすめ

AI接客の第一歩としてチャットボット導入を検討するなら、「さっとFAQ」がおすすめです。
さっとFAQは、プログラミングやAIの専門知識が一切不要で、生成AIを活用しながら誰でも簡単に導入・運用できるチャットボットです。
| 「さっとFAQ」の主な特徴 | |
|---|---|
| 驚きの低コスト | 月額わずか1万円から利用可能 |
| お申し込みから即日公開 | 既存のFAQをExcelファイルにまとめるだけで、すぐにチャットボットを構築できる |
| 簡単な操作性 | Excelから会話データを簡単に作成でき、ノーコードでシナリオ作成やアンケート機能の実装も可能 |
| 生成AIの活用 | 追加料金なしで生成AIと連携をおこない、ファイルやURLを指定するだけでかんたんに会話データを作成 |
| ハイブリッド型の高精度 | 一問一答形式からシナリオ形式まで4種類のチャットボットで用途に合わせて選択可能 |
| 豊富な機能 | 複数のボット管理、分析ダッシュボードなど、運用に必要な機能が充実 |
| 万全のセキュリティ | 不正アクセス対策や脆弱性対策はもちろん、災害時にもサービスが停止しない堅牢な基盤で運用 |
| 手厚いサポート | 導入から運用まで、専任の担当者がきめ細やかにサポート |
さっとFAQは、AIチャットボットではないものの、手軽に導入できるチャットボットとして、大手企業から中小企業まで、500社以上の導入実績があります。問い合わせ対応の効率化により、年間400時間の業務時間と800,000円のコスト削減を達成した事例もあるなど、あらゆる業界から評価されています。
手軽さと高い効果を両立したさっとFAQは、IT部門の負担を軽減し、予算が限られている企業でも導入することが可能です。
現在、30日間の無料トライアルをおこなっています。「AIをつかいこなせるか不安」「スモールスタートで接客を自動化したい」という方はこの機会に導入をご検討ください。
さっとFAQによる効率化・コスト削減・顧客満足度をアップした事例

「さっとFAQ」は、500社以上の企業で導入され、成果を上げています。本章では、効率化・コスト削減・顧客満足度をアップした事例をご紹介します。
小売:チャットボットの顧客対応で満足度が向上

フラワーギフトの受注事業を展開する花キューピット株式会社は、母の日などの繁忙期に問い合わせに対応しきれない状況が発生するという課題を抱えていました。そこで、カスタマーセンターを取り巻く環境を改善するためにチャットボットを導入しました。
顧客に自己解決を促すツールとしてチャットボットさっとFAQを導入した結果、利用者数やチャット回数を見ると、母の日の前後は平均の約2.5倍も利用されるようになりました。
最初は問い合わせの内容にほとんど回答できていなかったそうですが、データを分析しさまざまな問い合わせに対応できるように回答を工夫し精度を上げていきました。現在では、基本的な質問はチャットボットで自己解決できていることがデータで確認できており、顧客満足度の向上にも直結していると考えているそうです。
参考:「お花を贈りたい」という思いに寄り添って お客様の手間をチャットボットで軽減
医薬品:電話による問い合わせを削減し、複雑な問い合わせに対応できるように

風邪薬やスキンケアなど多岐にわたる医薬品を開発し販売している宇津救命丸株式会社では消費者からの問い合わせ対応における、電話に代わるツールとしてチャットボットを活用しています。
お客様相談室用にもともと用意してあったExcelをそのまま活用できることや、簡単にチャットボットを作れるという点が決め手となり、さっとFAQを導入しています。週に2〜3時間の作業時間を確保し、約2カ月でリリースに至りました。
リリース後もメンテナンスを重ね、現在ではリリース当初よりもチャット開始率を20%向上させることに成功しています。さらに、同社はチャットボットを導入したことで電話での問い合わせが2割ほど減少しました。
問い合わせが減った分、複雑な問い合わせに対応するための時間をより多く作り出せ、従業員の業務範囲の拡大にも成功しています。
教育:管理業務部門への問い合わせ削減で約400時間の業務削減

医療従事者向けにeラーニングを中心とした教育支援を行っている株式会社学研メディカルサポートでは、人事、法務、総務、経理といった管理業務部門への問い合わせが多く寄せられていることが大きな課題となっていました。
電話での問い合わせだけでなく、担当社員が直接呼び止められ質問されることも多く、そのたびに社員は他の業務を中断しなければなりませんでした。また、質問対応後は再び仕事に集中し直す必要があり、業務効率に影響したため、社内FAQとして「さっとFAQ」を導入しています。
導入前には、年間で約400時間の業務削減が見込まれていましたが、実際に導入してみると、当初の想定を大きく上回る時間と費用の節約を実現できています。
参考:株式会社サンソウシステムズ「医療従事者に心とコンテンツの両面で寄り添うためにさっとFAQで業務効率を大幅に向上」
AI接客の将来展望

AI技術の進化により、AI接客の可能性は広がっていきます。将来的には、以下の変化が予測されます。
- より人間らしい自然な対話:生成AIの進化により、AIの言葉遣いや応答が自然になり、人間と遜色のないコミュニケーションが実現します。
- 感情認識技術の向上:顧客の声のトーンや表情から感情を読み取り、相手の心情に寄り添った、温かみのある対応が可能になります。
- 予測的サポートの実現:行動データを分析し、顧客が困る前に解決策を提示。期待を一歩先回るサービスが、新たな顧客体験を生み出します。
AI技術の進化により、AI接客はより人間らしく、感情豊かで、予測的なものへと進化するでしょう。AI接客が顧客とのエンゲージメントを高め、ロイヤリティを向上させるための重要なツールとなると期待されます。
まとめ:AI接客は人間との協業でビジネスを次のステージへ導く

AI接客は、人間の仕事を奪うものではありません。AI技術は進化していくと予測されますが、人間が本来注力すべき付加価値の高い仕事に集中するためのパートナーとして役立ちます。AIとの協業で顧客体験を向上させ、ビジネスを次のステージへと導けるでしょう。
しかし、AI接客を効果的に活用するには、導入目的を明確にし、自社に最適なツールを選び、適切な運用体制を構築することが重要です。目的によっては、高機能なAIやロボットが不要な場合もあります。
株式会社サンソウシステムズが提供する「さっとFAQ」は、生成AIを活用してかんたんに会話データを作成できるハイブリッド型チャットボットツールです。ファイルやURLを指定するだけで会話データ作成をサポートしてくれるため、チャットボット構築の手間と時間を大幅に削減できます。
また、顧客や社内からの質問に自動対応できることはもちろん、会話データを蓄積し分析に活かすことも可能です。月額1万円という業界屈指のコストパフォーマンスで、企業規模に関わらず導入しやすいツールです。
30日の無料トライアルも実施しているので、AIを活用した接客を考えている場合はぜひお試しください。専任のスタッフが丁寧にサポートいたします。