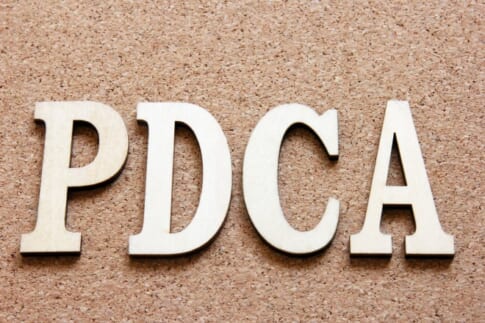2025年、製造業を取り巻く環境は、 ますます厳しさを増しています。 人手不足や原材料価格の高騰、サプライチェーンの脆弱性、 環境問題への対応など、中小企業を経営している方々は、 日々数多くの課題に直面しているでしょう。
そこで本記事では、 製造業が抱える7つの主要な課題を徹底解説し、中小企業が生き残るための具体的な道筋をわかりやすく紹介します。 解決策を参考にしながら、長く生き残る企業へと成長しましょう。
弊社では、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)国内トップシェアを誇る現場帳票システム「i-Reporter」の導入支援をおこなっています。
導入することで、紙の現場帳票の「記入・報告・管理」すべてのペーパーレス化を実現し、生産性向上につなげられます。
要件定義から設計・導入、その後の運用管理まで、お客様に寄り添った伴走支援が可能ですので、ご一緒に現場の生産性向上に向けた業務課題を整理していきましょう。
サービス資料を用意しましたので、あわせてこの機会にこちらから無料でダウンロードしてみてください。
導入実績4,000社以上
目次
製造業における課題

2025年、製造業は数多くの課題に直面しています。これらの課題は中小企業の経営を圧迫し、競争力を低下させる要因となりかねません。そこでまずは、製造業が抱える主要な7つの課題について詳しく解説します。
人手不足と高齢化
製造業における人手不足は深刻な問題です。少子高齢化が進む日本において、労働人口の減少は避けられません。特に、熟練技能者の高齢化が進み、技術の承継が困難になっている現状があります。
厚生労働省の「労働経済の分析」によると有効求人倍率は上昇傾向にあり、人手不足がより深刻化していることがわかります。
参考:令和5年版労働経済の分析
原材料価格の高騰
世界的な資源需要の増加や地政学的なリスクにより、原材料価格は高騰しています。鉄鋼や原油、非鉄金属など、製造業に欠かせない原材料の価格上昇は、製品の製造コストを押し上げ、企業の収益を圧迫します。
サプライチェーンの脆弱性
近年、自然災害や感染症の世界的流行などにより、サプライチェーンの脆弱性が発覚しました。特定の地域や企業に依存したサプライチェーンは、供給途絶のリスクを抱えています。部品や原材料の調達が滞ると生産計画に大きな影響が出て、納期遅延や機会損失につながります。
環境問題への対応
地球温暖化対策や資源保護の観点から、製造業は環境問題への対応を迫られています。CO2排出量の削減や省エネルギー化、廃棄物の削減など、環境負荷を低減するための取り組みが不可欠です。また、環境規制の強化により、対応が遅れると事業継続が困難になる可能性もあります。
デジタル化の遅れ
製造業におけるデジタル化の遅れは、生産性向上や競争力強化の妨げとなっています。IoTやAI、ビッグデータなどのデジタル技術の導入が進んでいない企業は、業務効率化や品質向上で後れを取り、市場の変化に対応できなくなる恐れがあります。
経済産業省の資料にも、デジタル人材の確保・育成が重要視されていることから、積極的に解決すべき課題と言えるでしょう。
参考:ものづくり企業におけるデジタル化に対応した人材の確保・育成
変化する顧客ニーズ
顧客ニーズは多様化し、変化のスピードも加速しています。大量生産・大量消費の時代は終わり、多品種少量生産やカスタマイズ対応が求められるようになりました。顧客の要求に応じた製品を迅速に提供するためには、柔軟な生産体制や高度な技術力が不可欠です。
法規制の強化
労働安全衛生法や環境関連法、個人情報保護法など、製造業を取り巻く法規制は年々強化されています。これらの法規制を遵守するためには、適切な管理体制や設備投資が必要です。しっかりとした社内体制を整えなければ、法律を遵守した企業運営は困難になるでしょう。
経済産業省が示す製造業の課題と対策

経済産業省も製造業が直面する課題を深く認識し、さまざまな対策を講じています。ここでは、経済産業省の課題認識や具体的な支援策について解説します。
経済産業省の課題認識
経済産業省は製造業が直面する課題として、主に以下の点を挙げています。
| 課題 | 詳細 |
|---|---|
| 国際競争の激化 | 新興国の台頭などにより、国際的な競争が激化しており、日本企業の競争力強化が急務となっている |
| 国内市場の縮小 | 少子高齢化による労働人口の減少や消費の低迷により、国内市場が縮小傾向にある |
| 技術革新の遅れ | デジタル技術の活用や新たなビジネスモデルの創出が遅れており、国際的な競争において不利な状況にある |
| 人材不足 | 熟練技能者の高齢化や若手人材の確保難により、人材不足が深刻化している |
上記の課題に対し、経済産業省は製造業の「稼ぐ力」の向上を目指してさまざまな政策を打ち出しています。
具体的な支援策
経済産業省は上記のような課題を克服するために、以下のような具体的な支援策を実施しています。
| 支援策 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 生産性向上支援 | ・IoTやAIなどの導入支援 ・業務効率化コンサルティング | ・中小企業の生産性向上 ・コスト削減 |
| 技術開発支援 | ・研究開発費の補助金 ・共同研究の推進 | ・革新的な技術の開発 ・競争力強化 |
| 海外展開支援 | ・海外市場調査 ・展示会出展支援 ・海外投資支援 | ・海外市場への進出 ・販路拡大 |
| 人材育成支援 | ・職業訓練 ・技能検定 ・OJT支援 | ・人材育成 ・技能伝承 |
| 事業承継・M&A支援 | ・事業承継計画策定支援 ・M&A仲介支援 | ・後継者不足の解消 ・事業の継続 |
上記の支援策は自社の課題やニーズに合わせて、最適な方法を選択することが重要です。
製造業における課題解決のためのチェックリスト

製造業が直面する課題は多岐にわたりますが、効果的な解決策を見つけるためには体系的なアプローチが不可欠です。ここからは、課題解決のためのチェックリストを紹介します。
このチェックリストは現状分析から実行、評価までのプロセスを網羅しており、各ステップを丁寧に進めるとより効果的な課題解決が期待できます。
現状分析
まず、自社の現状を正確に把握することが重要です。以下の項目について、客観的なデータを基に分析をおこないましょう。
| 分析項目 | 詳細 |
|---|---|
| 事業の状況 | 売上や利益、市場シェアなどを分析し、強みと弱みを明確にする |
| 生産体制 | 生産能力や稼働率、不良率などを分析し、改善点を見つけ出す |
| DXの現状レベル | デジタル技術の導入状況やデータ活用状況などを評価し、遅れている分野を特定する |
| 人材 | 従業員のスキルや年齢構成、離職率などを分析し、人材不足や高齢化の問題を把握する |
| 設備 | 設備の老朽化状況やメンテナンス状況などを確認し、更新の必要性を検討する |
目標設定
現状分析の結果を踏まえ、具体的な目標を設定しましょう。目標は、SMARTの原則に基づいて設定することが重要です。
SMARTの原則とは、目標設定の際に用いる以下の5つの基準のことを指します。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| Specific(具体的) | 目標は具体的に記述し、誰が見ても理解できるようにする |
| Measurable(測定可能) | 目標の達成度を測定できる指標を設定する |
| Achievable(達成可能) | 現実的な範囲で、達成可能な目標を設定する |
| Relevant(関連性) | 企業の戦略目標と整合性の取れた目標を設定する |
| Time-bound(期限) | 目標達成の期限を設定する |
例えば「生産性を1年以内に10%向上させる」「不良率を6カ月以内に5%削減する」といった具体的な目標を設定すると、次の行動を起こしやすいです。
解決策の検討
目標を達成するために、さまざまな解決策を検討します。以下の視点からアイデアを出し合い、最適な解決策を見つけましょう。
| 施策 | 詳細 |
|---|---|
| デジタル技術の活用 | IoTやAI、RPAなどのデジタル技術を活用し、業務効率化や自動化を図る |
| サプライチェーンの見直し | サプライチェーンの最適化を図り、リスク分散やコスト削減を目指す |
| 人材育成 | 従業員のスキルアップを図り、多能工化や専門性の向上を促進する |
| 設備の更新 | 老朽化した設備を更新し、生産性向上や安全性向上を図る |
| 業務プロセスの改善 | 業務プロセスを見直し、無駄を排除して効率化を図る |
計画策定
検討した解決策の中から最適なものを選択し、具体的な実行計画を策定します。計画には、以下の項目を含めましょう。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 具体的なアクションプラン | 誰が、いつ、何を、どのようにおこなうかを明確にする |
| 必要なリソース | 予算や人員、設備など、必要なリソースを明確にする |
| スケジュール | 各アクションの開始日と終了日を設定する |
| 責任者 | 各アクションの責任者を明確にする |
| KPI(重要業績評価指標) | 目標達成度を測るためのKPIを設定する |
計画は関係者間で共有し、進捗状況を定期的に確認することが重要です。
実行
策定した計画に基づき、解決策を実行します。実行段階では、以下の点に注意しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 進捗管理 | 計画通りに進んでいるか、定期的に進捗状況を確認する |
| 問題発生時の対応 | 計画通りに進まない場合、原因を特定して迅速に対応する |
| 関係者との連携 | 関係者と密に連携し、情報共有や協力体制を構築する |
| 柔軟な対応 | 状況の変化に応じて、計画を柔軟に見直す |
評価
解決策の実行後、目標達成度を評価します。KPIを基に客観的なデータを収集し、効果測定をおこないましょう。評価結果に基づいて改善点を見つけ出し、次のアクションにつなげることが重要です。
| ステップ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 現状分析 | 事業、生産体制、DXレベル、人材、設備などの現状を分析 | 課題の明確化 |
| 目標設定 | SMARTの原則に基づき、具体的な目標を設定 | 目指すべき方向性の明確化 |
| 解決策の検討 | デジタル技術、サプライチェーン、人材育成など、さまざまな視点から解決策を検討 | 最適な解決策の発見 |
| 計画策定 | アクションプラン、リソース、スケジュール、責任者、KPIなどを明確にする実行計画を策定 | 計画的な実行の準備 |
| 実行 | 計画に基づき、解決策を実行 | 課題解決の実行 |
| 評価 | KPIを基に、目標達成度を評価 | 効果測定と改善点の抽出 |
上記のチェックリストを活用してPDCAサイクルを回すことで、継続的な改善を図りながら製造業が抱える課題を克服することが可能です。
製造業におけるDX推進のステップ

製造業を取り巻く環境が大きく変化する中、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は中小企業が生き残るための重要な戦略です。しかし、DXをどのように進めていけば良いのかわからないという方も多いでしょう。
ここでは、製造業におけるDXの定義と目的を明確にし、具体的な推進ステップについて解説します。
製造業におけるDXの定義と目的
製造業におけるDXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスや組織文化、ビジネスモデルを変革し、競争力を高めることです。経済産業省はDXを「企業がデータとデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義しています。
製造業においては、この定義に基づき、以下のような目的でDXを推進します。
| 目標 | 内容 |
|---|---|
| 生産性の向上 | IoTやAI、ロボティクスなどの技術を活用し、製造プロセスの効率化・自動化を図る |
| 品質の向上 | データ分析に基づき、不良品の発生を抑制して品質管理を高度化する |
| コスト削減 | 無駄な工程を省き、サプライチェーン全体を最適化することでコストを削減する |
| 顧客満足度の向上 | 顧客ニーズを的確に把握し、製品やサービスの開発・提供に反映することで顧客満足度を高める |
| 新たな価値創造 | デジタル技術を活用し、これまでになかった新たな製品やサービスを開発して市場を開拓する |
DX推進のステップ
DXを成功させるためには、以下のステップを踏むことが重要です。
| ステップ | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1. DX推進の目的とビジョンを明確にする | DXによって何を実現したいのか、具体的な目標を設定する | 経営戦略に基づいて自社の強みや弱みを分析し、DXによって解決したい課題を明確にする。 例えば、「生産性を20%向上させる」「不良品率を50%削減する」などの具体的な数値目標を設定する。 |
| 2. DX戦略を策定する | 目標達成のためには「どのようなデジタル技術を活用すべきか」「どのような施策を実行すべきか」といった計画を立てる | 現状の業務プロセスを分析し、デジタル化できる部分を洗い出す。 IoTやAI、クラウド、ビッグデータなど、最適な技術を選定して導入計画を策定する。 また、投資対効果を考慮し、優先順位をつける。 |
| 3. 必要な人材やスキルを定義する | DXを推進するために必要な人材を確保し、スキルを育成する | DXを推進するためにはITスキルだけでなく、データ分析やプロジェクトマネジメント、チェンジマネジメントなど、さまざまなスキルが必要である。 社内人材の育成や外部からの採用、専門家への委託など、最適な方法で人材を確保する。 |
| 4. 推進プロセスを策定する | DXを円滑に進めるための組織体制や役割分担、コミュニケーション方法などを明確にする | DX推進チームを立ち上げ、各部門の代表者を含めた全社的な協力体制を構築する。 定期的な進捗報告会を開催し、課題や改善点を共有する。 また、現場の意見を積極的に取り入れ、改善サイクルを回す。 |
| 5. DX推進状況を評価し、結果に基づいて戦略やリソース配分を見直す | DXの成果を定期的に評価し、改善点を見つけて戦略を修正する | KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に進捗状況をモニタリングする。 目標達成度や投資対効果、顧客満足度などを評価し、改善点があれば速やかに戦略やリソース配分を見直す。 |
上記のステップを着実に実行することで、製造業におけるDXを成功に導くことができます。中小企業においてはスモールスタートで成功事例を作り、徐々に範囲を拡大していくことがおすすめです。
製造業におけるDX成功事例

製造業におけるDXは業務効率化や生産性向上、コスト削減など、多岐にわたる効果をもたらします。ここでは、最新技術を活用して成果を上げている企業の事例を紹介します。
事例1:天津電装電子有限公司(TDE)
天津電装電子有限公司(TDE)は、膨大な紙を消費する帳票のデジタル化が重要課題でした。生産や点検の記録などに200種類以上の帳票を使い、年間で何十万枚もの紙を消費していたからです。
しかも帳票の中には10~20年保管しなければいけないものも存在し、多くのスペースを取られていました。さらに、過去の帳簿が必要になったときは、その膨大な資料の中から探し出さなければならず、移動にも時間がかかっている状態です。
そこで、帳簿システム「i-Reporter」を導入し、年間30万枚の紙を削減しました。他のソフトウェアやシステムと比べると設計の自由度が高いため、ニーズに合わせたカスタマイズを実施しながら愛用しています。
事例2:Showa Create Cebu, Inc.
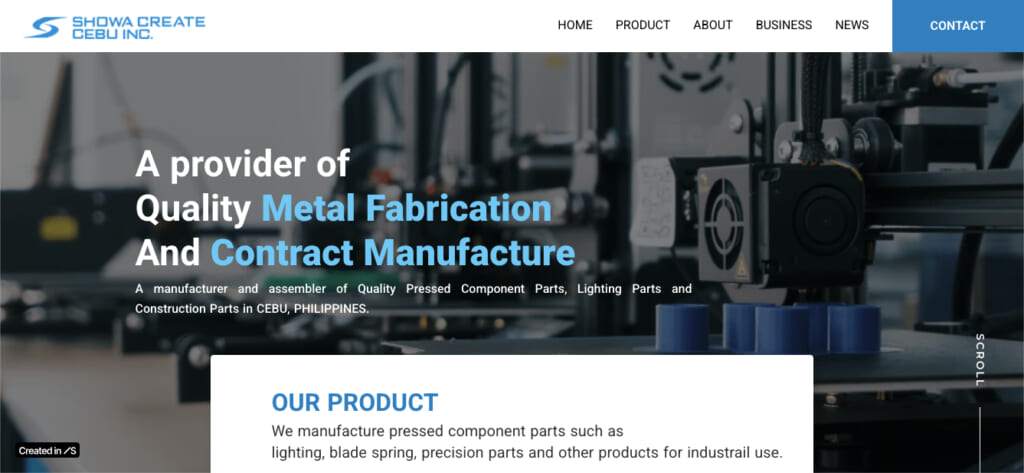
Showa Create Cebu, Inc.は、使っている帳票の種類は相当な数にのぼり、生産に関するものだけでも20種類以上あります。特に、生産や品質管理の帳票は毎日記入するものが多い上、印刷する用紙や帳票の管理にまつわるコストは高額でした。
そこで、帳簿システム「i-Reporter」を導入したところ、入力業務に手間がかからず、日付や選択肢などの項目はほぼミスなく入力できるようになっています。
また、従来の方法であれば作業前に作業標準書を事務所までわざわざ取りに行く必要がありましたが、帳簿システムの機能を活用することでこれらの手間も省けます。帳票のレイアウトを残すことができたため、従業員が抵抗を覚えることなく現場に定着しました。
参考:導入事例Showa Create Cebu, Inc.様
事例3:株式会社名村造船所

株式会社名村造船所では、業務の効率化を進めるために現場の管理者や関係者にヒアリングを行ったところ、紙の帳票が多いという声が集まりました。これまでは情報が紙のままで管理されていたことも課題として浮き彫りになっていたため、帳簿システムの導入を決めています。
その結果、情報を連携させながら管理できるようになったため、情報共有のスピードが大幅に上がりました。また、帳簿システムに対応しているiPadを現場に持参すれば、リアルタイムで状況をチェックでき、現場からの要望に即座に対応することができています。
製造業の課題克服に向けた最新技術とイノベーション

製造業が直面するさまざまな課題を克服するため、最新技術とイノベーションの導入が不可欠です。ここでは、中小企業が競争力を高め、持続的な成長を遂げるための主要な技術領域とその活用方法について解説します。
AI/IoT:データ活用による効率化と自動化
AI(人工知能)とIoT(Internet of Things)の融合は、製造業におけるデータ活用を飛躍的に向上させ、効率化と自動化を推進します。
工場内のさまざまなセンサーから収集されるデータをAIが解析することで、設備の異常検知や生産ラインの最適化、品質管理の高度化などが実現します。例えば、AIを活用した画像認識技術を導入すれば、不良品の自動検知が実現し、品質管理コストを削減することが可能です。
しかし、IoT導入にはセキュリティリスクの管理やIT人材の不足といった課題も存在します。これらの課題を克服するためには、セキュリティ対策の強化と従業員のITスキル向上に向けた教育が不可欠です。
ロボティクス:省人化と生産性向上
人手不足が深刻化する製造業において、ロボティクスの導入は省人化と生産性向上に大きく貢献します。従来、人が行っていた単純作業や危険な作業をロボットに代替させることで、労働環境の改善と人的ミスの削減が期待できます。
さらに、AIとロボティクスを組み合わせれば、より高度な作業の自動化も可能です。例えば、AIが作業指示を出し、ロボットがその指示に従って作業をおこなうと柔軟な生産体制を構築できます。
3Dプリンティング:多品種少量生産とカスタマイズ対応
3Dプリンティング技術は多品種少量生産やカスタマイズ対応を可能にし、顧客ニーズへの柔軟な対応を支援します。従来の製造方法では困難だった複雑な形状の部品や、少量生産の製品を比較的容易に製造できます。
これにより、試作品の迅速な作成や顧客の要望に応じたカスタマイズ製品の提供が実現するでしょう。また、3Dプリンティング技術は、設計段階での自由度を高めて革新的な製品開発を促進します。
マテリアルズ・インフォマティクス:新素材開発の加速
マテリアルズ・インフォマティクス(MI)は、材料開発にAIやデータ科学を活用するアプローチです。過去の実験データやシミュレーション結果をAIが解析することで、新しい材料の設計や既存材料の性能向上を効率的におこなえます。
これにより、高性能な新素材の開発期間を大幅に短縮し、製品の競争力強化に貢献します。
サステナブルテクノロジー:環境負荷低減と資源循環
環境問題への意識が高まる中、製造業においてもサステナブルテクノロジーの導入が重要です。省エネルギー技術や再生可能エネルギーの利用、廃棄物の削減・リサイクル技術などを導入すれば環境負荷を低減し、持続可能な生産体制を構築できます。
例えば、工場内のエネルギー消費量を最適化するシステムを導入すると、CO2排出量やエネルギーコストを削減することが可能です。
製造業における課題を解決しよう

製造業を取り巻く環境は常に変化しているため、常にアンテナを張り、最新の情報や技術を取り入れながら柔軟に対応していかなければいけません。
課題解決への道のりは決して平坦ではありませんが、一歩ずつ着実に進んでいくことで、必ず光明は見えてくるはずです。諦めずに自社の強みを活かし、新たな技術や発想を取り入れながら未来を切り拓いていきましょう。
株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
現場帳票のシステム化を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか?」といった課題や不安がつきものです。
そのような企業様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。
まず、やるべきことを整理するだけでもメリットになります。
お話を伺いたい方は、無料の『ちょこっと相談室』で、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。