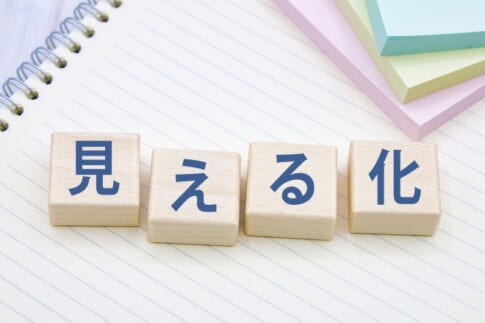製造業における出荷ミスは、顧客の個人情報が流出する危険性や返品・交換に伴うコストの増加など、さまざまな側面に影響を及ぼします。現在はインターネットショッピングの普及により、SNSや口コミから情報収集をおこない商品を購入する人が多いです。
製造業における出荷ミスは、顧客の個人情報が流出する危険性や返品・交換に伴うコストの増加など、さまざまな側面による影響があります。
そこで今回は、品質を維持しながら出荷ミスを減らすためのプロセスの改善方法について紹介します。
目次
出荷ミスが与える企業への影響
出荷ミスは、自社だけでなく取引先の企業にも多大な影響を及ぼします。一度の出荷ミスで、機密情報が他者へ流出したり口コミでの評価が悪くなったりする可能性があります。出荷ミスがどのような悪影響を及ぼすのか、見ていきましょう。
顧客満足度の低下
まず一つ目が、顧客満足度の低下です。出荷ミスが発生すると誤った商品が顧客に届いたり、商品の到着が遅れたりします。これにより、顧客は不満や不信感を抱き、企業は顧客の信頼を失います。顧客満足度の低下は、リピート購入の減少や口コミでの低評価につながり、結果的に新規顧客の獲得機会の喪失にもなります。
また、出荷内容は企業にとって非常に大切な個人情報になるため、ライバル企業やその業界に関連した企業に対して情報が流出すると、営業戦略が筒抜けになる可能性があります。個人情報を流出させしまった場合、取引企業との信頼関係が崩壊する事態になりかねません。
コストの増加
二つ目が、コストの増加です。間違った商品を出荷することで、返品や再出荷が必要になり追加の物流コストが発生したり、顧客への補償や商品の割引提供をしたりなどの費用がかかります。場合によっては、賠償問題に発展する可能性もあります。これらの追加コストは、企業の収益に影響を及ぼし、利益率の低下を引き起こすでしょう。
ブランドイメージの低下
三つ目はブランドイメージの低下です。近年ではネットショッピングが普及し、SNSやレビューサイトを参考にして商品を購入する機会が増えています。インターネットでの口コミ評価が低下すると、その会社のブランドイメージが悪くなり、ブランドイメージの低下につながります。
出荷ミスの原因
製造業において、些細な原因から出荷ミスが発生します。そこで、主な原因を3つ詳しく説明します。
ヒューマンエラー
システムの使用方法や商品の管理方法など、従業員が適切な教育を受けていない場合、出荷プロセスにおいてミスが発生しやすくなります。特に新入社員やパート従業員に対して、部門間やチーム間での情報伝達方法やデータの入力方法の教育が不十分な場合、誤った情報に基づいて出荷作業がおこなわれたりデータの誤入力によるトラブルが発生したりします。少しでもミスを減らすために、普段から従業員同士でのコミュニケーションが必要です。
システムエラー
管理システムにバグがある場合や複数のシステム間での連携が機能していない場合に、正確なデータが反映されなかったり更新がされなかったりして、出荷ミスが発生します。システムの不具合を見つけた際には、早めのメンテナンスをおこなうことが重要です。
手順の不備
工程の手順書に不備があったり作業指示が曖昧だったりした場合、従業員が正しい手順を理解できず、誤った操作をおこなう可能性があります。また、出荷プロセスが長期間見直されていない場合、古い手順や非効率的な手順が残ってしまいミスにつながりやすくなります。
出荷ミスを防止する基本対策
出荷ミスを防止するためには、従業員の教育やシステム・プロセスの改善など、さまざまな対策が必要です。そこで、出荷ミスを防止する基本対策を紹介します。
ヒューマンエラー対策
出荷業務に関する基本的な知識や手順を徹底的に新入社員に教えるのはもちろんですが、既存の従業員に対しても定期的に手順やシステムの使い方の再教育をおこなうことも重要です。アップデートされた最新の情報を手順書に書き起こして配布するだけでなく、直接指導をすることで、管理側と作業員との間に認識のずれをなくすとともに、疑問点などもその場で解消できます。
また、手順やシステムの使い方のシミュレーショントレーニングを取り入れることで、実践力を養えるため、現場でのミスを減らす効果が期待できるでしょう。
現場に合わせた自動化ツールを導入することで、計算ミスやデータ入力ミスなどのヒューマンエラーを極限まで減らすことが可能です。システムを自動化することで紙でのデータ保存が不要になり、作業エリアの整理整頓がおこなえ、作業に必要なもののみを現場に配置することで出荷ミスのリスクを低減できます。
システムエラー対策
長期間に渡り同じシステムを使い続けているとセキュリティが脆弱になり、情報漏洩の危険性が高まります。セキュリティを向上する以外にも定期的なソフトウェアのアップデートをおこなうことで、システムの不具合を修正できます。また、データのバックアップも併せておこなうことで、システムトラブル時に迅速な対応と復旧が可能です。
プロセスの改善
出荷作業に関する手順書を作成し、全従業員へ周知をおこないます。手順書に変更点が生じた場合は早急な最新情報の反映が重要です。定期的に手順書を見直すことで、業務効率の向上やプロセスの簡略化が可能になります。
出荷ミス防止の具体的な対策方法
出荷ミスを防ぐためのシステムの使用方法や改善方法を紹介します。
帳票電子化ツールの活用
作業現場で使用されている紙ベースの報告書や伝票などのデジタル化によって、データの正確性が向上します。デジタル化ツールを活用することで、手書きによる誤字脱字や読みづらさをなくし、入力ミスの防止が可能です。
「i-Reporter」は導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)、国内トップシェアを誇る現場帳票システムです。
導入することで、紙の現場帳票の「記入・報告・管理」全てのペーパーレス化を実現。さまざまな業務の効率化やDX化に繋げることができます。
また、弊社株式会社サンソウシステムズでは、要件定義から設計・導入、その後の運用管理まで、お客様に寄り添った伴走支援が可能です。
ぜひ、ご一緒に現場の業務課題を整理していきましょう。サービス資料を用意しましたので、併せてこの機会にこちらから無料でダウンロードしてみてください。
導入実績4,000社以上
ピッキングシステムの改善
紙で管理していたピッキングリストをデジタル化することで、情報の更新や共有が簡単におこなえます。キーワードや日時を使用し、ピンポイントで必要な情報を読み取ることが可能です。また、デジタル化しない場合は紙媒体の保管スペースを確保する必要があるため、限りある作業スペースを圧迫し、作業効率が低下するおそれがあります。作業員の働きやすい環境を作るためにも、必要に応じたデジタル化は必須です。
品質管理の強化
出荷前の品質管理項目のチェックリストを作成し、複数人で最終チェックをおこなうことで、出荷ミスを防止できます。また、品質管理に特化した部門や監査チームを結成し、定期的に品質監査を実施することで、現場での問題点を早期に発見・対策可能です。品質管理の徹底により、製品や企業への信頼性の向上が期待できます。
帳票電子化ツールの導入に成功した事例
実際の現場において、デジタル化ツールの導入に成功した事例を紹介します。
京都電機器株式会社

引用:京都電機器株式会社
携帯電話やパソコンの部品を製造する機械の電池の他、発電機に内蔵されているインバーター装置やバッテリーフォークリフトの充電器を製造しています。
帳票を電子化する前は、製品15台の出荷記録を1枚の紙に記載していました。そのため、1台分の記録スペースがとても小さく、横列との見間違えによるチェック忘れ、視認性や可読性など、保管の品質にも問題が生じていました。
そこで株式会社シムトップスが提供する「i-Reporter」を導入。製品1台につき1帳票で構成されているため、現場の声を反映させた記録しやすく見やすい電子帳票が実現できました。また、記録作業と写真撮影、画像の添付が一度におこなえるようになり、撮影後にチェックシートと画像の紐づけをおこなう必要がなくなりました。
伊藤精工株式会社

引用:伊藤精工株式会社
エンジン駆動系部品、ワイパー部品、カーエアコン部品、ラジエーター部品、各種センサー部品など自動車部品の製造と販売をしています。
工場にある膨大な量の紙の帳票を電子化したい、帳票のデータを集計・管理する時間の削減、全工場間で情報を共有することが課題でした。
そこで株式会社シムトップスが提供する「i-Reporter」を導入。帳票を集計・管理する手間を月37.5時間の削減に成功し、場所にとらわれない申請と管理が可能になったことで、申請承認作業のスピードアップが実現できました。
株式会社ミントウェーブ

引用:株式会社ミントウェーブ
自治体・民間企業・文教向けのシンクライアントシステムやシンクライアント応用機器、電力系統・設備の監視制御システム、ERP活用・設計支援システムといった、さまざまな分野での製品やシステム、サービスを提供している情報機器メーカーです。
紙の在庫管理表に手書きで記入することで記入漏れや間違いが発生したり、正しい在庫数が月末にならないとわからなかったりといった課題がありました。
そこで株式会社シムトップスが提供する「i-Reporter」を導入。画面をタップするだけで作業ができるため、作業時間を約90%削減することに成功しました。また、在庫がリアルタイムに管理できるため、不要な資産を抱え込む必要がなくなりました。
出荷ミス防止における継続的な改善方法
出荷ミスは一度だけでなく、継続的に防止する必要があります。そこで、出荷ミスを継続的に防止するための改善方法を紹介します。
PDCAサイクルの導入
PDCAサイクルを効果的に組み立てることで、品質向上や顧客満足度の向上が期待できます。製造業におけるPDCAサイクルの具体例を紹介します。
〇Plan(計画)
不良品率の低減や納期の遵守など具体的かつ測定可能な目標を設定し、「生産効率を5%向上させる」などの達成基準を明確にします。その後、生産ラインのデータや品質検査の結果を活用し現状の分析をおこない、改善計画の立案をします。
〇Do(実行)
立案した改善計画を実施します。実施している過程で進捗状況を細かく記録し、予期せぬ問題が発生した場合は迅速に対処します。
〇Check(評価)
実施した内容を分析し、設定された目標が達成されたかを確認します。評価の結果、新たな問題点や追加の改善点が必要な箇所の特定をおこないます。
〇Act(改善)
効果のあった改善案で新しい手順書を作成したり、マニュアルに追加したりします。新しく追加された手順や方法を全従業員に周知するために勉強会やトレーニングをおこない、作業に不備がないように教育を徹底します。
PDCAサイクルを継続的に実施することで、新たな改善点や次の計画が容易に作成でき、さらなる業務効率の向上と品質改善が期待できるでしょう。
定期的なレビューとフィードバック
定期的に作業員からフィードバックをもらうことで、現場での問題点や実施した改善効果のデータ収集が可能です。収集されたデータを活用することで、次回の改善活動に反映できます。また、第三者に監査を依頼することで、社内では見落としている問題点を見つけたり、対策を講じるためのヒントを得られたりする可能性があるため、非常に効果的です。
出荷ミスを防ぐために

出荷ミスを防ぐためには、徹底したヒューマンエラー対策とシステムの改善が必要です。従業員の教育を強化し、作業環境を整えることでミスを減らせます。また、デジタル化や自動化ツールを活用により、データ入力や在庫管理の精度を向上できます。さらに、手順書の作成やレビューとフィードバックを継続的に実施することで、信頼性の高い出荷プロセスの構築が可能です。
株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
現場帳票のシステム化を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか」といった課題や不安がつきものです。
そのような企業様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。
まず、やるべきことを整理するだけでもメリットになります。
お話を伺いたい方は、無料の『ちょこっと相談室』(Teams:オンライン)で、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。