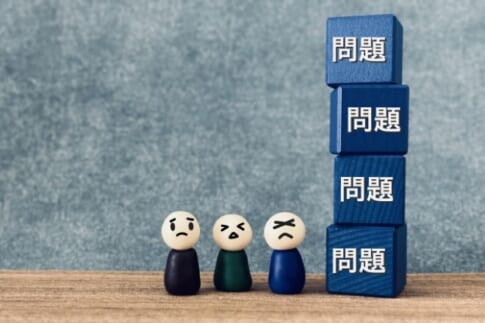現品票とは、製品がどこにあり何であるかを明確にする、まさに現場の「身分証明書」のような存在です。製造業でよく使用されますが、現品票の役割や納品書、受領書との違いがわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、現品票の基本や必要性、作成方法、そして運用上の課題とペーパーレス化による解決策まで現品票に関するあらゆる情報をわかりやすく解説します。
導入実績4,000社以上
現品票とは

現品票(読み方:げんぴんひょう)とは、製造業や物流業の現場で、製品や半製品、部品、材料などの現物を出荷・納品する際に添付される伝票のことです。現品票によって、現品が「何であるか」を示す役割を果たします。
英語では、分野によって「part tag」「label」「identification tag」「kanban card」などと表現されます。
製品のいわば「身分証明書」である現品票で記載するのは、以下の内容です。
- 品名: 現品が何であるか
- 品番: 現品を特定するためのコード
- 数量: 現品の数量
- ロット番号: 製造ロットを特定するための番号
- 製造日: 現品が製造された日付
- 工程: 現品がどの工程にあるか
- 担当者: 現品を担当した作業者
これらの情報で、製品の所在や状態、数量などを正確に把握し、管理が可能になります。
現品票と関連書類との違い

現品票は製品や仕掛品などの個体を管理するための伝票ですが、納品書や受領書など、他の書類と混同されることがあります。本章では、現品票と関連書類との違いを明確に解説します。
納品書との違い
納品書は、商品やサービスを納品する際に、売り手側が買い手側に発行する書類です。納品物の明細や数量、金額などが記載され、請求書と合わせて用いることが多いです。通常、製品とは別に送付します。
一方、現品票は、製品そのものに添付される伝票であり、製品の種類や数量、品質、輸送先などが記載され、製品そのものに添付します。
受領書との違い
受領書は、納品された商品やサービスを受け取ったことの証明に、買い手側が売り手側に発行する書類です。納品書の内容を確認し、相違がなければ受領書を発行します。
現品票は、受領書のように受領の事実を証明するものではなく、あくまで製品の管理を目的としています。
出荷指示書との違い
出荷指示書は、倉庫や工場から製品を出荷する際に、担当者に対して指示を出すための書類です。出荷する製品の種類や数量、出荷先などが記載されます。
現品票は、出荷指示書に基づいて製品に添付され、その後の工程での管理に利用されます。
検収書との違い
検収書は、納品された製品やサービスが発注内容と合致しているかを確認(検収)した結果を記録する書類です。品質や数量、仕様などが確認され、問題がなければ検収書が発行されます。
製品の個体を管理する現品票は、検収作業の際に製品の特定や確認を容易にするために役立ちます。
発注書との違い
発注書は、製品やサービスを注文する際に、買い手側が売り手側に発行する書類です。発注する製品の種類や数量、単価、納期などが記載されます。
現品票は、発注書に基づいて製造された製品に添付され、その後の工程での管理に利用されます。
現品票の必要性

現品票は、製造業や物流の現場において製品の管理を効率化し、誤出荷を防ぎ、トレーサビリティ※を確保するために不可欠なツールです。本章では現品票がなぜ必要とされるのか、具体的な理由を解説します。
※トレーサビリティ:製品の製造から販売までの過程を追跡できる仕組み・システムのこと
入出庫の確認作業を効率化するため
現品票には、製品の品名や製品コード、数量、製造日など製品管理に必要な情報が集約されています。さまざまな情報が一目でわかるように表示されるため、入庫時や出庫時の確認作業が大幅に効率化されます。
また、正確な個数を迅速に把握できるため、在庫の過不足を防ぎ、スムーズな入出庫作業も実現可能です。
例えば、以下のような情報の記載で、確認作業を効率化できます。
| 項目 | 詳細 | 効果 |
| 品名 | 製品の名称 | 製品の識別 |
| 製品コード | 製品を特定する番号 | 誤認防止、システム連携 |
| 数量 | 製品の個数 | 在庫管理、ピッキング |
| 製造日 | 製品の製造日 | 品質管理、先入れ先出し |
| ロット番号 | 製造ロットを特定する番号 | トレーサビリティ、不良追跡 |
誤出荷を防ぐため
現品票は、誤出荷を防止する上でも重要な役割を果たします。出荷作業員は現品票に記載された情報を基に、出荷する製品が正しいかを確認しなければなりません。特に、類似した製品が多い場合や複数の製品を同時に出荷する場合には、現品票による確認が役立ちます。
以下の情報の記載で、誤出荷のリスクの低減が可能です。
- 出荷先
- 注文番号
- 製品の型番
- 数量
これらの情報の確認で、出荷作業員は出荷指示書と現品票の内容を照合し、誤った製品が出荷されるのを防げます。
トレーサビリティを確保するため
トレーサビリティとは、製品の製造から販売までの過程を追跡できる仕組み・システムのことです。ロット番号や製造日を記載する現品票は製品の製造履歴を追跡できるため、トレーサビリティの確保が可能です。
例えば、以下のようなケースで、現品票がトレーサビリティに役立ちます。
- 不良品が発生した場合:ロット番号の追跡で、同じロットの製品の特定・回収が可能
- 製品の品質に問題が発生した場合:製造日の追跡で、問題が発生した時期に製造された製品の特定・原因追及が可能
現品票に記載された情報の適切な管理で、製品のライフサイクル※全体にわたるトレーサビリティを確保し、品質管理の向上に貢献します。
※製品のライフサイクル:製品が市場に入ってから衰退するまでの間の売上や利益の推移を示すもので、製品や市場の成長プロセスは「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の4つに分類される
現品票を活用する際の注意点

現品票は、現場での作業効率化に不可欠なツールですが、効果を引き出すための注意点があります。本章では、現品票を活用する上で特に重要なポイントを解説します。
正しい情報に更新する
現品票は、常に最新の情報が記載されていることが重要です。製品の移動や加工状況の変更があった場合は、速やかに現品票の内容を更新しなければなりません。古い情報が記載されたままの現品票を使用すると、製品の誤った場所への移動や誤った作業の原因となります。
例えば、以下のようなケースでは、現品票の更新が必要です。
- 製品の加工段階が進んだ場合
- 製品の保管場所が変更になった場合
- 製品の数量が変更になった場合
- 製品の検査結果が判明した場合
現品票更新の徹底で、常に正確な情報に基づいて作業を進められ、ミスの発生を抑えられます。
紛失や破損に注意する
現品票は製品に取り付けられた状態で管理されることが多いため、紛失や破損のリスクがあります。現品票の紛失や破損によって判読できない状態になると、製品の所在や状態が把握できなくなり、作業効率の低下や誤出荷の原因となります。
現品票の紛失や破損を防ぐためには、以下のような対策が必要です。
- 現品票を製品にしっかりと固定する
- 現品票が水や油などで汚れないように保護する
- 現品票の保管場所を定める
万が一、現品票が紛失・破損した場合は、速やかに再発行し製品に取り付け直します。
運用に関する教育をおこなう
現品票の適切な運用には、現場の作業員全員が現品票の重要性を理解し、正しい使い方の習得が不可欠です。現品票の運用方法や注意点について、また、現品票の重要性を理解し正しく利用できるように、定期的な教育・訓練を実施し、作業員全体の意識向上を図ります。
教育内容としては、以下のような項目が挙げられます。
- 現品票の目的と役割
- 現品票の記載項目と意味
- 現品票の記入方法
- 現品票の更新方法
- 現品票の保管場所
- 現品票の紛失・破損時の対応
教育を通じて、作業員一人ひとりが責任感を持って現品票を取り扱うように意識づけることが、現品票の効果的な活用につながります。
現品票作成の完全ガイド

本章では、現品票の作成から管理まで一連の流れを詳しく解説します。基本項目や記入例はもちろん、印刷方法や管理方法、作成時の注意点、テンプレートの活用方法まで、現場ですぐに役立つ情報をご紹介します。
現品票の基本項目と記入例
現品票に必要な8つの基本項目は、製品の特定・管理に不可欠な情報です。
以下の表は、一般的な現品票の基本項目と記入例です。
| 項目 | 説明 | 記入例 |
| 現品票コード | 現品票を識別するための固有の番号 | 00001 |
| 品番 | 製品の型番や製品番号 | ABC-123 |
| 品名 | 製品の名称 | 〇〇製造機 |
| 数量 | 製品の個数 | 10個 |
| 製造日 | 製品の製造年月日 | 2025年4月1日 |
| ロット番号 | 製造ロットを識別する番号 | Lot.20240101 |
| 担当者 | 製品の製造または管理を担当する者 | 山田太郎 |
| 保管場所 | 製品の保管場所 | A倉庫1番棚 |
8つの項目の正確な記入で、製品の追跡や管理が容易になります。必要に応じて、検査日や有効期限、顧客名といった情報の追加も可能です。
現品票の印刷方法
現品票の印刷方法は、使用するプリンターや用紙、現品票の形式によって異なります。一般的には、以下の手順で印刷をおこないます。
- Excelなどの表計算ソフトや、専用の現品票作成ソフトを使用し、現品票のデータを作成
- プリンターにA4用紙や専用のラベル用紙など適切な用紙をセット
- 用紙サイズ、印刷品質、印刷枚数などの印刷設定
- 印刷の実行
小型プリンタと読み取り端末の活用で、その場で印刷・貼り付けが可能になり、作業効率の向上が期待できます。
現品票の管理方法
現品票の管理は、製品の所在を明確にし、誤出荷や紛失を防ぐために非常に重要です。以下の点に注意して管理をおこないます。
- 製品に直接貼り付けるか、製品を入れた容器に貼り付ける
- 剥がれないようにしっかりと貼り付ける
- 情報が常に最新の状態になるように更新を徹底
- 情報を台帳やシステムで一元管理
現品票の情報は、システムによる一元管理で、在庫管理やトレーサビリティを向上させることができます。
現品票作成時の注意点
現品票を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
- 正確な情報を記入する:誤った情報の記入は誤出荷や誤入庫の原因に
- 見やすい文字で記入する:手書きでの記入は、丁寧に誰が見ても読める文字で記入
- 耐久性のある用紙を使用する:破れにくい・水に強い用紙で現品票の紛失や破損を防止
- バーコードやQRコードを活用する:バーコードやQRコードの印字で読み取りが容易になり、入力ミスの削減が可能
現品票テンプレートの活用方法
現品票テンプレートの活用で、現品票の効率的な作成ができます。さまざまなサイトでExcel形式の現品票テンプレートを配布しており、中には無料でダウンロードできるものもあります。テンプレートを利用する際には、以下の点に注意しましょう。
- 自社の要件に合わせて、テンプレートをカスタマイズする
- 必要な項目がすべて含まれているか確認する
- 印刷時に、文字や罫線が正しく表示されるか確認する
現品票が抱える課題

現品票は、製造・物流現場において重要な役割を果たす一方で、いくつかの課題もあります。課題を理解し適切な対策を講じることで、より効率的な運用が可能です。
ヒューマンエラーが起きやすい
現品票は手書きで記入されることが多く、人為的なミス(ヒューマンエラー)が発生しやすい課題があります。例えば、数字の誤記や記入漏れなどが挙げられます。文字の判読が難しいケースも少なくありません。ヒューマンエラーは、誤出荷や在庫管理の混乱を招く原因です。
対策としては、記入項目の明確化、ダブルチェックの実施、デジタル化による入力支援などが挙げられます。特に、バーコードやQRコードの活用で、手入力によるミスを大幅に削減できます。
運送中にはがれる
現品票は製品に貼り付けて使用されるため、運送中に剥がれてしまうことが問題です。剥がれてしまうと、製品の追跡が困難になり、誤出荷や紛失のリスクが高まります。
対策としては、粘着力の強いラベルを使用する、現品票を保護するカバーを装着する、製品に直接印刷するなどの方法があります。また、剥がれにくい素材ラベルの選定も重要です。
運用・管理が難しい
紙の現品票は、発行や貼り付け、回収、保管といった一連の作業に手間がかかります。また、現品票の情報を手動でシステムに入力する必要があるため、二度手間が発生します。さらに、現品票の紛失や破損によって、情報の追跡が困難になることも少なくありません。
対策として、現品票管理システムの導入が有効です。現品票管理システムは、現品票の発行から管理までをデジタル化し、業務効率を大幅に向上できます。
国内トップシェアを誇る現場帳票システム「i-Reporter」も、運用・管理を容易にして業務効率を高められるシステムです。弊社では、「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けています。ぜひお気軽にご相談ください。
データの蓄積ができない
紙の現品票はデータとしての蓄積が難しいため、分析や改善に活用できません。例えば、どの製品がどの工程で滞留しているか、どの運送業者の配送品質が低いかといった情報の把握が困難です。
対策としては、現品票をデジタル化し、データを蓄積・分析できる仕組みの構築が重要です。これにより、ボトルネックの発見、業務プロセスの改善、品質管理の向上などさまざまな効果が期待できます。
課題を解決する現品票のペーパーレス化とは

現品票の運用には、ヒューマンエラー、紛失、管理の煩雑さ、データ蓄積の困難さといった課題がつきものです。課題を解決するのが、現品票のペーパーレス化です。
現品票管理システムとは
現品票管理システムとは、現品票の作成や発行、管理、追跡といった一連の業務をデジタル化し、効率化するシステムです。具体的には、以下のような機能が搭載されています。
- 現品票のデジタル作成・発行機能: パソコンやタブレット端末から必要な情報を入力して現品票を作成し、発行する
- バーコード・QRコードによる自動認識機能: 現品票に印刷されたバーコードやQRコードの読み取りで製品情報を瞬時に認識し、入出庫管理や在庫管理に役立てる
- リアルタイムな在庫管理機能: 現品票の情報を基にリアルタイムで在庫状況を把握する
- トレーサビリティ機能: 製品の製造から出荷までの履歴を追跡する
- データ分析機能: 蓄積された現品票のデータを分析し、業務改善に役立てる
現品票管理システムの機能を活用することで、従来の紙ベースの現品票管理における課題を解決し、業務効率化やコスト削減、ミスの防止、トレーサビリティの向上を実現できます。
現品票を含む現場帳票のペーパーレス化を検討している方におすすめしたいのが、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)国内トップシェアを誇る現場帳票システム「i-Reporter」です。より簡単に、ミスのない、すばやい入力が可能なため、生産性向上や業務効率化につなげられます。
弊社では、「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けています。ぜひお気軽にご相談ください。
現品票管理システムのメリット・デメリット
現品票管理システムの導入を検討する際には、システムのメリット・デメリットを理解した上で、自社の状況に最適なシステムの選択が重要です。
メリット
- 業務効率化:
手書き作業や転記作業が不要になり、入力ミスも削減されます。また、リアルタイムな在庫管理により、迅速な意思決定が可能です。 - コスト削減:
紙代、印刷代、保管スペースなどのコストを削減できます。また、人的ミスの削減による損失防止にもつながります。 - ミスの防止:
システムによる自動チェック機能により、入力ミスや誤出荷の防止が可能です。 - トレーサビリティの向上:
製品の製造から出荷までの履歴を正確に追跡できます。 - データ分析の活用:
蓄積されたデータの分析で、需要予測や在庫最適化などさまざまな業務改善に役立てられます。 - ペーパーレス化の推進:
紙の使用量を削減し、環境負荷の低減が可能です。
デメリット
- 導入コスト:
初期費用やランニングコストが発生します。 - システム選定の難しさ:
数多くのシステムが存在するため、自社に最適なシステムを選定するには手間がかかります。 - 運用ルールの策定:
システムの効果的な運用には、適切な運用ルールを策定しなければなりません。 - 従業員への教育:
システム導入後、従業員への操作教育が必要です。 - システム障害のリスク:
システム障害が発生した場合、業務が停止してしまう可能性があります。
現品票管理システムの導入は、初期コストや運用体制の構築が必要となるものの、長期的に見れば業務効率化やコスト削減、ミスの防止、トレーサビリティの向上など、多くのメリットをもたらします。導入を検討する際には、自社の課題やニーズを明確にし、最適なシステムの選定が重要です。
現品票を理解して、現場の効率化を実現しよう

現品票を正しく理解し活用することで、現場のさまざまな課題を解決し、効率化を実現できます。特に現品票管理システムの導入は、業務効率化を促進する方法です。
現品票管理システムの導入を検討している場合は、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)国内トップシェアを誇る現場帳票システム「i-Reporter」がおすすめです。「i-Reporter」は、工程管理表や作業指示票、検査成績書、品質管理表などさまざまな紙の現場帳票を電子化し、現場が抱える課題を解決します。
しかし、システムを導入したくても「そもそも自社の課題がわからない」「システムをどのように活用すれば良いかわからない」とお悩みの方もいるでしょう。
弊社では、お客様のシステム導入を丁寧に支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けています。ぜひお気軽にご相談ください。