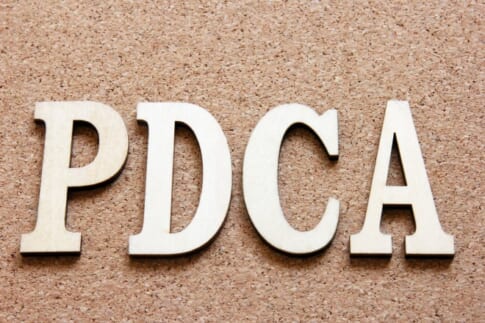多くの企業でDX推進が加速する昨今、DX推進の一つとして帳票DXに興味がある企業も多いと思います。帳票DXという言葉は聞いたことあるけれど「帳票DXとは具体的に何か」「実際にどのような取り組みをおこなうのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
帳票DXとは何かを知り、取り組むことは、DX推進の第一歩になります。
本記事では、帳票DXとは何かについて詳しく解説します。メリット・デメリットや具体的な方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
帳票DXには、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」がおすすめです。紙の現場帳票業務をすべてペーパーレス化し、業務の効率化やコスト削減などを実現します。
また弊社サンソウシステムズでは、i-Reporterの導入支援をおこなう『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設置しています。
帳票DXでツールを導入する際、「ツールを比較している時間が確保できない」「導入後に運用を継続できるか不安」といった悩みがつきものです。
そのような悩みを解消できるよう、コンサルティング実績の豊富な弊社がヒアリングから目標設定、本導入・運用まで伴走サポートします。
まずは現状の課題を整理するだけでもメリットになりますので、話を伺いたい方は無料の『ちょこっと相談室』(Zoom:オンライン)で、お気軽にご相談ください。
導入実績4,000社以上
目次
帳票DXとは

帳票DXとは、現場帳票を電子化する取り組みです。帳票の作成から管理までを電子化し、企業のDXを実現させます。
これまで紙でおこなっていた現場帳票の運用を電子化することで、印刷コストやファイリングの保管スペースなどを削減することが可能です。
昨今では、環境問題へ取り組む企業が増加しています。また求職者の中でも、企業選びの基準として、環境問題への取り組みを含める傾向が強くなっています。
ペーパーレス化である帳票DXは、社会問題に対して積極的に取り組む企業として、イメージアップにもつながる要素の一つなのです。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデル、企業文化などを根本から変革して自社の競争優位性を高める取り組みです。AIやIoT、ビッグデータを活用して、業務の効率化や新たなビジネスチャンスの創出、レガシーシステムからの脱却を実現します。
例えば、AIを活用したスマート家電やモバイルオーダー、クラウド会計サービスなど、幅広い業界でDXが進んでいます。
ITツールを導入して、業務の効率化を図るIT化とは異なり、DXは製品やサービス、ビジネスモデル自体を変革させるため、IT化はDXを実現するための一つの手段です。
変化の激しい現代社会において、DXは企業にとって必要不可欠な経営戦略と言えます。
帳票DXが推進される背景

帳票DXは現代社会における課題や環境変化など、さまざまな理由で推進されています。
情報管理の属人化
現在の日本の情報管理は、「レガシーシステム」という古い基幹システムを使用しており、ブラックボックス化しています。レガシーシステムはデータの統合や分析、最新技術との連携が難しく、DX推進に必要不可欠なデータの活用が困難です。
レガシーシステムを支えている人材の多くは、2025年に定年退職を迎えます。そのため、担い手がいなくなる前にシステムの刷新が課題となっています。刷新が間に合わない場合、事業機会を失い、国際競争に乗り遅れる可能性があります。
また、2025年以降、年間で最大12兆円の損失が生じる可能性が示唆されていることから、帳票を含むDXが推進されているのです。
参考:「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開|経済産業省」
ペーパーレス化への適応
生活行動や働き方の変化によってテレワークが急速に普及しています。テレワークでは、紙書類でのやり取りが困難なことから、ペーパーレス化も急がれるようになりました。
デジタル化の一つの手段であるペーパーレス化は、DX推進の第一歩です。紙書類による運用はスピード感のある意思決定の妨げになる場合があるため、帳票作成・管理においてもDXを進めることは必要不可欠と言えます。
帳票DXのメリット
帳票DXには多くのメリットがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
業務を効率化できる
帳票管理を電子化すると、帳票の作成・申請から承認作業までのフローをすべてネットワーク上で完結できます。あらかじめ決められたフォーマットに沿って進めるだけで簡単に作成・申請できるため、業務効率を高められます。
帳票の修正や検索もネットワーク上でおこなえることから、取引先からの問い合わせにも速やかに対応可能です。
また紙による運用とは異なり、担当者に帳票を直接届ける必要がないため、作成から承認までを短期間で進めることが可能です。
スマートフォンやタブレットでも操作でき、外出中でも帳票を作成・管理できます。アナログな帳票作成・管理は面倒だと思われがちです。電子化して効率化できれば、重要な業務にリソースを集中させることができ、会社全体の生産性を高められます。
コストを削減できる
帳票を電子化できれば、用紙や印刷コストなどを削減できます。郵送料金やファイリング、印刷に必要な人員も必要ないため、多くのコストを削減可能です。
また、保管場所の確保も必要がなくなり、棚やキャビネット、かごなども用意しなくて良いことから、多くの帳票を扱う企業であれば大幅にコストカットできます。
これまで保管スペースとして使っていた場所をワークスペースとして拡張するなど、別の目的で活用すれば、売上アップや新たなビジネスチャンス獲得にもつなげられます。
セキュリティの強化
帳票の課題として挙げられるのがセキュリティ面です。保管場所やキャビネットに鍵をかけるなどの対策は可能ですが、デスクの上に書類を置き忘れた場合など、取引先や顧客の情報が外部に漏洩する可能性があります。
情報が漏洩した場合、発覚までに時間かかる場合もあるため、より被害が大きくなることも少なくありません。
帳票を電子化できれば、アクセス制限や閲覧制限、ログ監視などによって情報漏洩のリスクを軽減できます。デスクの上に置き忘れることもなくなることから、セキュリティの強化が可能です。
データの活用
帳票の電子化は、履歴の閲覧や検索も容易にできます。そのため、これまでの履歴データを活用してリアルタイムな経営分析が可能です。
例えば、売上分析や在庫・仕入れ分析、キャッシュフロー管理などを細かく分析できます。顧客や取引先ごとの売上傾向や全体の動向なども分析でき、改善点の把握や今後の需要予測などに役立ちます。
外部だけでなく、従業員の残業や有給消化などの勤務状況も把握できることから、就業環境の改善にも有効です。
帳票履歴はただ残すだけでなく、今後の会社経営をより良くするための判断材料になります。
帳票DXのデメリット
帳票DXには多くのメリットがある反面、デメリットも存在します。帳票DXにおけるデメリットも把握し、導入の不要・不必要を見極めましょう。
導入コストや負担がかかる
帳票DXをおこなう場合、ツールやシステムの導入費用、クラウドサービスの利用料金が発生します。紙の帳票をデータとして残す場合は、読み取るためのスキャナーやデバイスの購入も必要です。
帳票の電子システムやサービスの中には、多くの機能を搭載しているものもありますが、機能が多いほどかかるコストも増えます。
もちろんコストだけでなく、導入や運用の整備をおこなう人員も必要です。導入後の運用改善や従業員の教育も必要であるため、運用が安定し定着するまで、ある程度の時間と労力が必要です。
ただし、帳票DXで削減できるコストや業務負担など総合的に判断すると、コストメリットが大きいと言えます。
取引先に理解と承認が必要
帳票DXを推進する場合、取引先や顧客にも請求書や領収書を電子発行することへの理解と承認が必要です。なかには、さまざまな理由によって紙書類でしか受け取ってもらえないケースも少なくありません。
その場合、取引先や顧客によって電子発行と紙発行を選択できるシステムの利用がおすすめです。帳票DXを進める前に、電子発行への対応可否について事前に確認しておきましょう。
帳票DXの具体的な方法
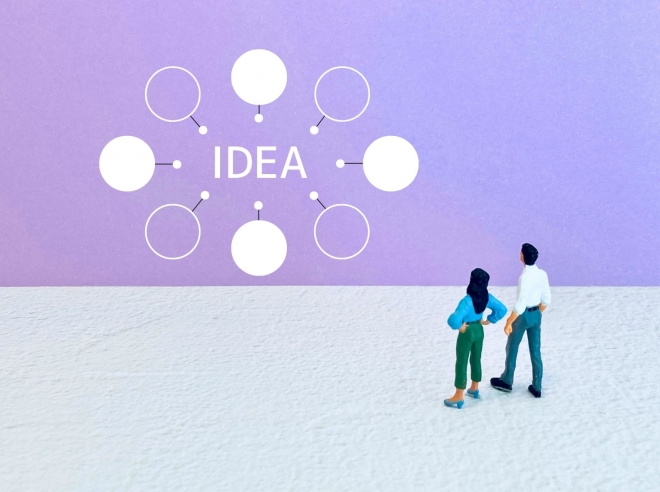
帳票DXには、さまざまな方法があります。自社にとって最適な方法を見つけるためにも、事前に把握しておきましょう。
Excelの活用
Excelで手軽に電子帳票の作成が可能です。帳票に記入する項目のレイアウトを作成すれば、簡単に帳票を電子化できます。
レイアウトを固定化すれば、VBAやマクロを活用して帳票入力の自動化も可能です。
ただし、各項目を一つずつ手入力する必要があるため、手間がかかるだけでなくミスも起こりやすいデメリットもあります。帳票の要件に変更があれば、その都度レイアウトの作り直しも必要です。
また、Excelで処理できるデータ容量には限りがあるため、容量が大きすぎる場合は、画面がフリーズするなど不具合が生じることも少なくありません。
加えて、帳票データをPDF形式に出力して保存する場合、電子帳簿保存法に沿って保管する必要があります。
Excelを活用して帳票を電子化する際は、運用体制の構築と運用ルールの徹底が必要不可欠です。
電子帳票作成ツールの利用
帳票DXには、電子帳票を作成できるツールの活用がおすすめです。帳票の設計や作成、承認までをツール上で完結できます。
帳票のレイアウトを自由に設計できるため、それぞれの会社に最適な形式で作成可能です。外部サービスやシステムと連携が可能であれば、帳票に必要な項目が自動で反映され、帳票における運用をよりスムーズに進められます。
ツールの導入にはコストと労力が必要なため、自社の予算に応じて最適なツールを選択しましょう。
帳票DXにおすすめのツール
帳票を電子化できるツールにはさまざまなものがあります。なかでも、はじめての帳票DXにおすすめのツールを紹介します。
i-Reporter

株式会社シムトップスが提供する「i-Reporter」は、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)の現場帳票システムです。操作性の高さとデータ活用のしやすさが特徴で、業務におけるさまざまな課題を解決できます。
例えばデータ入力をする際、数値選択やカメラ、バーコード読み取りなど、記録したいデータに応じて入力方法が用意されているので、ITが不慣れな現場従業員でも直感的に利用可能です。データの入力方法が豊富であれば、現場の状況をリアルタイムで正しく把握できます。
また、登録されたデータは、週次・月次で一括出力でき、写真データの自動リネームや帳票データの自動仕分けも可能です。外部システムと連携すれば、自動でグラフ作成やデータ登録が可能になるため、帳票記入後のデータ管理工数を大きく削減できます。
帳票DX

株式会社オプロが提供する「帳票DX」は自社に合わせた帳票を作成できる自由度の高い電子帳票サービスです。PDFファイルはもちろん、Officeファイルで作成した帳票を電子化できます。
電子化した帳票のデータは、電子契約サービスや配信サービスなどにつなげ、後続プロセスの自動化が可能です。取引先や顧客に応じて送付方法を電子や紙、Web配信などから選択できます。
また、雛形として用意されている帳票テンプレートを、自社に最適な内容に設計できるデザインツールも利用可能です。緊急度の高い現場からの要望に対しても迅速に対応できます。
さまざまな仕様の帳票を使用している企業におすすめのツールです。
ジョブカン見積/請求書

株式会社DONUTSが提供する「ジョブカン見積/請求書」は、見積書や請求書、納品書などを電子化できるペーパーレスツールです。豊富なテンプレートと操作性の高さが特徴で、簡単に帳票を作成できます。
データ管理では画面が見やすく、ステータス管理で今の状況を一目で判断可能です。古いデータも検索機能で迅速に閲覧できます。
また、会計ソフトと自動で連動しているため、入力時間の削減やタイムリーな経営状況の判断が可能です。
30日間無料お試しも用意しているので、初めて帳票作成ツールの導入を検討している企業におすすめです。
楽楽明細

株式会社ラクスが提供する「楽楽明細」は、豊富な機能が特徴の電子帳票ツールです。自社で使用している帳票を再現する機能や取引先に送った帳票の開封状況がわかる機能、入金管理機能など、帳票管理に特化した便利な機能を備えています。
現在使用しているフォーマットをそのまま利用できれば、迷わず記入できるため、導入直後でもスムーズに利用可能です。
また、自社で基幹システムや販売管理システムを利用している場合は、API連携オプションで自動データ連携できます。顧客データや帳票データを一括で取り込むことで、導入してから運用開始まで、短期間で済ませられます。
帳票DXを実現して業務フローを大きく削減しよう
帳票DXとは、帳票作成から承認、管理までを電子化することであり、今後の競争社会を乗り越える上で必要不可欠な取り組みです。業務の効率化やコスト削減で現場の負担を軽減するだけでなく、データを活用して経営の判断力も高められます。
人手不足や業務の属人化、ヒューマンエラーなど、帳票業務において課題を抱いている企業は、ぜひ積極的な帳票DXに取り組みましょう。
効果的に帳票DXに取り組みたい場合は、電子帳票ツールの導入がおすすめです。なかでも「i-Reporter」は導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)、国内トップシェアを誇る現場帳票システムです。
紙の現場帳票の作成や記入、管理などをペーパーレス化し、さまざまな業務を効率化できます。
また弊社サンソウシステムズでは、i-Reporterの要件定義から設計・導入まで伴走支援をおこなっています。管理運用までサポートしますので、ぜひ一緒に現場の課題解決に取り組みましょう。
まず、やるべきことを整理するだけでもメリットになりますので、無料の『ちょこっと相談室』(オンライン)まで、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。