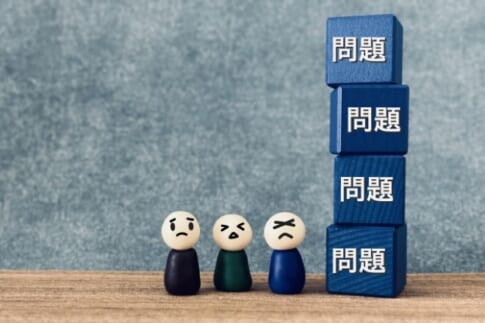製造業において生産性向上とコスト削減のため、効率的な物流管理をおこなうことが欠かせません。効率的な物流管理をおこなうためには、物流KPIを導入し目標を達成させるための道筋を明確にする必要があります。
この記事では、物流KPIの概要や指標一覧、導入の進め方を解説します。導入事例やITツールを活用するメリットも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
「i-Reporter」は導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)、国内トップシェアを誇る現場帳票システムです。
導入することで、紙の現場帳票の「記入・報告・管理」すべてのペーパーレス化を実現。さまざまな業務の効率化やDXにつなげられます。
また、弊社株式会社サンソウシステムズでは、要件定義から設計・導入、その後の運用管理まで、お客様に寄り添った伴走支援が可能です。
ぜひ、ご一緒に現場の業務課題を整理していきましょう。サービス資料を用意しましたので、併せてこの機会にこちらから無料でダウンロードしてみてください。
導入実績4,000社以上
目次
物流KPIとは

物流KPIとは、物流業務の業績を評価・計測するための指標です。KPIは「Key Performance Indicators」の頭文字をとったもので、日本語にすると重要業績評価指標です。物流KPIは、数値で測定できる定量的な指標を定めるため、品質や効率を客観的に評価・計測できます。
物流KPIを設定すると、データに基づいた目標を決められるため、改善点や解決するための戦略が明確になる点がメリットです。まだ物流KPIを設定していない場合には、ぜひこの記事を参考に自社の目標を設定してみましょう。
物流KPIの指標一覧

物流KPIの指標は、設定する目的に合わせて以下の3つのカテゴリに分けられます。
- コスト・生産性
- 品質・サービスレベル
- 物流条件・配送条件
ここからは、それぞれのカテゴリ別に物流KPI指標の一覧を紹介します。
コスト・生産性
コスト・生産性の指標は、削減できるコストや効率化できる業務がないか、人員配置の見直しなどを探す際に役立ちます。人別・ライン別・時間帯別・ルート別など、見直したい場所に絞って利用するのも効果的です。
物流KPIにおけるコスト・生産性指標の一覧は、以下の表の通りです。
| 評価項目 | 計算方法 | 説明 |
|---|---|---|
| 保管効率 | 保管間口数 ÷ 総間口数 | 倉庫や物流センターの保管スペースの効率性を示す指標 |
| 人時生産性 | 処理ケース数 ÷ 投入人時 | ピッキング・仕分け・光峰作業の生産性を測る指標 |
| 数量あたり物流コスト | 物流コスト ÷ 出荷数量 | 総物量コストを数量あたりで管理する指標 |
| 日次収支 | 1日あたりの収益 – 1日あたりのコスト | 1日あたりの収支を示す指標 |
| 実車率 | 実車距離 ÷ 走行距離 | 無駄な空車走行を減らすために稼働状況を計測する指標 |
| 実働率 | 実働日数 ÷ 営業日数 | 車両の稼働していない時間を減らすために稼働状況を計測する指標 |
| 積載率 | 積載数量 ÷ 積載可能数量 | 車両の積載効率を改善するための指標 |
品質・サービスレベル
品質・サービスレベルの指標は、製品の品質を維持・向上したい場合やリスク管理、顧客満足度を上げるために使われます。
物流KPIにおける品質・サービスレベルの一覧は、以下の表の通りです。
| 評価項目 | 計算方法 | 説明 |
|---|---|---|
| 棚卸差異率 | 棚卸差異 / 棚卸資産数量 | 棚卸資産の実際の数量と帳簿上の数量の差異を示す指標 |
| 誤出荷率 | 誤出荷発生件数 / 出荷指示数 | 出荷指示に対して品・数量・出荷先違いなど誤って出荷された件数の割合を示す指標 |
| 遅延・時間指定違反率 | 遅延・時間指定違反発生件数 / 出荷指示数 | 出荷指示に対して遅延や時間指定違反が発生した件数の割合を示す指標 |
| 汚破損率 | 汚破損発生件数 / 出荷指示数 | 商品が汚れたり破損したりした件数の割合を示す指標 |
| クレーム発生率 | クレーム発生件数 / 出荷指示数 | 誤出荷・書類ミス・作業者などへの顧客からのクレームが発生した件数の割合を示す指標 |
物流条件・配送条件
物流条件・配送条件の指標は、効率的な配送計画を立てたり、コスト管理を最適化したりするのに活用されます。顧客別や納品先別で測定する場合もあります。
物流KPIにおける物流条件・配送条件の一覧は、以下の表の通りです。
| 評価項目 | 計算方法 | 説明 |
|---|---|---|
| 出荷ロット | 出荷数量(数量や重量) | 顧客別・納品先別の出荷ロットサイズを示す指標 |
| 出荷指示遅延件数 | 出荷指示の遅延件数 | 出荷指示の遅延発生件数を示す指標 |
| 配送頻度 | 配送回数 / 営業日数 | 配送先別の配送頻度を示す指標 |
| 納品先待機時間 | 納品先での待機時間の平均 | 納品先での待機時間を示す指標 |
| 納品付帯作業時間 | 納品先での付帯作業時間の平均 | 納品先での契約外の荷役・開梱・検品など付帯作業時間を示す指標 |
| 納品付帯作業実施率 | 納品付帯作業実施回数 / 納品回数 | 契約外の付帯作業を実施した割合を示す指標 |
物流KPI導入の進め方

物流KPIを導入すると目標が明確となり、効率化や品質向上、利益の増加などさまざまなメリットがあります。しかし、物流KPIを導入する場合、どのような手順で進めていけば良いのか悩むケースも多いでしょう。ここからは、物流KPI導入の進め方について解説します。
1. KPI導入をおこなう担当者の選出
物流KPIの導入をおこなう際には、まず担当部署や担当者を決めましょう。物流KPIは、生産や営業など1つの部署だけで完結するものではなく、部署を跨いでの改善が必要な場合があります。すべての部署を俯瞰して課題や見直しができる選任のチームを作るのが理想的です。
選任のチームを作成するのが難しい場合でも、物流KPIを主導する人物や責任の所在を明確にする必要があるため、担当者は決めておくようにしましょう。
2. データを分析し現状を把握する
担当者や部署が決定した後には、物流KPIを設定するためのデータを集めます。物流KPIの指標一覧の中から、利用する可能性のあるデータがどのような方法でどの部署が集められるのか調べましょう。指標によってデータを集めるのが難しい場合には、他の指標への置き換えも検討します。
なお、取得するデータは正確なものでないと意味がないため、注意が必要です。データを集約した後は、まずは現状について把握します。
3. 目標を設定し戦略を立てる
現状を把握した後は、集めたデータに基づき、目標を設定し達成のための戦略を立てます。現状を把握すると、会社として改善しなければならない課題が特定できます。特定した課題に対し目標を設定する際には、SMARTの法則に乗っ取って設定するのがおすすめです。
SMARTの法則とは、Specific(具体的)・Measurable(測定可能)・Achievable(達成可能)・Relevant(関連性)・Time-bound(期限付き)の頭文字を取った方法です。数値で確認でき現実的な目標を設定できるため、達成できる可能性が上がります。
目標が決定した後は、達成させるために必要な戦略を練ります。例えば、製品の破損率を減らす場合には、わかりやすいマニュアルの整備や社員教育などが考えられるでしょう。戦略を考える際には、必要な時間や資金、人的リソースも考慮する必要があります。
4. 運用ルールを設定し社内周知する
目標や戦略が決定した後には、運用ルールを設定しましょう。運用ルールとは目標達成に向けた具体的な行動のことで、指標に基づいたデータを計測する頻度、報告のフロー、表彰制度、戦略を見直しするタイミングの整備が挙げられます。
運用ルールが定まったら、全社員が把握できるような社内周知も重要です。
5. 定期的に見直し改善する
実際に運用を開始したら終了ではなく、定期的に見直しや改善をおこなう必要があります。なぜなら、実際に開始してみて初めて気が付いたり発生したりする問題点があるからです。問題点があったから失敗ではなく、改善を積み重ね、より良い仕組みを作っていくことが大切です。
物流KPIの運用にITツールを活用するメリット

物流KPIを導入・運用していく際には、ITツールを使用すると効率的にデータを収集・分析できます。ここからは、物流KPIの運用にITツールを活用するメリットを紹介します。
リアルタイムでデータの収集ができる
物流KPIの運用にITツールを使用すると、リアルタイムでデータ収集できる点がメリットです。ITツールによっては、機械やセンサーから直接情報を受け取りデータ反映できるものもあります。人によって入力されたデータも即時反映されるため、最新の情報を全員と共有できます。
データ分析が簡単
データ分析が簡単な点も、ITツールを使用するメリットです。自動で計算できるのはもちろん、グラフに変換して視覚的にわかりやすくまとめられます。ITツールに計算を任せることで、ミスが減らせるのもメリットです。
データ連例でリポート作成にも役立つ
ITツールを使用すれば、複数のデータを統合させてリポートの作成もできます。複数の拠点がある場合にも、それぞれのデータを集約し一元管理できるため、各拠点を比較したい際にも便利です。グラフやダッシュボード機能を使うと、視覚的にわかりやすいリポートの作成にも役立ちます。
物流KPIの活用事例

物流KPIを導入し成功させるためには、他の会社で活用した事例から学ぶのが一番です。ここからは、コストや生産性を改善させた事例を紹介しますので、自社で活用できるか検討してください。
生産性を1.3倍改善した事例
物流センターの受託運営をおこなう会社の事例を紹介します。
- 課題 : 倉庫内の業務で発生する作業員の人件費を改善したい
自社で開発した生産性分析ソフトを活用し、各作業別の生産性を計測しました。計測した結果の中で、改善余地時間の算出に着目しデータや現場から聞き取り結果より、曜日により業務量に差が出ることが明らかになりました。
戦略として、必要人員の割り出しと作業進捗管理の徹底、多能工化の取り組みをし、改善余地時間の15%削減と生産性を1.3倍に改善できた事例です。
在庫の適正化に取り組み企業体質の強化をした事例
続いて、グループ全体での商品ロスや廃棄ロスに課題感を持つ会社の事例を紹介します。
- 課題 : 商品ロスや廃棄ロスが発生している/組織の構造改革が必要
「さまざまなロスを省くことは、顧客と従業員両方にメリットがある」という考えから、在庫の適正化にこだわった目標を設定しました。具体的には、販売・運送・製造・開発など在庫にかかわるすべての部門を対象とし、各部署の役員が責任もって対応できる仕組みを作り出し、全社的な目標達成に向けた意識統一を図っています。
参考:ロジスティクスKPI活用の手引き|公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
物流コストの見直しをおこなった事例
最後に紹介するのは、当初の見立てより物流コストが大幅に予算を超えてしまうため、コスト抑制のために物流KPIを活用した事例です。
- 課題 : 緊急出荷が多く取引ルールが守られていない/積載率が低い/デポ間の調整移動が多い
課題に対して、指標の数値を年度ごとに見える化し、取り組んだ部門の成果が一目でわかるように工夫しています。
運賃のコストを計る指標は、以下の2つを用いました。
- 配送数量/運賃
- デポ補充数量/運賃の指標
保管料のコストを計る指標としては、以下の2つです。
- 保管数量/保管料
- 荷役数量/荷役料
物流KPIの運用には現場帳票システム「i-Reporter」が便利

物流KPIを運用していく上では、ITツールを使ったDXが欠かせません。現場帳票システムの「i-Reporter」であれば、iPad・iPhone・Windowsに対応しており、入力作業もスムーズです。さまざまなIoT機器から情報を取得したり、各種分析ツールへ連携したりできるため、リポートの作成にも役立ちます。
株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
物流KPIの導入を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか」といった課題や不安がつきものです。
そのような会社様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。
まず、やるべきことを整理するだけでもメリットになります。お話を伺いたい方は、無料の『ちょこっと相談室』(Teams:オンライン)で、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。
運送・物流業界の情報をさらに知りたい方は、ぜひこちらのメディアもご覧ください。
運送・物流業界向けの情報を発信しているオンラインマガジン|トラッカーズマガジン