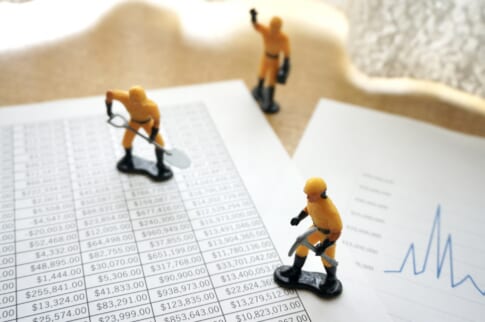作業指示書とは、業務ごとに作業内容や注意点をまとめた書類です。わかりやすく内容がまとまった作業指示書ができれば、業務を円滑かつ安全に進められます。
今回の記事では、作業指示書の作り方や役立つツール、無料で使えるテンプレートを紹介します。業務品質を向上したい方や作業指示書の作成にお悩みの方はぜひ参考にしてください。
『i-Reporter』は導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)、国内トップシェアを誇る現場帳票システムです。導入することで、作業指示書など現場帳票の「記入・報告・管理」すべてのペーパーレス化を実現し、さまざまな業務の効率化やDX促進につなげられます。
また、弊社株式会社サンソウシステムズでは、要件定義から設計・導入、その後の運用管理まで、お客様に寄り添った伴走支援が可能です。
ぜひ、ご一緒に現場の業務課題を整理していきましょう。サービス資料を用意しましたので、併せてこの機会にこちらから無料でダウンロードしてみてください。
導入実績4,000社以上
目次
作業指示書とは

作業指示書とは、業務を正確かつ円滑に進めるために、作業内容や手順、実施日時、担当者などを明記した書類のことです。現場作業や製造工程、サービス業務、建設、IT業界など、幅広い分野で活用されています。
作業指示書は、作業手順書や業務マニュアルと混同されやすいですが、役割は異なります。作業手順書は、ある作業をどのように実施するかの流れを示す文書であるのに対し、作業指示書はいつ・誰が・何を・どうやっておこなうかを具体的に指示する書類です。
例えば、作業指示書に安全に作業するための注意点やミスが多いカ所
を記載しておくことで、業務のミスが減り生産性の向上も期待できます。
作業指示書が必要とされる理由

作業指示書は単なる作業のメモやToDoリストではありません。業務の効率化、安全性の確保、品質の維持、そしてチーム全体のパフォーマンス向上に直結する、いわば“業務遂行の設計図”です。ここでは、なぜ作業指示書がさまざまな業界・業種で必要とされるのか、その理由を詳しく解説します。
情報伝達の正確性
作業指示書の最も基本的な役割は、業務に必要な情報を正確に伝達することです。
例えば口頭での指示やチャットのやり取りだけでは、言った・言わないのトラブルがつきものです。時間が経つと記憶が曖昧になり、重要な指示内容が抜け落ちるミスを発生させます。こうした伝達ミスは、作業の遅延や品質不良の原因となるだけでなく、信頼関係の損失にも影響がでます。
作業指示書にあらかじめ必要事項を記載しておけば、作業者はいつでも確認でき、共通の理解に基づいて作業の進行が可能です。特に、製造業や建設業、物流業など現場ベースで多人数が関わる業務においては、情報の正確な伝達が業務の成否を左右します。
また、作業指示書は証拠書類としての役割も果たします。万が一問題が発生した場合でも、誰が・いつ・どのような指示を出したかを記録として残しておくことで、原因の究明や責任の明確化が可能です。
作業ミスや事故の防止
作業ミスの多くは、うっかりミスや思い違いによるものです。特に、複数の工程を含む業務や、専門的な知識や技術を要する作業では、些細な認識違いが大きなミスにつながります。
作業指示書には、作業の手順や留意点、使用する機器や資材などを明確かつ具体的に記載することで、作業者の判断に頼らずに安全で正確な作業を実現できます。
さらに、工場や建設現場などでは、誤操作や確認漏れが大事故につながる可能性もあります。例えば、電源を切らずに整備作業をすることや、指定の安全装備を着用しないなど確認を怠れば、重大な労災事故を引き起こす恐れもあります。
作業指示書があれば、これらのリスクをあらかじめ明記でき、作業者への安全教育の一部としても活用が可能です。現場に掲示し、点呼時に確認することで、日常的な安全意識の定着にもつながります。
業務の標準化
企業が一定の品質を維持し、業務効率を高めていくには誰がやっても同じ成果が出せる状態、すなわち業務の標準化が不可欠です。
しかし、実際には熟練者の暗黙知に頼って業務が行われているケースも多く、「○○さんがいないと回らない」といった属人化の問題が起きやすくなります。これは、社員の異動・退職・休職などがあった際に業務の品質が大きく低下するリスクがあります。
作業指示書にノウハウを落とし込み、明文化しておくことで、業務の標準化と可視化が可能です。これにより、新人や異動者でも同じ作業を再現できるようになり、OJTやマニュアルの補完にもなります。
特に生産工程や点検業務などの反復作業では、作業指示書があることで業務のムダやムラが可視化され、業務改善の土台にもなります。
チーム間の連携強化
現代の業務は、一人の担当者だけで完結することが少なく、製造から検査、出荷、納品、フォローアップまで、複数の部署やスタッフが連携して初めてひとつの業務が完了します。
このような場面では、作業指示書が共通の理解を生み出すためのツールとして機能します。例えば、前工程の作業内容や注意事項が記載された指示書があるだけで、後工程の担当者は状況を把握しやすくなり、スムーズな引き継ぎも可能です。
また、管理職やマネージャーが進捗を確認し、品質のチェックポイントを把握する際にも、作業指示書の情報が役立ちます。結果として、業務全体の可視化が進み、ボトルネックの発見やリスクの事前対処が可能になります。
特に、DXによる業務の見える化が求められる中で、作業指示書はその起点となるドキュメントです。
作業指示書の種類と活用例
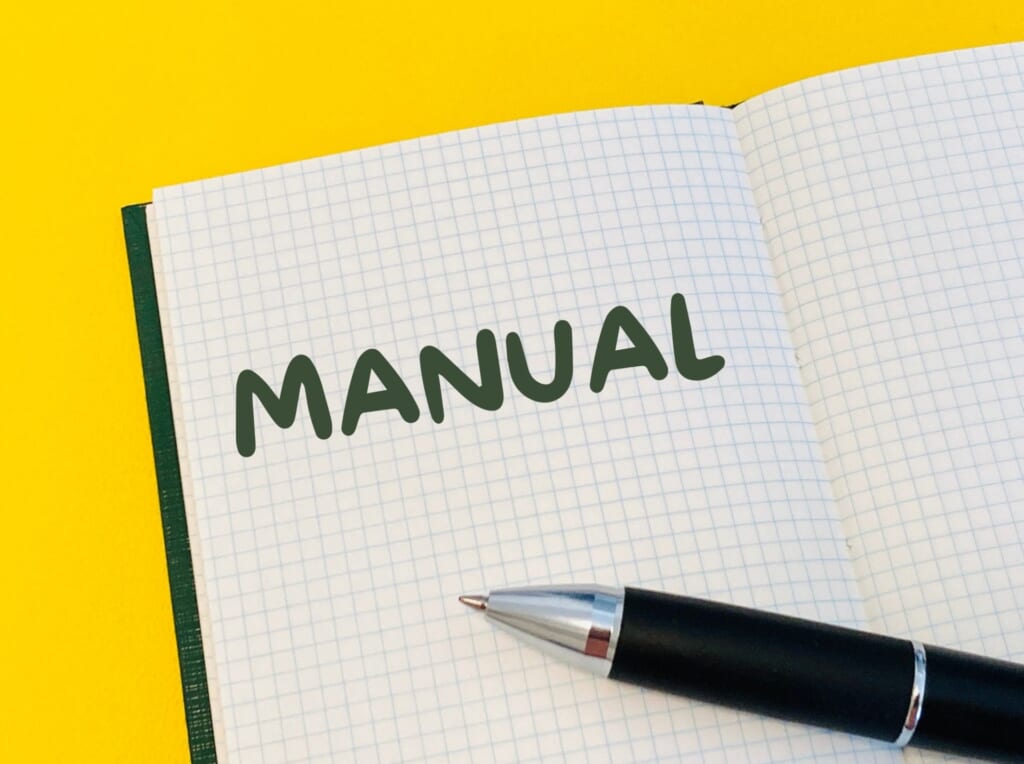
作業指示書は、あらゆる業種・業界において作業の可視化とミスの防止を実現する重要なツールです。しかし、業務の内容や現場の特性に応じて、その形式や活用方法は大きく異なります。ここでは、代表的な4つの業種を取り上げ、それぞれにおける作業指示書の具体的な活用例を紹介します。
製造業:工場の組立・検査作業における活用
製造業では、製品の組立・加工・検査・出荷といったプロセスにおいて作業指示書が不可欠です。作業内容が標準化されておらず、熟練工の経験に依存している場合、品質のバラつきや納期遅れといったリスクが高まります。
例えば、ある部品の組立作業において、「どの順番で部品を取り付けるか」「どの工具を使うか」「トルク値はいくつか」といった詳細な情報を作業指示書に落とし込むことで、誰が作業しても一定品質が保てるようになります。また、不具合が出た場合でも、どの工程でどんな作業が行われたかを振り返ることができるため、トレーサビリティの確保も可能です。
近年では、製造業においてもIoTとの連携が進んでおり、作業指示書と生産設備のセンサー情報を連動させることで、リアルタイムな作業進捗の把握や異常検知もできるようになります。
建設業:現場作業の指示管理
建設現場では、多くの職人や協力会社が関わるため、作業の段取りと役割分担を明確にすることが極めて重要です。
例えば、鉄筋工事の工程においては作業指示書に「使用する資材の種類」「配筋のピッチ」「作業場所のエリア指定」「必要な安全装備」など、具体的な指示を日別または工程別に記載します。これにより、現場監督や作業者は混乱なく業務を進めることができ、安全対策の徹底にもつながります。さらに、建設現場では天候や搬入スケジュールによって計画が変動しやすいため、作業指示書の更新性・柔軟性が鍵です。クラウド型ツールと連携することで、スマートフォンやタブレットからリアルタイムに内容を共有・修正できるようになり、現場の混乱を最小限に抑えるといった工夫が可能です。
サービス業・IT業:現場対応、保守点検作業
サービス業やIT業における作業指示書は、顧客先での訪問作業・メンテナンス・トラブル対応など、フィールド業務で活用されています。
例えば、空調設備の保守を行うサービスマンの場合、「訪問先の情報」「実施する点検内容」「使用する部品」「作業後のチェック項目」などを記載した作業指示書を持参することで、現場対応がスムーズになります。作業完了後は、作業記録をそのまま報告書として提出できる仕組みもおすすめです。
IT業界においても、オンサイト保守やネットワーク機器の設定業務などで作業指示書が用いられます。作業環境に応じてアクセス権の設定手順やIPアドレスの割り振りなどを明記し、人的ミスの防止とセキュリティ維持を図るのが狙いです。
DXツールとの組み合わせによる活用例
近年では、紙やExcelによる従来型の作業指示書に加え、IoTやクラウドシステムと連携したスマート作業指示書の導入が進んでいます。
例えば倉庫業務においては、出荷作業の作業指示書をスマートフォンやハンディ端末で確認しながら、ピッキングを進める仕組みが一般的になりつつあります。IoTタグやQRコードを読み取ることで、在庫の位置や数量が即座に表示され、作業の効率化と在庫精度の向上を同時に実現可能です。
また、製造現場では作業指示書と機械設備のセンサー情報を連携させ、作業中に異常が発生した場合はアラートを出す仕組みも実装されています。これにより、単なる指示文書だった作業指示書が、リアルタイムで業務全体を最適化するための基盤へと進化しています。
作業指示書の必要項目と作り方
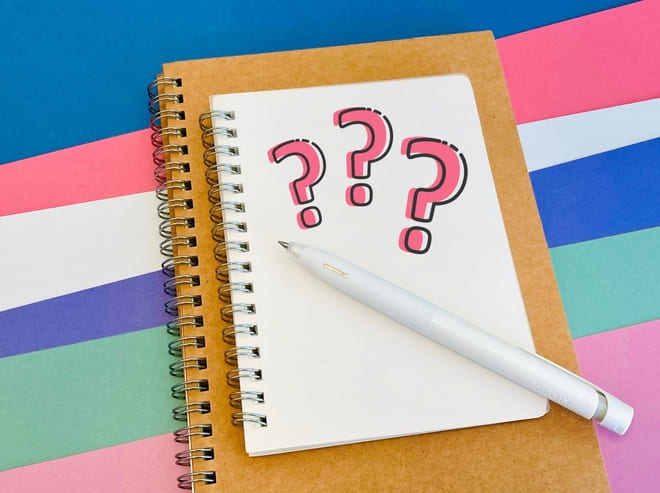
作業指示書を作成する際には、抜けや漏れがないようにしつつ、わかりやすい指示をおこなう必要があります。5W1Hを意識していつ・だれが・どこで・何を・なぜ・どのようにおこなうのか明確にするよう意識しましょう。ここからは、作業指示書に記載したい項目と作り方について解説します。
タイトル
タイトルには、製品名や作業名など、どの業務で使用する作業指示書であるかが明確になるように記載します。場合によっては型番や製造ロット番号を記載しておくと、作業指示書の取り間違えを防げます。
作成日と管理番号
いつ作成した書類かわかるように作成日も記載しておきましょう。また、作業指示書を管理するための管理番号を作成すると、必要な作業指示書をすぐ探せます。発注元単位で作業指示書を管理したい場合には、発注元も記載すると探しやすくなります。
責任者と作業者
誰が作成し誰に指示を出したかを把握するため、作業指示書の責任者と作業をおこなう人(宛先)、 作成者の名前も入れます。作業指示書の内容で不明点が出た際にすぐ確認できるよう、電話番号やメールアドレスも記載しておくと便利です。
期間や納期、作業日時
作業指示書には、業務が継続する期間や納期も記載しておくと、いつまでに何をおこなうのか明確にできます。また、実際に作業した日付や時間も記録しておきましょう。作業時間を記録しておくと、どのくらいの時間で作業ができるのか判断する基準や業務改善に活用できます。
指示内容
指示内容には、作業工程や作業内容、必要な工具などを時系列に沿って記載します。作業担当者が指示書を見てすぐに作業できるように、必要な項目はすべて記載しておくことが重要です。また、作業する上で危険なカ所やミスが起きやすいカ所を注意喚起しておくと、安全で正確な作業ができます。
必要に応じて、写真や図面を載せると、見やすくなりスムーズに業務が進められます。他にも、完了報告などに使用するQRコードやバーコードを載せるケースもあります。
作業指示書を作成する際のポイント

作業指示書は、実際に作業をする従業員が見てわかりやすい内容にする必要があります。ここからは、作業指示書を作る際に気を付けたいポイントについて解説しますので、作成の際の参考にしてください。
作業内容に合ったレイアウトを選択する
作業指示書を作成する際には、作業内容にあったレイアウトの選択が重要です。使用しない項目が多く、レイアウトが煩雑で見づらいと、使いにくいだけではなく重要な項目を見落としてしまう恐れがあります。
自社でオリジナルの作業指示書を作成する際には、どのような内容が必要か項目や承認プロセスを精査しましょう。配布されているテンプレートを活用する場合にも、自社で必要な機能が備わっているのかよく確認してから採用するのが大切です。
抜け・漏れのないように記載する
作業指示書に記載する内容は、時系列に沿って抜けや漏れがないように記載しましょう。抜けや漏れがあると、業務上のミスにつながる可能性が高まります。特に製品名や数量、納期などを誤って記載してしまうと、製品が納期までに完成しない恐れがあるため注意が必要です。
作業工程の中に機器や工具を使用する場合には、作業指示書に扱い方も記載しておきましょう。また、作業指示書は一度作成したら完成ではありません。ミスや事故を基に改善し、現場からの効率の良い作業方法を取り入れるなど、日々更新し最新の情報を記載することが重要です。
曖昧な表現や主観的な文章を避ける
作業指示書を作成する際には、曖昧な表現や主観的な文章になっていないか注意しましょう。読み手によって捉える内容が変化すると、不良品の発生や製作の誤製作につながります。
部品や製品であれば型番を、数量や時間などは目安ではなく具体的な数字で記載すると誰が製造しても同じ品質を保てます。危険な作業に対する注意点も、具体的にどの工具の何に気をつけて使用すべきなのか記載するようにしましょう。
誰が見てもわかりやすいよう簡潔にまとめる
作業指示書に記載する文章は、誰が見てもわかりやすいように簡潔にまとめましょう。長すぎる文章は、読み終わるのに時間がかかります。1つの文章に要点を1つだけ盛り込む一文一意を意識して、端的な文章になるように心がけることが大切です。
しかし文章を短くしようとするあまり、専門用語を多用した作業指示書を作成すると、新入社員が理解できなくなります。作業指示書は熟練の職人だけが理解できる内容では意味がありません。作業指示書をよく活用する新入社員が見てもミスなく業務できる内容が理想ですので、専門用語を使い過ぎないように注意しましょう。
写真や図を活用する
作業指示書には、必要に応じて写真や図を取り入れると効果的です。文章だけを目で追うより、写真や図を見ればすぐ理解できる場合もあるためです。写真を載せる際には、作業者の目線で撮影するのがポイントです。
また、写真や図に赤丸や吹き出しを付けて、注目すべき点を明確にするとさらにわかりやすくなります。
ツールを活用した作業指示書の効率化

作業指示書の活用をさらに進化させるために、多くの企業で注目されているのがデジタル化による運用です。紙ベースでの管理には限界があり、リアルタイムな共有や検索性、記録との連動といった点で課題を抱える現場も少なくありません。ここでは、作業指示書をより効率的に活用するためのDX的なアプローチをご紹介します。
i-Reporterで作成&共有の簡略化

現場帳票のデジタル化を支援するi-Reporterは、作業指示書の作成から共有・保管・承認フローまでを一元化できるツールとして、幅広い業界で導入が進んでいます。
i-Reporterで作成された作業指示書は、すべてクラウドベースのデータベースに保管されます。保存された指示書にはラベルを付けて分類することができ、過去の履歴から必要な指示書を検索・並び替えして即座に表示することが可能です。現場ごと、製品ごと、日付ごとなど、組織に合わせた柔軟な管理が実現できます。
これらの機能によって、従来の紙ベース運用で発生していた手間やトラブルが大幅に削減され、業務効率と品質管理の両立が可能です。
弊社、株式会社サンソウシステムズでは、i-Reporterの導入を検討中の企業様に向けて、要件定義から設計、実装、社内展開、その後の運用管理に至るまで、一気通貫での伴走支援を提供しております。初めてのデジタル帳票導入で不安を感じる方にも安心してご相談いただけるよう、無料でご覧いただけるサービス資料をご用意しております。ぜひこの機会にダウンロードしてご活用ください。
導入実績4,000社以上
Excelテンプレートのそのまま活用
多くの現場で使用されているExcel帳票を「そのまま活用できる」という点も、i-Reporterの導入メリットとして大きな魅力です。
i-Reporterは、ExcelやPDF、画像などで作成された既存の帳票をそのまま取り込むことができるため、「現場で慣れ親しんだフォーマットを維持したまま」デジタル化を推進できます。新しいテンプレートに作り替える手間や、現場での再教育などのコストが抑えられ、スムーズな移行と現場定着が可能です。
また、作業指示書に図面ファイル(PDF)や作業工程の写真、説明動画を添付することもできるため、視覚的にわかりやすい帳票が作成できます。これにより、作業の抜け漏れや誤解を防ぎ、特に複雑な工程や危険を伴う作業においては、安全性の向上にもつながります。
「今使っているExcelをそのまま活かしたい」「現場に負担をかけずにDXを進めたい」といった企業には、i-Reporterの柔軟な対応力が大きな武器になるでしょう。
スマートフォンやタブレットでの確認
スマートフォンやタブレット端末を活用することで、作業指示書の閲覧がよりスマートに行えるようになっています。
例えば、作業開始前にアプリを開けば、当日の作業内容や注意点、写真付きの手順をその場で確認できます。わざわざ事務所に戻って資料を探す手間や、作業前に印刷を待つ必要がなくなり、業務のスピードと正確性が大幅に向上します。
また、現場で変更が生じた場合にも、リアルタイムで更新された指示書を即座に共有できるため、情報の齟齬や指示ミスを最小限に抑えることが可能です。端末操作に不慣れな方でも直感的に扱える専用アプリも増えており、業種・職種を問わず導入が進んでいます。
作業記録との紐づけやデジタル署名機能
作業指示書の真価が発揮されるのは、「作業前の指示」だけでなく「作業後の記録・報告」にも対応できる点です。近年では、作業指示と作業実績を一体管理できるシステムの導入が進んでおり、紙のチェックリストとは異なる運用が可能です。
例えば、作業者が現場で作業を終えた後、スマートフォンやタブレット上で「作業完了」のチェックを入れ、必要に応じて写真を添付することで、そのまま報告書として記録される仕組みがあります。さらに、責任者によるデジタル署名によって作業内容を確認・承認すれば、そのまま管理帳票としても活用可能です。
これにより、作業指示書と作業記録がバラバラに存在するのではなく、一連の流れとして一元化されるため、業務の見える化・トレーサビリティの確保・監査対応にも効果を発揮します。特に製造業や保守業務など、報告義務が求められる業種にとっては、大きなメリットです。
作業指示書の無料テンプレート
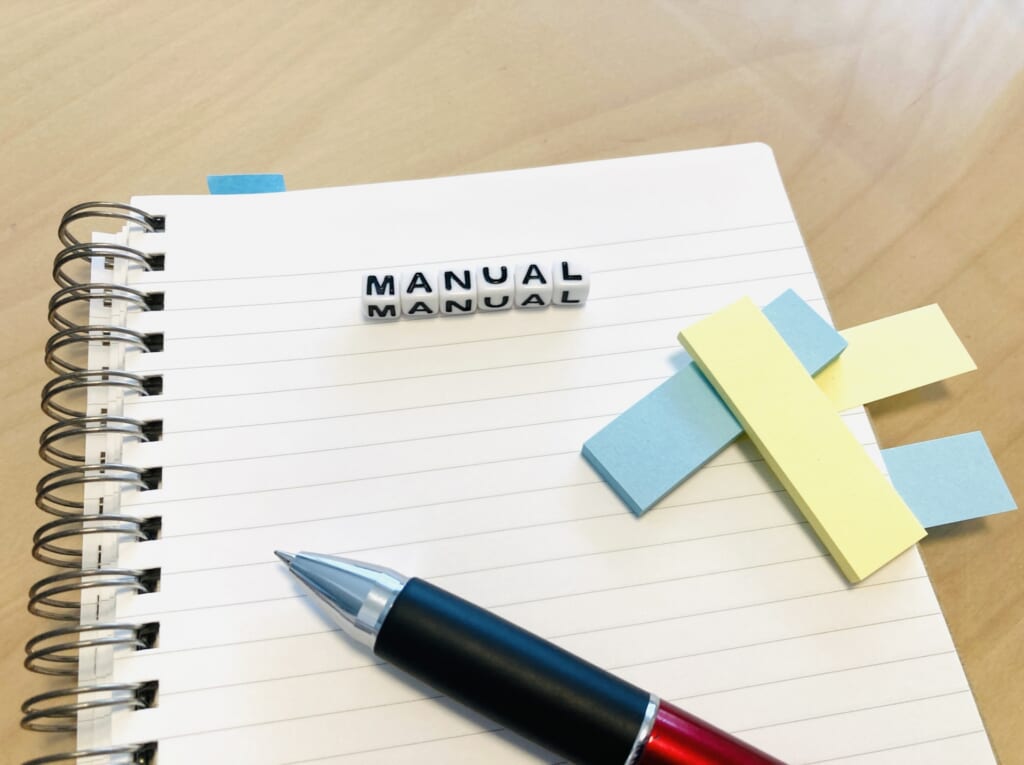
作業指示書を一から設計・作成するには、作業内容の整理、レイアウト設計、記載項目の検討など多くの工数がかかります。特に初めて作成する場合や業務の種類が多岐にわたる場合には、どこから手を付けて良いか迷ってしまうこともあるでしょう。
そんなときに便利なのが、無料でダウンロードできるテンプレートの活用です。作業指示書のベースがあることで、記載すべき項目や構成のイメージをつかみやすくなり、自社に合わせたカスタマイズもスムーズに進められます。
ここでは、実務に役立つ作業指示書テンプレートを提供している代表的な3つのサイトをご紹介します。
smartsheet
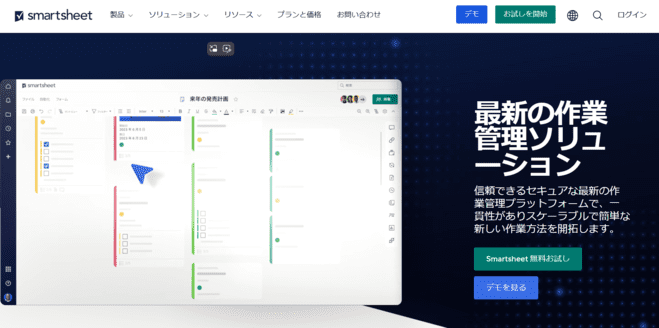
smartsheetは、業務効率化を支援するクラウド型のプロジェクト管理ツールを提供している企業です。プロジェクト管理、スケジュール調整、工程管理など、さまざまなビジネスシーンに対応したテンプレートが豊富に取り揃えられています。
中でも作業指示書テンプレートは、製造業・サービス業・工事業などの業界別に最適化されており、実際の業務現場ですぐに活用できる実用性の高い構成が特徴です。チェックボックス形式や進捗ステータス欄があらかじめ用意されており、複数工程の管理にも適しています。
また、テンプレートはExcel形式でダウンロード可能なため、Microsoft Officeに慣れている方でも編集がしやすく、自社の業務フローに合わせてカスタマイズするのも簡単です。
テンプレラボ

テンプレラボは、ビジネスや日常生活で使える高品質な書類テンプレートを多数提供している人気サイトです。請求書や見積書、勤怠管理表といった帳票類だけでなく、現場で使える作業指示書のテンプレートもシンプルな形式で提供されています。
テンプレラボの作業指示書テンプレートは、シンプルで余計な装飾がなく、記入項目が明確に分かれているため、「まずは一通り作業指示書を作ってみたい」という方にも適しています。ExcelとWord両方に対応しており、印刷して手書きで記入することも可能です。
また、同じフォーマットで「報告書」や「確認書」なども用意されているため、帳票類を一元的に管理したい場合にも便利です。
bizroute

bizrouteは、中小企業や個人事業主向けにビジネステンプレートや業務改善ノウハウを発信しているサイトです。営業報告書、業務フロー表、議事録などのテンプレートに加え、業務指示書・作業指示書のフォーマットも無料公開されています。
bizrouteのテンプレートは、どちらかといえば業務管理や現場運用の経験がある方向けの内容で、担当者・日付・作業内容・完了確認など、実務レベルで必要とされる情報が網羅的に構成されています。そのため、「すでに現場で指示書を運用しているが、もっと管理しやすい形にしたい」といったニーズにぴったりです。
カスタマイズのしやすさもポイントで、用途に応じて行の追加や担当者ごとの色分け、コメント欄の挿入なども容易に行えるため、自社の運用にあわせた最適なフォーマットに仕上げることが可能です。
わかりやすい作業報告書の書き方とは?Excelのテンプレートを紹介! – DXみらい研究所
無料テンプレート活用時の注意点
テンプレートを使う際には、「そのまま使う」のではなく、自社の業種や業務内容に合わせてカスタマイズすることが前提です。特に安全管理や品質チェックが必要な業務では、テンプレートに加えて注意喚起欄やリスク対策の項目を追記するなど、現場で使いやすい工夫が必要になります。
また、テンプレートを選ぶ際は「必要な情報が網羅されているか」「作業者にとって見やすいか」「紙でもデジタルでも運用可能か」といった観点も意識して選ぶようにしましょう。
作業指示書の活用のポイント

作業指示書は、単に「業務の内容を伝える」だけの文書ではありません。うまく活用することで、現場のミスを減らし、教育効率を上げ、業務品質を安定させるなど、企業の生産性や信頼性を大きく向上させる可能性があります。ここでは、作業指示書の具体的な活用ポイントを3つの視点から紹介します。
実際の業務改善効果
作業指示書の導入・活用によって得られる最大の効果が、業務全体の見える化と安定化です。
多くの現場では、作業者による判断のバラつきや、担当者間の認識の違いにより、作業内容や品質に差が出るケースが少なくありません。作業指示書を活用すれば、「何を」「いつまでに」「どのように」行うべきかが明確になり、すべての作業者が共通の基準のもとで業務にあたることが可能になります。
さらに、作業実績を記録として残すことで、後から振り返ることも可能です。トラブルが発生した際の原因追及や、継続的な業務改善においても、作業指示書のデータは非常に有効な情報資産となります。
作業の属人化回避・新人教育にも効果大
もうひとつの大きな効果は、業務の属人化を防ぎ、教育コストを削減できる点です。
属人化が進むと、その社員が休職・退職したときに業務が回らなくなり、会社全体のリスクにもつながりかねません。
作業指示書をしっかりと整備し、ノウハウや判断基準を言語化しておけば、誰が担当しても同等の作業が可能です。これにより、業務の引き継ぎがスムーズに行えるだけでなく、教育資料としても活用できるため、新人社員の立ち上がりが早くなるという利点があります。
特に、現場経験が浅い社員や、パート・アルバイトスタッフが多い環境では、作業指示書の有無によって作業効率や安全性に大きな差が出てしまいます。
自社での導入を検討する際のチェックリスト
作業指示書を効果的に活用するためには、単にテンプレートを導入するだけではなく、自社に合った形で設計・運用することが重要です。そこで、自社で導入を検討する際に確認しておきたいポイントを以下にチェックリスト形式でまとめました。
- 現場の業務が属人化していないか?
- 業務中に「言った・言わない」のトラブルが発生していないか?
- 作業ミスや手戻りが多発していないか?
- 新人が戦力化するまでに時間がかかっていないか?
- 紙やExcelベースの運用に限界を感じていないか?
当てはまるものが多い場合は、作業指示書の改善をおすすめします。
導入初期はシンプルな項目から始め、現場のフィードバックを基にブラッシュアップしていくことで、現場で使われる指示書に育っていきます。今後のDX推進や人材不足への対応を見据え、作業指示書の整備を業務改革の第一歩として取り組んでみてはいかがでしょうか。
作業指示書は“業務の地図

作業指示書はたとえるなら、業務を正確・効率的に進めるための“地図”です。
わかりやすい作業指示書を作成し運用すれば、初めて業務をおこなう社員でも的確な作業が可能です。ITツールを使って作業指示書を作成すると、運用後の修正も簡単にでき、分析作業までスムーズにおこなえます。まだ作業指示書の作成・運用に帳票管理システムを導入されていない場合には、この機会に検討をおすすめします。
株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)の現場帳票システムi-Reporterの導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
作業指示書などの現場帳票のシステム化を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか」といった課題や不安がつきものです。
そのような会社様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。
まず、やるべきことを整理するだけでも効果的です。お話を伺いたい方は、無料の『ちょこっと相談室』(Teams:オンライン)で、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。