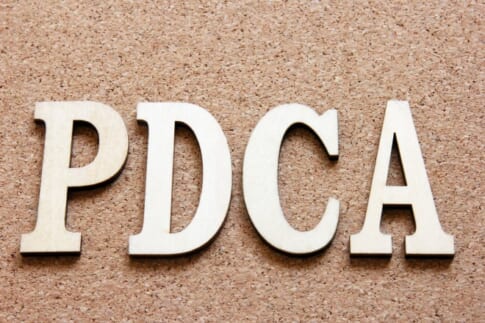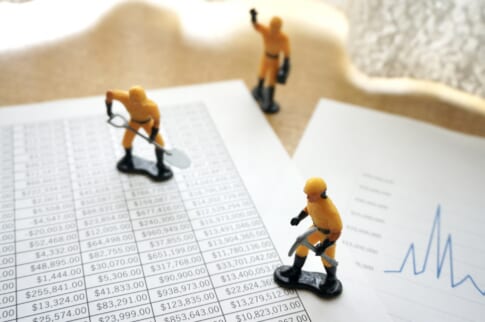作業報告書は、業務の進捗状況や成果を記録するために使用する帳票です。製造業の現場でも多く使用されており、業務の振り返りや分析に使用できます。
この記事では、わかりやすい作業報告書の書き方やテンプレートを紹介します。効果的な作業報告書の作成や記入方法についてお悩みの方はぜひ参考にしてください。
「i-Reporter」は導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)、国内トップシェアを誇る現場帳票システムです。導入することで、作業報告書など現場帳票の「記入・報告・管理」すべてのペーパーレス化を実現し、さまざまな業務の効率化やDXにつなげることができます。
また、弊社株式会社サンソウシステムズでは、要件定義から設計・導入、その後の運用管理まで、お客様に寄り添った伴走支援が可能です。ぜひ、ご一緒に現場の業務課題を整理していきましょう。サービス資料を用意しましたので、併せてこの機会にこちらから無料でダウンロードしてみてください。
導入実績4,000社以上
目次
作業報告書とは
作業報告書とは、業務やプロジェクトの進捗状況や成果を社内や取引先に伝える目的で作成する帳票です。必要な項目がまとめられた作業報告書があれば、業務に携わる関係者が進捗状況や成果を把握しやすくなります。
製造業の現場で使われる作業報告書は、日報や週報など、一定期間の業務を記載して社内で活用するケースが多いです。作業報告書を作成しておくと、後から業務の振り返りや分析もおこなえ、今後の業務の策定や改善にも活かせます。
作業報告書を作成する目的
作業報告書の目的は、業務の透明性と効率性を高めることです。まず、作業内容および作業状況の共有が目的として挙げられます。日々の業務で、作業者自身しか把握できない細部の情報を文書化することで、管理者や関係者との情報共有が可能です。
作業に要した時間や進捗状況など、作業者でなければ正確に把握できない情報を詳細に記述することで、チーム全体の状況認識を統一できます。
次に重要な目的が、問題点の共有です。作業中に発生した課題や障害を報告書に記録することにより、潜在的なトラブルやリスクを事前に特定し、適切な対策を講じられます。
さらに、作業報告書の作成は生産性の改善にも貢献します。作業過程の問題点が可視化されることで、非効率な作業フローや改善すべきポイントが明確になり、業務プロセス全体の最適化が可能です。作業報告書は、単なる報告だけでなく、業務改善のための貴重な資料としても機能します。
作業報告書と業務報告書の違い
業務報告書は、日々の職務から得られた知見や重要な情報を管理職へ定期的に伝達するための文書として位置づけられています。
業務報告書として作成する主な書類は次の通りです。
- 業務日報
- 週次・月次報告書
- クレーム報告書
- 出張報告書
- 研修報告書
業務報告書は単なる活動記録ではなく、業務全体を俯瞰した情報や発見事項を含む、より包括的な内容です。業務報告書は活動の種類やカテゴリ別に区分して作成されることが一般的です。例えば、顧客訪問、社内プロジェクト、調査活動など、それぞれの業務領域に応じた独自の形式や内容構成で報告書が作られます。
区分けして書類作成されるため、情報の整理と検索が効率的になり、組織内での知識共有や意思決定プロセスが円滑化します。
一方、作業報告書は特定の作業や工程に焦点を当て、具体的な進行状況や技術的課題を詳細に記録することが主な目的です。
作業報告書と稼働報告書の違い
稼働報告書は、特定の期間における稼働状況を記録するための書類です。実際に業務に従事した時間だけでなく、非稼働の時間と理由も明確に記録しなければなりません。
稼働報告書は、機械設備のメンテナンス時間、システムのダウンタイム、または人員の不在期間などの非稼働時間も重要な記録対象です。非稼働時間が明確になることで、リソースの活用状況や効率性を正確に把握できます。また、非稼働の原因を分析することで、運用改善に役立てられます。
また、稼働報告書は「稼働時間中にどのような作業がおこなわれたか」の側面も含むため、作業報告書と類似した役割もあることが特徴です。組織によっては両者を区別せず、稼働報告書が作業報告書の機能も兼ねる形で運用されます。
作業報告書が個別の作業内容や進捗、課題に重点を置くのに対し、稼働報告書はリソースの稼働率や時間配分の全体像を把握することが本来の目的です。
作業報告書の項目と書き方
作業報告書には、だれがどのような作業をいつどこでおこなったのか、5W1Hを意識して正確に記載する必要があります。ここからは、作業報告書に記載する基本項目と各項目の書き方について解説しますので、作成の際の参考にしてください。
作業者の情報
作業報告書には、実際に業務をおこなった従業員の氏名や所属を記載します。複数人でおこなった場合には、代表者のみを記載し、全員の名前を名字のみに省略します。書類の作成者と作業者が異なる場合には、作成者の名前も記載しておくと確認事項が生じた際に便利です。
件名
件名は、業務の内容が一目でわかるようにタイトルを記載します。あまり長すぎる件名にならないよう、端的に記載するのがポイントです。業務に携わっていない人物が見ても業務内容がわかるように記載してあると、他部署で分析や戦略をおこなう際にも役立ちます。
作業日時
作業日時には、作業した日時や作業にかかった時間を記載します。書類作成日と作業日時が異なる場合は、それぞれの日時を別途記載しておくことがおすすめです。可能であれば、どの業務にどれくらい時間がかかったかを記載しておくと、業務改善や分析をおこなう際に活用できます。
作業内容・進捗状況
作業内容にはどのような方法で何をおこなったのかを記載します。進捗状況は全体に対して作業の進み具合を記載します。簡易的に要旨のみを記載する場合もありますが、細かく記載しておいた方が活用しやすく重宝します。また、トラブルが生じた際の原因分析に役立てることも可能です。作業工程が複数ある場合には、工程ごとに詳しく作業内容を記載しておくと見やすくなります。
次回の作業予定など
1回の作業では終わらない業務の場合に、上司や次の担当者がわかるように次回の作業予定を記載しておきます。次回どのような作業をおこなうのか明確にしておくと、人員配置を考え、作業時間を予測するのに活用できます。次回の作業日が離れている場合には、日時も記載しておくと便利です。
特記事項・備考
特記事項・備考には、設定した項目に当てはまらない情報を記載します。具体的には、作業の中で気が付いた点や、休務者や機械の不具合など通常とは異なる事態が発生した場合に記録する項目です。特に書くことがない場合は未記入、もしくは「特になし」と記入します。
作業報告書の例文

作業報告書の項目と書き方を解説してきましたが、ここでは実際に書類を作成する際の例文を紹介します。システム開発と定期点検の例文を紹介するので、作業報告書を作成する際の参考にしてみてください。
システム開発の作業報告書例文
システム開発作業報告書
- 作業者情報 報告者 システム開発部 田中〇〇
- 作成日 2025年4月10日
- 件名 既存システム機能向上・効率化プロジェクト
- 作業日時 作業期間 2025年4月1日~4月10日
- 総作業時間 40時間
- 作業内容・進捗状況
1.要件定義書のレビュー 進捗率 90%
詳細
・機能要件の整合性確認を完了
・クライアントからの最終承認待ち
2.開発環境の構築 進捗率 100%
詳細
・開発サーバーの設定完了
・必要なライブラリ・フレームワークのインストール完了
3.既存システムとの連携 進捗率 80%
詳細
・API連携インターフェースの設計完了
・認証システムとの連携テスト完了
・〇〇システムとの連携に技術的課題が発生
・連携方式の代替案を現在検討中 - 次回の作業予定
・既存システムとの連携部分の設計完了(4月15日まで)
・〇〇システムとの連携に関する代替案の提案・決定 - 特記事項・備考
〇〇システムとの連携における課題は、API仕様の互換性に関する問題であることが判明。レガシーシステムの制約により、当初想定していた連携方式では実装が困難な状況。
装置の定期点検の作業報告書例文
装置定期点検作業報告書
- 作業者情報 報告者 佐藤〇〇
- 作成日 2025年4月10日
- 件名 株式会社××所有コピー複合機定期点検
- 作業日時
作業日 2025年4月10日
作業時間 9:00~12:30(3.5時間) - 作業内容・進捗状況
1. コピー複合機定期点検 進捗率 100%
詳細
・本体内部の清掃完了
・各部品の磨耗状況確認完了
・給紙ローラーの清掃・調整完了
2. 紙詰まり対応 進捗率 100%
詳細
・紙詰まり頻発カ所(第2給紙トレイ付近)の重点点検実施
・給紙ローラーの磨耗を確認(交換推奨レベルに近づいている)
・紙詰まり検知センサーの位置調整実施
3. 軽微なメンテナンス 進捗率 100%
詳細
・ファームウェアのアップデート実施(Ver.3.12.5 → Ver.3.14.2) - 次回の作業予定
・6カ月後(2025年10月頃)に次回定期点検を予定
・給紙ローラーの交換作業を次回点検時に実施予定 - 特記事項・備考
第2給紙トレイの給紙ローラーに磨耗が見られるため、次回定期点検時に交換を推奨します。現状でも使用可能ですが、紙詰まりの頻度が高くなる可能性があります。
作業報告書を書く際のポイント
有意義な作業報告書を作成するためには、誰が見てもわかりやすいよう客観的なデータや写真などを取り入れ、事実をありのままに記載することが重要です。ここからは、記入する際に意識するべきポイントについて解説しますので、参考にしてください。
事実のみを記載し要点をまとめる
作業報告書に記載する内容は、事実を記載し要点をまとめるように意識しましょう。個人的な主観や推測まで記載してしまうと、正確な作業内容が把握できません。誤解を招くような表現やあいまいな記載を避けることで作業状況の正確な情報を伝えることができます。
また、作業報告書はなるべく短い時間で作業内容が把握できるように意識することが重要です。
数字やグラフを用いる
文章のみ記載すると、要点をまとめられず具体性が欠けている作業報告書ができあがります。客観的なデータを示すためには、数字やグラフを取り入れることが重要です。
具体的には、目標数に対してどれくらいの商品を完成させたかを分数やグラフを使って表現すると一目で作業状況を把握できます。文章だけではあいまいになってしまう部分に、数字やグラフを用いると説得力と信頼性が増します。
写真や図を取り入れる
文章で説明するよりも写真や図を取り入れた方が直感的にわかりやすく、正確に情報を伝えられます。特に複雑な作業工程を示す際や、機械・商品の不具合を報告する場合には、文章より写真や図をそのまま載せた方が一目で内容が伝わります。
なるべく当日中に記入する
人の記憶は時間が経てば経つほど薄れていき、正確性を失っていきます。作業報告書は記憶が失われてしまう前に、作業をおこなった当日に記載するのがおすすめです。業務が忙しく当日中に書けない場合もあるかもしれませんが、記憶が鮮明なうちに記入すると情報の正確性が増します。作業当日に記入すると、情報の共有も速やかにおこなえるため、引継ぎもスムーズにできます。
内容に誤りがないようチェックする
作業報告書を提出する前には、誤りや誤字脱字、漏れがないか必ず確認しましょう。作業報告書の内容に誤りや記入漏れがあると、正確な情報が伝わらず、業務に支障をきたしてしまう可能性があります。特に、誤字脱字が多いと、可読性が下がり読み解くのに時間が必要です。
作業報告書のミスが多発した場合、記入者の評価が下がってしまい信用を失う恐れがあります。時間をおいて読み返し、ほかの従業員に読んでもらうなど、しっかりチェックすることが重要です。
結論から先に書く
結論が先に書かれていない文書では、内容を正確に理解できず、読み手は最初から最後までしっかりと読み込まなければなりません。資料の細部まで把握することは大きな時間的負担となり、重要な情報を見逃す原因のひとつです。
一方、結論が明確に示されている文書であれば、読み手は一度目を通すだけでも核心部分を即座に把握できます。結論が最初にわかれば、必要に応じて詳細部分を読むかどうかを判断でき、情報処理の効率が向上します。
社内の上司や同僚、取引先の担当者、顧客など、作業報告書の提出先がどこであっても、報告書内でもっとも伝えたい結論を先に提示することは効果的です。
5W1Hを意識する
5W1Hの要素は次の通りです。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| Who:誰が | 誰の作業内容か |
| What:何を | 作業した内容は何か |
| When:いつ | いつの作業か |
| Where:どこで | どこで作業したか |
| Why:なぜ | 作業の目的 |
| How:どのように | 作業内容の詳細 |
求められている内容を正確に書くことは基本ですが、5W1Hに沿って「わかりやすさ」や「具体的な例」などを加えることで報告書の評価が高まります。抽象的な説明だけではなく、実際のケースや数値データなどの具体例を示すことで、読み手の理解を助け、情報の価値を高められます。
また、報告の内容が雑多にならず、順序良く整理されていることも重要です。関連情報をグループ化し、論理的な流れを作ることで、読み手は混乱することなく内容を把握できます。適切な見出しや段落分け、箇条書きなどの形式的な工夫も、情報の整理につながります。
5W1Hの枠組みに沿って情報整理された報告書は、単なる事実の羅列ではなく、状況の全体像を明確に伝える価値ある文書です。読み手は必要な情報を効率良く把握し、適切な判断や行動につなげられます。
作業報告書のExcelテンプレート
作業報告書を導入する場合、ゼロから作成するのは大変です。インターネット上には、無料で使える作業報告書のテンプレートを公開しているサイトがあります。ここからは、作業報告書のExcelテンプレートを公開しているサイトを紹介しますので、ご活用ください。
bizocean
bizoceanは、3万点以上の書式テンプレートやひな形が利用できるサイトです。経理や人事など700種類以上の幅広いカテゴリからテンプレートを探せます。書式以外にも、画像やハガキに印刷できるデータも利用可能です。
作業報告書のテンプレートは、以下のリンクからダウンロードできます。なお、ダウンロードする際には会員登録が必要です。
bizroute
bizrouteは、ビジネスで使えるテンプレートやノウハウを紹介しているサイトです。テンプレートの公開だけではなく、記入方法なども記載しています。送付状や雇用契約書、業務フロー図など、さまざまなジャンルの書式テンプレートが利用可能です。
作業報告書のテンプレートは、以下のリンクからダウンロードができます。会員登録は不要です。
[文書]テンプレートの無料ダウンロード
[文書]テンプレートの無料ダウンロードは、案内文や議事録、FAXの送付状など246種類のカテゴリから文書テンプレートが利用できるサイトです。ビジネス文書以外にも、回覧板やチラシ・ポスターなど幅広い種類のテンプレートを取り扱っています。
こちらのサイトでは以下のリンクから作業日報をダウンロードできます。
作業報告書を書くメリット
製造業の現場で作業報告書を作成すると、業務の効率化や社員の育成に活用できます。ここからは、作業報告書の作成により得られるメリットについて紹介しますので、自社にとって役立つかご検討ください。
作業内容を共有できる
作業報告書を作成すると、同じ部署の従業員はもちろん、他部署や取引先などにも共有できます。作業報告書には実際におこなった作業の内容や進捗状況が記載されているため、上司や責任者が現在と過去の状況を確認するのに役立ちます。
わかりやすい作業報告書が作成できていれば、専門外の人物が読んでも状況を共有できるでしょう。最初に作業した従業員とは別の従業員やほかの業者への引継ぎも、作業報告書を通じてスムーズな共有が可能です。
生産性の向上に役立つ
作業報告書に時間や内容を詳しく記載しておくと、どのような作業に時間がかかっているのか分析できます。時間がかかっている作業に割く人員を増員し、より効率的な方法を模索することが可能です。
さらに同じ作業をおこなう際に、過去の作業報告書の手順やトラブル回避方法などを参考にできます。初めて業務に携わる場合にも、最初から指導する時間を省けますし、作業のイメージをつかみやすくなります。
進捗状況の管理がしやすくなる
作業報告書を作成すると、進捗状況の管理をしやすくなる点もメリットです。口頭で作業状況を共有する場合、責任者へ情報が届くまで時間がかかってしまいます。内容がまとめられた作業報告書を電子化しておけば、即座に責任者まで進捗状況の把握が可能です。
素早く進捗状況の遅れやトラブルを確認できれば、あらかじめスケジュール調整や人員配置などの対策が取れます。ギリギリで納期に間に合わないことが発覚するなどのトラブルを回避しやすくなります。
社員の育成に使える
作業報告書を作成する際に、作成者はおこなった業務内容を振り返ります。自身がおこなった作業を振り返ることで、作業中には気づけなかった課題や改善策を見いだせます。従業員の成長を促すためには上司からの指導も大切ですが、従業員自身の気づきや意識の変化がより重要です。
毎日、作業報告書を書き続けることで、以前より成長した自分に気が付くこともモチベーションアップにつながります。社員の育成に役立てたい場合には、作業報告書に改善策や所感など自由に記載できるスペースを設けておくのがおすすめです。
作業報告書を書くデメリット
作業報告書を作成するとさまざまなメリットがあることを紹介しましたが、いくつかのデメリットもあります。ここからは、作業報告書を作成するデメリットについて解説します。
作業報告書の作成に時間がかかる
作業報告書をわかりやすいものにしようとすればするほど、作成に時間がかかってしまいます。作業報告書は、一日の仕事が終わってから記入しなければならないため、残業時間が増える可能性があることも懸念点です。
作業報告書の記入に手間がかかりすぎると、作成することが目的になり、内容が薄くなってしまう恐れがあります。効率良くわかりやすい作業報告書を作成できるよう、レイアウトを工夫し、入力支援機能の付いた帳票管理システムを導入するのもひとつの手段です。
記載内容が人によってバラバラになる
作業報告書は、従業員の文章力によって質が左右されます。伝わりやすい文章で書かれていない場合には、記録しても価値が薄くなってしまうでしょう。自由記入できる欄が増えるほど差が出てしまうため、チェックリスト方式や、写真や図を使えるようにするなどの対策が必要です。
また、作業報告書を記入する目的をしっかり伝え、定期的に記入方法や伝わりやすい文章の書き方を指導すると作業報告書の質を上げられます。
作業報告書を作成する本来の目的を見失う
報告書作成が日常業務の一部となると、報告書を書いて満足する状態に陥りがちです。報告書を作成すること自体が目的化してしまい、その先にある情報共有、問題解決などの本質的な目的が忘れられます。
報告書が形骸化することで、本来最も重要である作業内容の把握と共有ができません。書類は作成するものの、内容が表面的で重要な情報が欠けてしまうなど、報告書本来の機能が失われます。形骸化した報告書は、業務上の課題や改善点を見つけ出せず、組織の成長や業務効率化の機会を逃します。
従業員には、作業報告書を作成する目的と重要性を再認識してもらうことが大切です。報告書は単なる記録ではなく、情報共有のツールであり、問題発見・解決のための重要な手段であることを組織全体で理解する必要があります。
作業報告書の作成は帳票管理システムが便利
製造業の現場では、ITツールを活用した効率化が求められています。作業報告書も帳票管理システムを導入し活用すれば、コストパフォーマンス良く効率化が可能です。ここからは、帳票管理システムを導入した場合に改善が期待できる点を紹介します。
入力支援機能により時間の短縮が可能
多くの帳票管理システムには、入力支援機能が搭載されています。入力支援機能とは、項目ごとにあらかじめ設定した選択肢や数値、テキストのみなどの入力規制をかける機能です。他にも入力必須項目の設定や、時刻や日付を自動取得することができます。
入力支援機能を使うと、決められた項目を毎回手入力する手間が省け、記入ミスや抜け・漏れによる書き直しを削減できるため、作業報告書を書く時間の短縮が見込めます。
情報の共有がしやすくなる
帳票管理システムを使うと、PCやスマートフォンなどさまざまな端末でアクセスできるようになるため、作業報告書の共有がしやすくなります。また、リアルタイムでデータの更新がされるので、最新の情報をインターネットがつながる場所であれば、どこにいても素早く最新情報へのアクセスが可能です。
承認ルートを設定できる帳票管理システムであれば、上司や責任者へスムーズに連携できます。共有できる範囲も容易に設定でき、必要な情報を適切に管理できる点もメリットです。
紙帳票に比べコストを削減できる
作業報告書を紙帳票で管理する場合、紙の購入費や保管場所の確保にコストがかかります。帳票管理システムであれば、必要最低限の帳票のみ印刷すれば良いため、コストパフォーマンスに優れています。
帳票の保管もクラウドやサーバー上でおこなえ、過去の作業報告書を探しやすい点もメリットです。紙を使用しないことで環境への配慮ができるため、持続可能な社会への貢献もできます。
分析がしやすくなる
帳票管理システムに保管した作業報告書は、ExcelやCSVなどに出力できるため、転記の必要がありません。例えば、平均作業時間を計算したい場合、紙の作業報告書であれば1枚ずつ入力された数値を拾って手計算する必要があります。
帳票管理システムであれば一括して出力できるため、転記ミスなく分析が可能です。検索やソートも簡単にできるので、探したい情報をスピーディに見つけられます。ラベル機能を活用して、作業ごとに帳票を分類しての管理も可能です。
写真の添付や他システムとの連携が可能
写真や画像の添付、他のシステムとの連携がしやすい点も帳票管理システムの便利な点です。タブレットを使用して作業報告書を作成すれば、写真を撮影してスムーズに添付でき、手書きの図を書き加えられます。QRコードやバーコードに対応していれば、帳票管理システムへのアクセスも簡単です。
また、製造ラインを管理するPLCなどのIoT機器から直接データの取得できる帳票管理システムもあります。反対に、帳票管理システムに入力したデータを他のITツールへ連携させられれば、情報の共有や分析に役立ちます。
効率良く作業報告書を作成し活用しましょう
必要な情報がまとまった作業報告書を作成できると、業務の効率化や改善に役立ちます。しかし、忙しい製造業の現場で作業報告書を作成する際には、なるべく手間をかけず簡単に仕上げたいものです。
デジタルの作業報告書を作成できる帳票管理システムは、コストパフォーマンスに優れ手軽に導入できるITツールです。紙帳票での作業報告書に手間を感じている場合や、これから作業報告書の改訂や導入を検討されている場合には、帳票管理システムを活用するのがおすすめです。
株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
作業報告書などの現場帳票のシステム化を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか」といった課題や不安がつきものです。
そのような企業様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。まず、やるべきことを整理するだけでもメリットになりますので、無料の『ちょこっと相談室』(オンライン)まで、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。