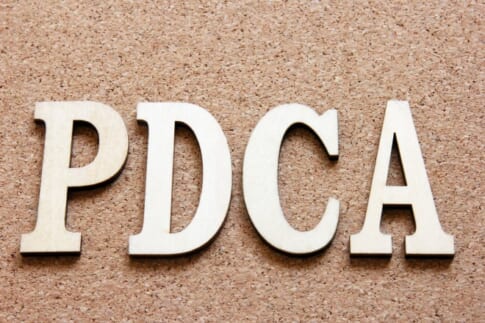日本は少子高齢化や終身雇用制の崩壊によりさまざまな業界で人手不足が深刻化しています。製造業は特に人手不足が目立つ業界で企業の経営を脅かす問題です。
本記事では、データに基づいた現状分析から、人手不足の根本原因を徹底解説します。人手不足で起きる製造業への影響や、問題を解決する対策・補助金・助成金についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
株式会社サンソウシステムズでは、製造業の人手不足を解決に導く現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
コンサルティング実績の多い弊社で、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。ぜひ一度、無料の『ちょこっと相談室』(オンライン)でお気軽にご相談ください。
目次
データで見る製造業の人手不足の現状と将来予測
人手不足は、製造業の現場において深刻な課題です。本章では、データに基づいて現状を把握し、将来予測について解説します。
製造業の人手不足の現状
厚生労働省の調査によると、中小企業における産業別社員数過不足DI(※1)において、製造業は感染症拡大前の2019年より人手不足が高まっていることが明らかになりました。
また、製造業の有効求人倍率(※2)は平均倍率の約2倍(2025年4月時点)と高い水準で推移しており、人手不足が深刻化していることが伺えます。
参考:厚生労働省「2024年版 ものづくり白書」|「一般職業紹介状況(令和7年2月分)について」
※1 産業別社員数過不足DI:産業ごとの社員数における過不足状況
※2 有効求人倍率:求職者1人に対してどれだけの求人があるかを示す指標で、数値が高いほど人手不足の状態を示す
製造業の人手不足の将来予測
厚生労働省の調査によると、34歳以下の若年就業者は減少し、高齢就業者数は増加していることも明らかになっています。少子高齢化が進む日本において、若年層の労働力は社会を支える上で不可欠です。
しかし、若年就業者が増えなければ、製造業における人手不足はさらに深刻化する可能性があります。また、熟練労働者の高齢化により、技術・技能の伝承が難しくなり、企業の生産力が下がることも避けられません。
製造業の人手不足の原因
製造業における人手不足は、複数の要因が複雑に絡み合って深刻化しています。本章では人手不足の4つの原因を詳しく解説します。
労働人口の減少
製造業で人手不足が進んでいる最も大きな要因は少子高齢化による労働人口の減少です。地方に住んでいる若年層が東京や大阪など都市部に集中することで、地方に工場を設けている企業は人口の流出により人材の確保が難しくなっています。
また、円安の影響により海外企業との価格競争が激化すれば給与面での待遇向上が難しく、求人を出しても人材が確保しにくいことも要因と言えるでしょう。実際に、新規求人数は減少傾向です。
さらに、熟練労働者の退職が進むことで、製造業は必要な労働力を確保することが難しくなっています。
3Kのイメージから志望する求職者が少ない
製造業は、一般的に「きつい、汚い、危険」という3Kのイメージを持たれています。企業によって環境は異なるものの、若年層の求職者にとってネガティブなイメージは製造業を敬遠する大きな要因です。
快適なオフィス環境やより魅力的な職種を求める若者が増える中で、製造業は人材獲得競争で不利な状況に立たされています。
フォローアップの失敗
採用活動におけるフォローアップの不足も、人手不足を悪化させる一因です。求職者への迅速な情報提供や、丁寧なコミュニケーションが不足すると、求職者は企業への関心を失い、他の企業へ流れてしまう可能性があります。特に、中小企業に多いケースが、採用担当者の負担が大きく、十分なフォローアップが行き届かないことです。
一方で、離職者数を抑止する対策を取っても、フォローアップ(教育)に注力するあまり既存社員から「面倒くさい」などのイメージを持たれ離職へとつながる逆効果になっているケースもあります。
また、フォローアップをする人材の不足により技術の継承ができず事業の低迷、給与の向上ができず離職するといった悪循環に陥ることも避けられません。結果的に人材の流動化が進む現代において条件の良い企業へと人材が流れてしまうため、人材不足に歯止めがかからない状態になるでしょう。
スキルミスマッチの拡大
製造業の現場では、IoTやAI、ロボティクスといった技術が急速に導入されており求められるスキルも高度化しています。しかし、求職者が持つスキルと、企業が求めるスキルとの間にミスマッチが生じていることが少なくありません。
特に、デジタル技術や自動化に関する知識・スキルを持つ人材の不足は深刻であり、人手不足をさらに加速させる要因となっています。
製造業の人手不足による影響
製造業における人手不足は、単なる人員不足に留まらず、企業の競争力や存続、そして社員の労働環境にまで深刻な影響を及ぼします。本章では、人手不足がもたらす具体的な影響について解説します。
国際競争力の低下
日本の製造業界は戦後から独自の技術を保有し、高品質な製品を製造することで国際競争力の優位性を確立しています。
しかし、昨今では人手不足の影響により独自の技術を保有する職人が減少していると同時に、世界全体での技術力の底上げで日本独自の技術を機械で模倣できるレベルまでになっています。
技術力で差をつけられないのであれば、優位性を確立するためにどれだけ業務を効率化するのかがポイントです。そのため人手不足が深刻化すると、納期遅延や品質低下が発生しやすくなり、結果的に国際競争力低下を招きます。
利益が出せず黒字倒産
人手不足が深刻化すると、受注があっても生産能力が追い付かず、利益を上げられないまま倒産(黒字倒産)するケースも発生しています。
帝国データバンクの調査によると、人手不足を理由とした「人手不足倒産」は増加傾向だと明らかになりました。受注状況が好調でも、人手不足から生産ラインを維持できずに黒字倒産してしまうこともあります。
また、外注をおこなっても外注費だけが膨らみ利益のでない状態が続いてしまうでしょう。
利益が出ないことにより経営に負荷がかかれば、既存社員への待遇改善には至らず離職率の向上につながり、さらに人手不足が深刻化する負のサイクルに陥ります。
参考:帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査(2024年度)」
業務負担の増加
人手不足が進むと悪循環へと陥りやすい理由は、既存社員への業務負担増加が挙げられます。
求人を出しても求職者が来なければ24時間稼働している工場は既存の社員だけで賄うことになります。一人当たりの業務量が増えることで、長時間労働や休日出勤が多くなり、社員のモチベーション低下や離職率上昇につながる悪循環につながる可能性があります。また、労働環境の悪化は、新たな人材の採用をさらに困難にする要因です。
さらに、働き方改革により労働時間や残業時間は規制が厳しくなっているため、既存社員だけでの稼働が厳しいと生産性の確保も難しくなり、倒産へとつながる恐れがあるでしょう。
製造業の人手不足を解決する8つの対策

製造業の人手不足を解決するには、多角的なアプローチが必要です。本章では、企業が取り組むべき8つの対策を具体的に解説します。
DXの推進
DXの推進は、人手不足を解消する上で非常に有効な手段です。業務の自動化や効率化を図ることで、少ない人数でもより多くの業務をこなせるようになります。
例えば、生産管理システムや在庫管理システム、ペーパーレス現場帳票ツールを導入することで、手作業でおこっていた業務を自動化できます。また、IoT技術を活用して工場の稼働状況をリアルタイムで把握し、異常を早期に発見することで、メンテナンスにかかる時間やコストを削減することも可能です。
さらに、DXの推進で業務プロセスの見える化・マニュアルの構築が可能になり、新卒者や転職者も業務内容を効率的に学習できます。
社員全員がマニュアル通りに業務をおこなうことで業務品質の統一・スキルの標準化が期待できるでしょう。
業務の自動化や効率化を図るツールとしておすすめしたいのが、ペーパーレス現場帳票ツール「i-Reporter」です。「i-Reporter」は使い慣れた紙やExcel帳票をデジタル化し、簡単な操作で入力作業が可能です。株式会社サンソウシステムズでは「ちょこっと相談室」という無料のオンライン相談窓口でDXの推進に関する相談も受け付けています。
効率的な育成体制を整える
社員のスキルアップは、人手不足を解消する上で欠かせません。OJTだけでなく、OFF-JTも積極的に取り入れ、体系的な育成体制を構築することが重要です。例えば、ベテラン社員の知識やノウハウを形式化し、マニュアルや研修プログラムの作成で、経験の浅い社員でもスムーズに業務を習得できるようになります。
また、時間や場所にとらわれずに学習できるeラーニングシステムの導入で、社員のスキルアップを支援することも可能です。
労働環境を改善する
製造業は「3K(きつい、汚い、危険)」のイメージを持たれがちなため、労働環境の改善は人材確保のために不可欠です。
空調設備の導入や作業スペースの改善、安全対策の徹底など物理的な労働環境の改善はもちろんのこと、フレックスタイム制やテレワークの導入など、柔軟な働き方を導入することも重要です。
また、社員の意見を積極的に取り入れ、風通しの良い職場環境を作ることも、定着率向上につながります。
さらに、社内コミュニケーションの促進は工場にありがちな属人化の解消にもつながるため、非常に有効な手段です。コミュニケーションが活性化すれば、従業員同士で悩みや困りごとを相談しやすい環境が作れます。従業員同士の信頼関係の向上が期待でき、業務の効率化にもつながるでしょう。
社員満足度を高める
社員満足度を高めることは、定着率向上に直結します。給与や福利厚生の改善はもちろんのこと、キャリアパスの明確化や評価制度の見直し、ワークライフバランスの実現など、多角的な施策が必要です。
社員の頑張りを正当に評価し、昇給や昇格の機会を与えることで、モチベーションを高められます。また、定期的な面談を実施し、社員の悩みやキャリアプランについて相談に乗ることで、信頼関係を構築し、離職を防ぐことも可能です。
スキルアップを支援する
社員のスキルアップを支援することは、企業の成長にもつながります。
資格取得支援制度や研修参加支援制度を設け、社員のスキルアップを積極的に支援します。また、外部講師を招いて社内研修の実施や、eラーニングシステムの提供など、多様な学習機会を提供することも有効です。
スキルアップした社員にはより高度な業務を任せることで、モチベーションを高め定着率向上につなげられます。
採用戦略を見直す
従来の採用方法にとらわれず、多様な採用チャネルを活用しましょう。求人サイトや人材紹介会社だけでなく、SNSや自社ホームページでの採用情報の発信、リファラル採用の導入なども有効です。
また、採用ターゲットを明確にしターゲットに合わせた採用活動の展開や、求職者が就業先を選ぶ基準を理解することも欠かせません。
厚生労働省が令和2年に調査した「令和2年転職者実態調査の概況」における現在の勤め先を選んだ理由を紹介します。
| 転職理由 | 割合(%) |
| 仕事の内容・職種に満足がいくから | 41.0% |
| 自分の技能・能力が活かせるから | 36.0% |
| 地元だから(Uターンを含む) | 13.9% |
| 賃金が高いから | 15.1% |
| 労働条件(賃金を除く)が良いから | 26.0% |
| 安全や衛生等の職場環境が良いから | 7.4% |
| 会社の規模・知名度 | 7.9% |
| 会社の将来性があるから | 12.2% |
| 転勤が少ない、通勤が便利だから | 20.8% |
| 前の会社の紹介 | 5.6% |
| その他 | 21.7% |
| 不明 | 0.9% |
特に多く支持を集めたのは「仕事内容・職種に満足がいくから」です。また「自分の技能・能力が活かせるから」と合わせると合計して77%の結果でした。現在の求職者が仕事・企業を選ぶ基準を理解し、基準に合わせた企業改革が必要です。
多様な人材を受け入れる
女性や外国人、高齢者など多様な人材を受け入れることで、人手不足を解消できます。
女性が働きやすい環境を整備するために、育児休暇制度の充実や時短勤務制度の導入、託児所の設置などを検討します。また、外国人社員が安心して働けるように、日本語教育や文化交流の機会の提供も重要です。高齢者には、経験や知識を活かせる業務を任せ、短時間勤務制度を導入するなど、柔軟な働き方を提案しましょう。
外国人を雇用する際は在留資格・期間を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられているため、必ずおこないましょう。
アウトソーシングを活用する
自社でおこなう必要のない業務は、積極的にアウトソーシングを活用しましょう。例えば、経理業務や人事労務業務、ITサポート業務などをアウトソーシングすることで、社員はコア業務に集中できます。
また、専門的な知識やスキルが必要な業務をアウトソーシングすることで、業務の質を高めることも可能です。アウトソーシング先を選ぶ際には、実績や費用だけでなく、セキュリティ対策や情報管理体制なども確認することが重要です。
製造業の人手不足を解消した企業事例

本章では、DXの推進や労働環境の改善、育成体制の整備によって人手不足を解消した企業の事例を紹介します。
DX推進で現場の効率化とモチベーションアップ

天津電装電子有限公司(TDE)は、自動車部品の製造・販売をおこなう企業です。同社では長年、生産現場で200種類以上の紙帳票を使用しており、年間数十万枚もの紙を消費していました。紙資源の問題に加え、帳票記録の検索に手間がかかり、データの活用が進まないことも課題の一つだったそうです。
ペーパーレス現場帳票ツール「i-Reporter」を導入した結果、現場の紙使用量の約9割相当の年間30万枚を削減しました。また、帳票データを簡単に検索できるようになったことで、管理業務だけでなく関連部署全体の業務効率が向上しました。離れた工場間を移動する必要もなくなったそうです。
また、現場の意識にも変化が生まれ、主体的に改善アイデアが出るようになりました。例えば、iPadで生産指示看板のQRコードを読み取ることで、作業効率化やミスの抑制を実現しています。
参考:株式会社シムトップス「天津電装電子有限公司(TDE)様 導入事例」
女性が働きやすい環境の整備で企業イメージ向上
旭電気株式会社は、コイル・モータの製造・設計、機械加工・板金加工をおこなう企業です。同社では主力製品の手作業中心で女性社員が多い状況でした。しかし、新たな製品の設計・製造には電気の専門知識が不可欠な設計が必要で、既存の女性社員から雇用不安が生まれていたそうです。
この課題に対し、2つの制度を整備しました。
1つ目は、新事業の業務知識習得のために、一日に一つずつ専門知識を身につけるレッスンを実施する「教育体制の構築」です。2つ目は、「女性が仕事を継続しやすい人事制度の整備」です。妊娠中の配置転換への配慮、育児休業期間中の代替要員の確保、育児休業中の社員への情報提供、短時間勤務制度をつくることで、働きやすい環境を整えました。
また、フレックスタイム、半日休暇、誕生日休暇制度、ノー残業デー、年次有給休暇の取得促進など、多様な働き方を支援する制度も導入しました。
その結果、職場への定着率が向上し、「女性が働きやすい企業」という評判も広がり、優秀な人材の採用と定着に大きく貢献しています。
参考:経済産業省「中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集」
経験豊富な社員による育成体制を整備
株式会社協和精工は、電気機械器具を製造する企業です。同社の課題は、品質保証を担える人材不足です。
そこで、大手企業を退職した経験豊富なシニアを採用し、業務改善によるコストカットを推進しました。 また、若手社員に向けた「社内塾」を開講し、前職で工場長クラスの経験を持つ男性パート社員を塾長に迎え、意識改革やプロセス改善を学びました。
結果、品質保証を担う人材も育成できただけでなく、積極的な人材育成の取り組みによって業績の回復と新分野への進出に成功しています。また、多様な人材の確保にも成功し、現在では「若手が元気な会社」として地元で評判となっているそうです。
参考:経済産業省「中小企業・小規模事業者の人手不足対応事例集」
製造業の人手不足をサポートする補助金・助成金まとめ

本章では、製造業の人手不足をサポートする補助金・助成金を8つご紹介します。
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、従業員の確保や定着をサポートするための助成金です。
具体的には、魅力ある職場づくりに向けた制度導入や、従業員の能力開発、処遇改善など、幅広い施策に対して助成金が支給されます。
人材確保等支援助成金では、以下7コースで助成しています。
(a)雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
(b)中小企業団体助成コース
(c)建設キャリアアップシステム等活用促進コース
(d) 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
(e)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
(f)外国人労働者就労環境整備助成コース
(g) テレワークコース
製造業の人手不足解決におすすめなのは、「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」「中小企業団体助成コース」「外国人労働者就労環境整備助成コース」「テレワークコース」です。助成額や要件はコースによって異なります。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するためにおこなう休業や教育訓練、出向に対して助成するものです。雇用保険適用事業主が対象で一定の要件を満たすことが必要です。
主な要件としては、
- 経済上の理由により、生産量または売上高が一定以上減少していること
- 労働者との間で休業等に関する協定を締結していること
- 休業、教育訓練、出向を実施していること
などが挙げられます。
受給額は、休業した場合は事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練をおこなった場合は賃金負担額の相当額に3分の2または2分の1の助成率を乗じて支払われます。
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障がい者など、就職が困難な者を雇用する事業主に対して支給される助成金です。雇用機会を増やし、安定的な雇用の促進が目的です。
主な要件としては、
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介で雇用したこと
- 雇用保険一般被保険者または高年齢被保険者として雇用し、継続した雇用が認められること
などが挙げられます。
受給額は、60歳以上の高年齢者は50万円または60万円、重度障がい者等を除く身体・知的障がい者は50万円または120万円、重度障がい者は100万円または240万円です。ただし、雇用形態や要件によって異なります。
参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」
業務改善助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引き上げを図るための制度です。設備投資やコンサルティングの導入、従業員に対する研修など、生産性向上に資する取り組みをおこなう事業主に対して、費用の一部が助成されます。貨物自動車やパソコン・タブレット・スマートフォンといった端末の新規購入など、通常助成対象として認められていないものも対象です。
助成額は30万円から600万円です。ただし、最低賃金の引き上げ額や引き上げる労働者数などによって異なります。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善などを支援するものです。働き方改革や賃上げ、インボイス導入といった制度の変更に対応するために実施しています。
主な要件としては、
- 付加価値額のCAGRが3.0%以上増加していること
- 支給した給与総額のCAGRが3.0%以上増加していること、または都道府県の最低賃金の直近5年CAGRより増加していること
- 都道府県の最低賃金より30円アップしていること
- 一般事業主行動計画の策定・公表をしていること
などが挙げられます。
補助額の上限は、従業員5人以下で750万円、6人~20人で1,000万円など従業員数によって異なります。また、特例もあるため事前にチェックしてください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が働き方改革や賃上げ、インボイス導入といった制度の変更に対応するため、作成した経営計画に沿って販路開拓などの取り組みをおこなう費用を一部補助する制度です。補助対象者は従業員20人以下の小規模事業者です。
主な要件としては、
- 資本金や出資金が5,000蔓延以上の法人に株式を100%保有されていないこと
- 直近過去3年の課税所得の年平均が15億円を超えていないこと
- 商工会の管轄地域内で事業をおこなっていること
などが挙げられます。
補助額の上限は、通常枠で50万円、賃金引上げ枠や創業枠、後継者支援枠などで200万円です。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者などがITツール導入費用の一部を補助する制度です。業務効率化や売上向上が目的で、ソフトウェアやクラウドサービス、ハードウェアなどの導入がサポートされます。
補助額・補助率は、導入するITツールや事業規模によって異なります。補助金を受給したい場合は、IT導入支援事業者との事前連携をおこなうなど、審査の要件を確認してください。
参考:IT導入補助金2025
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、パート、アルバイト、契約社員といった非正規雇用労働者の企業内でキャリアアップを促進するための助成金制度です。企業が非正規雇用労働者の処遇改善や能力開発に取り組むことで、費用の一部が助成されます。
キャリアアップ助成金の申請までに、就業規則の改定や規則に基づく正社員化などの取り組みが必要です。また、取り組み開始後6カ月分の賃金を支払った後の申請となるため、注意が必要です。
製造業の人手不足対策に活用できるi-Reporter

製造業における人手不足対策は多くの企業が取り組んでいますが、改善へと至った事例は多くありません。そのため、先述したDXの推進も視野に入れておく必要があります。
DX推進の一つの方法として、現場の情報をデジタル化し、業務改善に役立つ現場帳票システムの導入が挙げられます。現場帳票システムの中でもおすすめしたいのが、「i-Reporter」です。
「i-Reporter」は、紙の帳票をタブレットで再現し、現場でのデータ入力を容易にするシステムです。手書き感覚で情報を入力できるため、デジタルツールに不慣れな社員でもスムーズに導入できます。
株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
現場帳票のシステム化を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか」といった課題や不安がつきものです。
そのような企業様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。
まず、やるべきことを整理するだけでもメリットになります。
お話を伺いたい方は、無料の『ちょこっと相談室』(Zoom:オンライン)で、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応いたします。
製造業の人手不足解決策を実践しよう

人手不足は、製造業にとって大きな課題です。しかし、本記事でご紹介したさまざまな解決策を、自社の状況に合わせて実践していくことで、状況の改善につなげられます。
「どの部門で、どのようなスキルを持った人材が不足しているのか」「人手不足の原因は何か」「手不足によって、どのような影響が出ているのか」と現状分析と課題を明確化したうえで、解決すべき問題に優先順位をつけることが重要です。そして、それぞれの課題に対して、「〇〇部門の作業時間を〇〇%削減する」「社員の残業時間を〇〇%削減する」「採用応募者数を〇〇%増加させる」といった具体的な目標を設定します。
その後、本記事で紹介したさまざまな解決策を実行しましょう。実行後には定期的に効果測定をおこない、必要に応じて改善策を講じることで人手不足解決に導けます。
また、紹介した解決策と補助金・助成金情報も参考に、人手不足解消に向けた具体的なアクションプランを策定し、実行に移すことも重要です。未来の製造業を担う人材を確保し、持続可能な成長を実現しましょう。