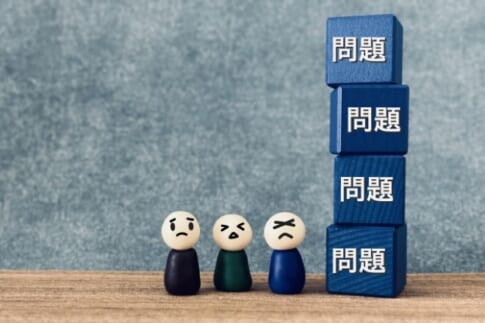製造や物流業界では、トレーサビリティの重要性が高まっています。トレーサビリティとは、製品の原材料調達から、製造、加工、流通、販売、そして廃棄に至るまでの追跡が可能な仕組みです。
本記事では、トレーサビリティの意味や必要性、各業界での活用例をわかりやすく解説します。さらに、トレーサビリティシステムの意味や導入のメリット・デメリット、システム選定のポイントまで徹底的に解説します。顧客に安心安全に製品を届けるためにトレーサビリティを理解し、信頼性の高い企業を目指しましょう。
導入実績4,000社以上
目次
トレーサビリティとは

トレーサビリティとは、製品の原材料調達から、製造、加工、流通、販売、そして廃棄に至るまでの追跡が可能な仕組みです。トレーサビリティにより、問題発生時の原因究明や影響範囲の特定、品質管理、そして消費者の信頼性向上につながります。
また、必要に応じて追跡までの情報を遡って確認できる仕組みを実現することを「トレーサビリティを取る」と表現します。
トレースフォワード(追跡)とトレースバック(遡及)の意味
トレーサビリティを理解する上で重要なのが、「トレースフォワード(追跡)」と「トレースバック(遡及)」という2つの用語です。トレーサビリティは、蓄積された情報を基にトレースフォワード・トレースバックを可能にすることで、はじめてトレーサビリティが実現します。
| 方式 | 意味 | 説明 |
| トレースフォワード(追跡) | 製品の流通経路を追跡 | 製造工程に沿って、製品が「どこへ行ったのか」を追跡することです。例えば、製造工場で不備が判明した場合、どの顧客に製品が届けられたのかを特定でき、リコールや不良品の対策に活用できます。 |
| トレースバック(遡及) | 製品の製造履歴を遡って追跡 | 製品が「どこから来たのか」を遡って追跡することです。例えば、製品に問題が発生した場合、どの原材料が使用されたのか、どの製造ラインで製造されたのかを特定でき、品質の向上・安定を期待できます。 |
簡単に言うと、生産者を「上流」、消費者を「下流」とした場合、上流から下流へ向かって製品を特定するのがトレースフォワード、下流から上流へ向かって製品を特定するのがトレースバックです。
2つの追跡方法の組み合わせで、問題発生時の迅速な原因究明と影響範囲の特定が実現できます。
トレーサビリティの方式

トレーサビリティには、大きく分けて「チェーントレーサビリティ」と「内部トレーサビリティ」の2つの方式があります。それぞれの方式は、追跡の範囲と目的に応じて使い分けられます。
チェーントレーサビリティ
チェーントレーサビリティとは、製品のライフサイクル全体、つまり原材料の調達から生産、流通、販売、そして最終的に消費者の手に渡るまで、製品の移動を追跡する方式です。サプライチェーンに関わる複数の企業や組織をまたいで情報を共有し、連携する必要があります。
チェーントレーサビリティは、以下のような場合に特に重要です。
- 食品の安全性を確保する場合
- 医薬品の偽造品対策をおこなう場合
- 製品の原産地を証明する必要がある場合
問題発生時の影響範囲特定やブランド保護ができることが、チェーントレーサビリティのメリットです。
内部トレーサビリティ
内部トレーサビリティとは、特定の企業や工場など限定された範囲内での原材料や製品の移動を把握する方式です。原材料の受け入れから製品の出荷までの社内プロセスを詳細に追跡します。
内部トレーサビリティは、以下のような場合に特に有効です。
- 製造工程における不良品の発生原因を特定したい場合
- 製品の品質を向上させたい場合
- 在庫管理を効率化したい場合
迅速な問題解決や効率的な生産体制を整備できることが、内部トレーサビリティのメリットです。
2つのトレーサビリティは、相互に助け合う関係にあります。内部トレーサビリティで得られた詳細な情報は、チェーントレーサビリティの一部として活用されます。 また、チェーントレーサビリティの要求事項に基づいた内部トレーサビリティのシステム設計も可能です。
トレーサビリティが重要視される背景

トレーサビリティが現代社会において重要視される背景には、主に3つの要因が挙げられます。
消費者の安全・安心志向の高まり
近年、消費者の製品に対する安全意識と安心を求める傾向が高まっています。消費者庁の消費者意識基本調査によると、商品の予約や購入で安全性を重要視している人は6割近くいることが明らかになりました。
企業は消費者の期待に応えるため、製品の生産から消費までの過程を透明化し、安全性を証明する必要があります。トレーサビリティの導入で、消費者は製品の情報を確認し、安心して商品を選択できるようになります。トレーサビリティは、企業と消費者の信頼関係を構築する上で不可欠な要素となっています。
法規制の強化とコンプライアンスの重要性
食品や医薬品、自動車など多くの業界でトレーサビリティに関する法規制が強化されています。具体的には「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」や「医薬品、医療機器等法」「道路運送車両法」などが挙げられます。
法規制は消費者の安全を守ることが目的で、企業は法令遵守の観点からもトレーサビリティの導入が求められています。法規制に違反した場合、罰金や営業停止などの厳しい処分が科されることも避けられません。
トレーサビリティの導入で、企業は法規制への対応を効率化しコンプライアンスリスクを低減できます。企業が社会的責任を果たす上で重要な役割を持ちます。
サプライチェーンの複雑化とグローバル化
グローバル化の進展に伴い、製品のサプライチェーンはますます複雑化しています。原材料の調達や製造、加工、流通、販売といった各段階が、複数の国や地域にまたがることが一般的です。サプライチェーンが複雑化するほど、製品の品質管理や安全性の確保が難しくなります。
トレーサビリティの導入でサプライチェーン全体を可視化し、問題発生時の原因究明や対応を迅速におこなえます。また、サプライチェーンにおける不正行為や偽造品の流通を防止する上でも有効です。グローバルなサプライチェーンにおいて、トレーサビリティは企業の競争力を高めるための重要な要素となっています。
トレーサビリティの導入効果

トレーサビリティの導入による主なメリットを4つ解説します。
品質の向上
トレーサビリティの導入で、製造プロセスの全工程が可視化され、追跡できるようになります。全行程の追跡によって潜在的な品質リスクを事前に特定・改善が可能です。
例えば、特定のロットや製造ラインで品質のばらつきが発生している場合、パターンを早期に発見し、対策を講じられます。結果、不良品の発生率を低減し、製品全体の品質を向上させられます。また、万が一不具合が発生した場合でも、原因究明を迅速におこない、再発防止につなげられることもメリットのひとつです。
安全確保
トレーサビリティは、製品の安全性を確保する上でも重要な役割を果たします。もし製品に不具合が見つかった場合、トレーサビリティの活用で、製品がいつ、どの工程で、どの原材料を使用して製造されたかを即座に追跡できます。
結果、問題のある製品のロットや製造日時を特定し、影響範囲を抑えた回収作業が可能です。特に、食品や医薬品といった安全性が重視される業界においては、トレーサビリティは消費者の健康を守るための重要な手段となります。
信頼性の向上
トレーサビリティは、企業に対する顧客や取引先の信頼性を高める効果も期待できます。トレーサビリティを通じた原材料の調達先や製造過程、流通経路など詳細な情報を提供することで、消費者は製品の品質や安全性に対して安心感を持てるでしょう。
また、トレーサビリティは環境配慮への取り組みをアピールする機会にもなります。例えば、持続可能な方法で調達された原材料を使用していることを示せば、企業の社会的責任をアピールし、ブランドイメージ向上につなげられます。
効率的な顧客管理
トレーサビリティで得られた情報を顧客管理に活用することで、より効率的なマーケティングや顧客対応をおこなうことが可能です。例えば、顧客が購入した製品情報の追跡で、顧客の嗜好や購買履歴を把握し、パーソナライズされた情報提供やキャンペーン展開につなげられます。
また、製品に関する問い合わせがあった際にも、トレーサビリティ情報の参照で、迅速かつ正確な回答を提供可能です。これにより、顧客満足度を高め、ロイヤリティ向上への貢献も期待できます。
トレーサビリティが抱える課題

トレーサビリティは製品の品質向上や安全確保、信頼性向上に不可欠な仕組みですが、いくつかの課題が存在します。トレーサビリティの効果を引き出すためには、課題の把握と事前準備、対策が必要です。
コストと投資対効果
トレーサビリティの導入には、ハードウェアやソフトウェア、システム構築、従業員教育など多額の初期投資が必要です。また、システムの保守・更新、データ管理など継続的なコストも発生します。
そのため、長期的な視点でのコスト削減効果や品質向上効果を予測し、段階的な導入戦略を立てることが重要です。まずは一部の製品ラインや工程から導入し、効果を検証しながら徐々に拡大していくと良いでしょう。
データの整合性の確保
トレーサビリティは多岐にわたる工程から情報を収集するため、データの入力ミスや欠落が生じやすい傾向にあります。エラーを抑え、常に正確なデータの維持が求められます。
自動化されたデータ収集システムの導入や、定期的なデータ監査の実施が重要です。
組織間連携と標準化の難しさ
サプライチェーンには異なる業種や規模の企業が含まれることが多く、それぞれが独自のシステムや業務プロセスを持っています。企業間で情報を円滑に共有するためには、データフォーマットやシステムの互換性の確保が必要です。
そのため、業界横断的なトレーサビリティプラットフォームの構築や、データフォーマットの標準化を推進する必要があります。
人材育成とデータリテラシー
トレーサビリティの効果的な運用には、専門的な知識とスキルを持つ人材が不可欠です。また、システムから得られるデータを活用し、客観的な根拠に基づいた意思決定をおこなう環境を整備する必要があります。
そのため、従業員向けの教育訓練プログラムの開発やデータ分析に関する研修を実施し、データリテラシーの向上を図らなければなりません。
法規制対応と国際標準化
業界ごとに異なるトレーサビリティ関連法規制への対応が求められるため、企業としては柔軟な環境設計が必要です。グローバルサプライチェーンにおいては、各国の法規制の違いに対応する必要があり、コンプライアンス管理が複雑化しています。
そのため、法規制や業界基準に関する情報を常に収集し、変化に対応できる体制を構築する必要があります。
【業界別】トレーサビリティの活用例

トレーサビリティは、各業界でその特性に合わせた形で活用されています。ここでは、食品、医薬品、製造業、そしてIT業界における具体的な事例を見ていきましょう。
食品業界:食の安全を守るためのトレーサビリティ
食品業界では、消費者の「食の安全」に対する意識の高まりから、トレーサビリティの導入が不可欠となっています。トレーサビリティの導入で、食品の安全性を確保する取り組みがおこなわれています。
事例:農産物の生産履歴、加工食品の原材料情報
農産物においては、生産者が栽培履歴を記録し、消費者が記録を確認しています。これにより、いつ、どこで、誰が、どのように生産したのかが明確になり、安全性の確保につなげることが可能です。
また、加工食品においては、原材料の産地や加工日、製造ロットなどの情報を追跡できるトレーサビリティを確保しています。これにより、万が一問題が発生した場合でも、迅速な原因究明と対応が可能です。
医薬品業界:偽造医薬品対策と品質管理
医薬品業界では、偽造医薬品の流通防止や品質管理の徹底のためにトレーサビリティが重要視されています。消費者が安心して医薬品を使用できるよう、厳格な管理体制が求められています。
事例:医薬品の製造番号、流通経路の追跡
医薬品には、製造番号(ロット番号)が付与され、製造から流通、販売までの過程の記録が可能です。これにより、偽造医薬品の発見や、品質問題が発生した場合の原因究明を迅速におこなえます。
また、温度管理が必要な医薬品においては、輸送中の温度を記録し、品質が保たれていることを証明するトレーサビリティシステムも活用されています。
製造業:不良品の特定と原因究明
製造業では、製品の品質向上や、不良品の発生原因を特定するためにトレーサビリティが活用されています。部品の調達から組み立て、検査、出荷までの情報管理で、問題発生時の迅速な対応が可能です。
事例:部品の製造ロット、組み立て工程の記録
製品に使用される部品には製造ロット番号が付与され、どの部品がいつ、どこで製造されたのかを追跡できます。
また、組み立て工程における作業者、作業時間、検査結果などの記録で、不良品が発生した場合の原因究明や製造プロセスの改善に役立てられます。
IT業界:変更履歴や障害発生時の原因究明
IT業界におけるトレーサビリティは、ソフトウェア開発やシステム運用において、変更履歴や障害発生時の原因究明を効率化するために重要な役割を果たします。
事例:ソフトウェア開発やシステム運用における管理
IT業界では、下記のようなトレーサビリティの活用が挙げられます。
- ソフトウェア開発における変更履歴管理: ソースコードの変更履歴、テスト結果、バグ修正の記録などを追跡し、問題発生時の原因特定や修正作業を効率化する
- システム運用における障害管理: サーバーやネットワーク機器のログ、エラーメッセージ、システム設定の変更履歴などを記録し、障害発生時の原因究明や復旧作業を迅速化する
- データ管理におけるアクセスログ管理: 誰が、いつ、どのデータにアクセスしたかを記録し、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減する
トレーサビリティシステムとは

トレーサビリティを確保するために有効なのが、トレーサビリティシステムです。本章では、トレーサビリティシステムについて解説します。
トレーサビリティシステムの意味
トレーサビリティシステムとは、製品の原材料調達から、生産、加工、流通、販売、そして最終的な消費や廃棄に至るまでの各段階における情報を追跡・管理するためのシステムです。これにより、いつ、どこで、誰が、何をしたのかを把握できます。
トレーサビリティとトレーサビリティシステムは、意味や役割に違いがあります。トレーサビリティは「追跡できる状態」を意味し、「トレーサビリティシステム」はトレーサビリティを機能させるシステムを表します。似た言葉とはいえ、意味と役割を明確に区別しておきましょう。
導入メリット
トレーサビリティシステムの導入によって、企業は以下のようなメリットを得られます。
業務効率化につながる
製品に関する情報を一元管理し、必要な時に迅速にアクセスできるトレーサビリティシステムは、業務効率化に大きく貢献します。手作業での記録や調査にかかる時間を削減し、より戦略的な業務に集中できるようになります。
コスト削減に役立つ
トレーサビリティシステムは、問題発生時の迅速な原因究明や、不良品の特定を簡単にします。結果として、調査・原因特定にかかる人件費や製品の回収費用、製造ラインの停止による損失など、無駄なコストの削減が可能です。
また、在庫管理の最適化やサプライチェーン全体の効率化も期待できます。例えば、過剰在庫による保管コストの増大や、品切れによる販売機会の損失予防、リードタイムの短縮ができます。
リスクが軽減できる
トレーサビリティシステムは、食品偽装や異物混入などの問題が発生した場合に迅速かつ正確な対応を可能にします。例えば、食品偽装問題が発生した場合、問題のある製品がどこから来たのか、どのような経路をたどって消費者の手に渡ったのかを迅速に特定できます。結果、企業は問題のある製品を迅速に回収し、被害の拡大を防ぐことが可能です。また、再発防止策を講じて、消費者の信頼回復につなげられます。
そのため、トレーサビリティシステムは企業のブランドイメージ低下や、訴訟リスクを抑えられます。
導入デメリット
トレーサビリティシステム導入には、メリットだけでなくデメリットも存在します。導入を検討する際には、デメリットも考慮する必要があります。
初期投資や運用コストが必要
トレーサビリティシステムの導入には、ハードウェアやソフトウェア、システム構築費用など、初期投資が必要です。また、システムの維持・管理、従業員教育など、継続的な運用コストも発生します。
システム選定が難しい
市場にはさまざまなトレーサビリティシステムがあるため、自社の規模や業種、目的に合ったシステムを選定する必要があります。システム選定を誤ると、期待した効果が得られないだけでなく、無駄なコストが発生する可能性もあります。
トレーサビリティシステム導入・運用・管理ステップ

トレーサビリティシステムを導入し、効果的に運用・管理していくためには、段階的なアプローチが不可欠です。以下の5つのステップを参考に、自社の状況に合わせた計画を立てていきましょう。
ステップ1:目的と範囲の明確化
まず、トレーサビリティシステムを導入する目的を明確に定義します。品質向上や安全確保、顧客からの信頼性向上など具体的な目標を設定しましょう。
次に、トレーサビリティを適用する範囲を決定します。全製品、特定の製品ライン、特定の工程など範囲の明確化で、システム構築に必要なリソースやコストを正確に見積もることが可能です。
例えば、食品業界であれば「〇〇産の△△という農産物の、生産地から小売店までの全工程を追跡可能にする」といった具体的な目的と範囲を設定します。製造業であれば、「特定の部品の製造ロット番号から、最終製品の出荷先までを追跡可能にする」といった目標設定が挙げられます。
ステップ2:情報収集と記録方法の決定
トレーサビリティに必要な情報を洗い出し、どのように収集・記録するかを決定します。原材料のロット番号、製造日時、検査結果、出荷先情報など、追跡に必要な情報を明確にします。他にも、製造日時や条件、品質検査などの情報をひも付けた管理で原材料の入荷から製品の出荷まで追跡が可能です。自社に必要な情報を洗い出しましょう。
情報収集の方法としては、バーコード、QRコード、RFIDなどの技術の活用が一般的です。また、記録方法は、紙ベース、Excel、専用のトレーサビリティシステムなど自社の規模や予算に合わせた方法を選択します。
記録する情報の種類と形式の標準化で、データの整合性を保ち、効率的な追跡を可能にします。
ステップ3:トレーサビリティシステムの選定・導入
ステップ2で決定した情報収集・記録方法に基づいて、最適なトレーサビリティシステムを選定します。システムの選定にあたっては、以下の点を考慮します。
- 自社の規模や業種に合っているか
- 必要な機能が備わっているか
- 既存のシステムとの連携が可能か
- 導入・運用コストは予算内か
- サポート体制は充実しているか
システムを選定したら、導入計画を立て段階的に導入を進めていきます。トレーサビリティシステムの全社的な展開を成功させるためには、特定の製品ラインや部門を選んで小規模な導入をおこなうことが重要です。小さい規模からはじめて、システムの有効性と課題を実際の業務環境で検証します。
ステップ4:運用ルールの策定と従業員への教育
トレーサビリティシステムを効果的に運用するためには、明確な運用ルールの策定と従業員への教育の徹底が重要です。誰が、いつ、どのように情報を入力・管理するのか、責任者は誰にするのかを明確にしましょう。
また、システムの使用方法だけでなく、トレーサビリティの重要性や目的を従業員に理解させることが意識向上につながります。
定期的な研修やマニュアルの作成などを通じて、従業員のスキルアップを図り、システムを円滑に運用できる体制を構築しましょう。
ステップ5:定期的な見直しと改善
トレーサビリティシステムは、導入して終わりではありません。定期的にシステムの運用状況を評価し、改善点を見つけ出すことが重要です。システムのパフォーマンス、データの正確性、従業員の習熟度などを評価し、必要に応じてシステムの改善や運用ルールの見直しをおこないます。
また、変化するビジネス環境や法規制に対応するためにも、定期的な見直しと改善を継続的に行うことがトレーサビリティシステムの効果を高めるために重要です。
トレーサビリティシステム導入で失敗しないための選定ポイント

トレーサビリティシステムは、導入すれば必ず成功するとは限りません。自社の課題や目的に合わないシステムを選んでしまうと、期待した効果が得られない可能性もあります。本章では、トレーサビリティシステム導入で失敗しないための重要な選定ポイントを解説します。
- 目的の明確化
品質向上、安全確保、効率化など、なぜトレーサビリティシステムを導入するのかを明確にします。目的が曖昧なままでは、必要な機能やシステム要件を定義できず、不適切なシステムを選んでしまう可能性があります。 - 必要な機能の洗い出し
どのような情報を、どこまで追跡したいのか検討し、ロット管理や工程管理、在庫管理など必要な機能を洗い出しましょう。自社のサプライチェーンの特性や管理レベルに合わせて、必要な機能の過不足ない選択が重要です。 - 既存システムとの連携
ERP、生産管理システムなど既存の基幹システムとの連携は可能か、データ連携がスムーズに行えるかを確認する必要があります。連携がうまくいかない場合、二重入力やデータの不整合が起きる可能性があります。 - 操作性とUI/UX
現場の担当者が簡単に使えるように、直感的でわかりやすいインターフェースであるかを確認しましょう。操作が複雑なシステムは現場での定着が進まず、データの入力漏れや誤りが増える可能性があります。 - 拡張性と柔軟性
将来的な事業拡大や、法規制の変更に対応できるか、システムの拡張性や柔軟性を確認します。ビジネス環境の変化に柔軟に対応できるシステムを選ぶことで、長期的な利用が可能です。 - セキュリティ対策
データの改ざんや不正アクセスを防ぐためのセキュリティ対策は万全か確認します。トレーサビリティデータは機密情報を含むため、セキュリティ対策は非常に重要です。 - サポート体制
導入時のサポート、運用時の保守体制は整っているか、サポート体制を確認します。導入時のトラブル対応や、運用時の疑問点など、迅速に対応してくれるベンダーを選ぶことが重要です。 - 費用対効果
導入費用や運用費用、保守費用などを総合的なコストを考慮して、費用対効果を十分に検討します。単に安価なシステムを選ぶのではなく、長期的な視点で費用対効果の高いシステム選びが重要です。
トレーサビリティを導入して信頼性の高い企業へ

トレーサビリティの導入は、企業にとって品質向上や安全確保、そして顧客からの信頼を得る上で非常に重要です。サプライチェーン全体を可視化し、製品のライフサイクルを追跡可能にすることで、企業はより責任ある行動をとり、透明性の高いビジネスを実践できます。
自社のみのトレーサビリティ導入が難しい場合は、システムの導入がおすすめです。特にトレーサビリティの強化に役立つのが、導入社数No.1(富士キメラ総研 2024年8月8日発刊)国内トップシェアを誇る現場帳票システム「i-Reporter」です。
製造業や物流業で起きがちな「作業が適切な時間と場所でおこなわれているかわからない」という課題も、「いつどこで誰が何を記入したか」の記録・管理ができる「i-Reporter」で解決できます。
しかし、トレーサビリティ確保のためにシステムの導入を考えていても、「そもそも自社の課題がわからない」「うまく活用できるか不安」とお悩みの方もいるでしょう。
弊社では、お客様のシステム導入を丁寧に支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けています。ぜひお気軽にご相談ください。