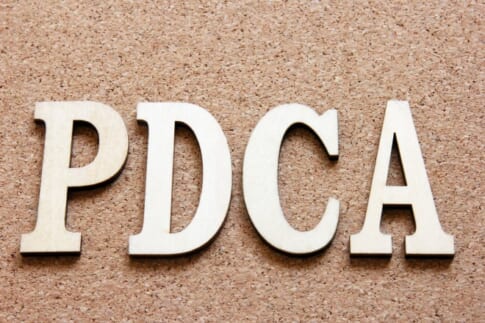温度管理が必要な商品を取り扱う際、どのような保管方法を選ぶべきでしょうか。
倉庫を選ぶときには、立地やコストだけでなく、商品の特性に合った温度環境が重要です。
特に、温度変化に敏感な商品を安全に保管するためには、適切な温度管理が欠かせません。この記事では、低温倉庫の特徴や導入前に確認すべきポイントについて詳しく説明します。
「i-Reporter」は導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)、国内トップシェアを誇る現場帳票システムです。
導入することで、紙の現場帳票の「記入・報告・管理」すべてのペーパーレス化を実現。さまざまな業務の効率化やDXにつなげられます。
また、弊社株式会社サンソウシステムズでは、要件定義から設計・導入、その後の運用管理まで、お客様に寄り添った伴走支援が可能です。
ぜひ、ご一緒に現場の業務課題を整理していきましょう。サービス資料を用意しましたので、併せてこの機会にこちらから無料でダウンロードしてみてください。
導入実績4,000社以上
目次
低温(定温)倉庫とは

低温(定温)倉庫の基本的な機能
低温倉庫は「定温倉庫」とも呼ばれ、温度や湿度を一定に保つことで、商品を適切な状態で保管できる倉庫です。特に温度変化に弱い生鮮食品や農産物、水産物などの長期間鮮度を保ちながら管理するために活用されています。
冷蔵倉庫や冷凍倉庫も、同様に温度を一定に保つ機能を持っていますが、冷凍倉庫は、さらに低い温度帯での保管が必要な商品に対応しています。そのため、メーカーによっては冷蔵倉庫や冷凍倉庫も含めて「低温倉庫(定温倉庫)」と呼ぶ場合もあるので覚えておきましょう。
低温(定温)倉庫が必要とされる理由
低温(定温)倉庫が必要とされるのは、温度変化に敏感な商品を長期間、安全に保管するためです。
例えば、生鮮食品などを輸送する場合、特定の温度での保管が非常に重要です。もし適切な温度を保てなければ、食品は腐敗や品質劣化を引き起こすこともあるでしょう。そのため、特に温度変化に弱い生鮮食品や加工食品の保管は、鮮度を維持するために低温(定温)倉庫で保管する必要があるのです。
さらに、医薬品や精密機器のような商品を管理する場合でも、厳密な温度管理が求められます。これらの商品は決められた温度で保管しなければ、成分や部品が劣化するリスクがあるため、一定の温度・湿度を維持することが非常に重要なポイントです。
そのため、低温倉庫は温度変化に敏感な商品を保護するだけでなく、商品を最適な状態で長期間保管できる環境を提供し、商品の品質を維持するために重要な役割を果たしているのです。
低温(定温)倉庫とほかの倉庫の違いと特徴
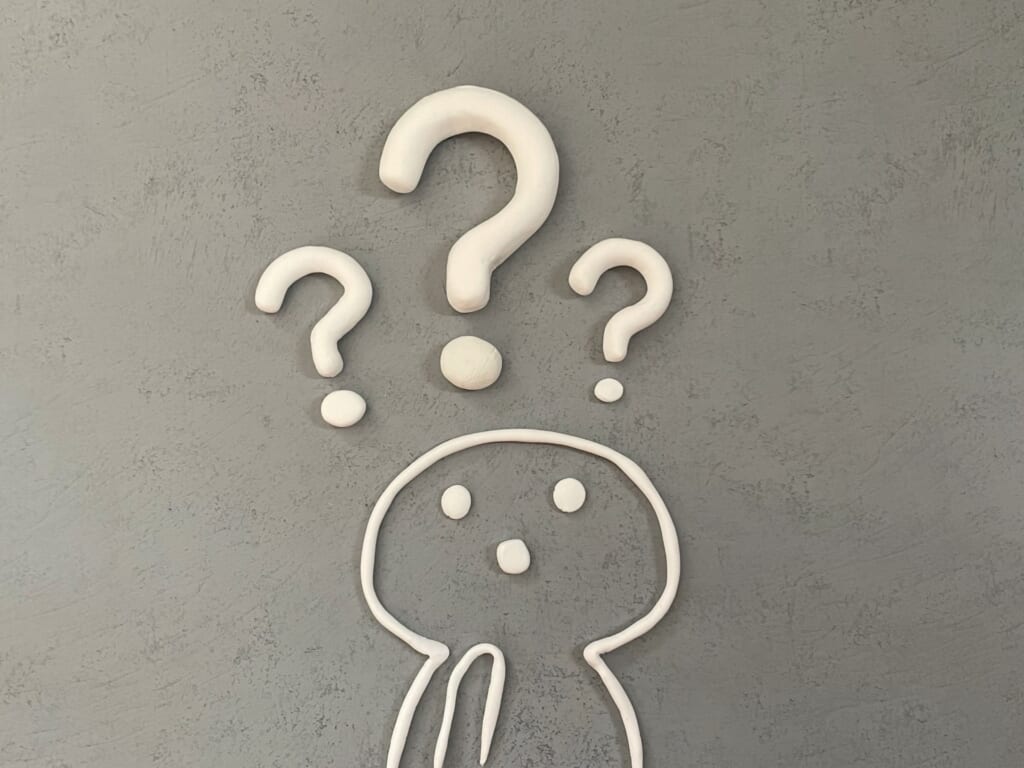
倉庫は、保管する商品の性質に応じて、異なる温度帯で管理されます。主に「常温」「低温(定温)」「冷蔵」「冷凍」の4つのカテゴリーに分かれています。それぞれの温度帯には、対応する商品や特徴があり、保管方法が異なります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
常温、低温(定温)、冷蔵、冷凍の違い
常温倉庫
まず、常温倉庫は、最も一般的に利用されている倉庫の一種です。温度管理が不要であるため、コストを抑えた形で商品の保管が可能なのが大きな利点です。通常の室温で保存できる商品はこのカテゴリーに該当し、乾燥食品や缶詰、日用品などが代表例です。これらの商品のように、外気温の変化による状態の変化が起こりにくいものを保管する際に適した倉庫です。
低温(定温)倉庫
次に、低温(定温)倉庫は、10~20℃程度の温度で保管が必要な商品に対応しています。
特に適しているのは果物や野菜、飲料など、温度変動に敏感な商品です。これらの商品は、一定の低温環境でのみ品質を維持できるため、低温倉庫での管理が必要になります。
冷蔵倉庫
冷蔵倉庫は10℃以下の温度で保管する必要がある商品に使用されます。冷蔵環境では、腐敗の原因となる微生物の活動を遅らせ、商品の鮮度を長く保つことができます。そのため、生鮮食品や乳製品、加工食品など、腐敗しやすい商品を取り扱う場合は、冷蔵倉庫で保管する必要があります。
冷凍倉庫
最後に、冷凍倉庫は主に-18℃以下の温度で保管される商品に対応します。一般的には冷凍倉庫も冷蔵倉庫に分類されますが、特に温度が低い範囲で保管する場合、わかりやすく区別するために冷凍倉庫と呼び分けられることがあります。冷凍食品やアイスクリーム、肉類など、長期保存を必要とする商品が主な対象です。
低温(定温)倉庫のメリットとデメリット

低温(定温)倉庫の主なメリット
低温(定温)倉庫の最大のメリットは、商品を長期間にわたって高品質な状態で保管できることです。
温度や湿度を適切に管理することで、商品の劣化を防ぎ、鮮度や品質の維持が可能になります。特に温度変化に敏感な商品では、定温での管理が欠かせません。
例えば、鮮度が重要な生鮮食品や劣化しやすい医薬品は、適切な温度で保管しなければ短期間で品質が損なわれてしまいます。低温倉庫では、これらの商品を最適な環境で保管することにより、長期間にわたってその品質を維持できるのです。結果として、腐敗や劣化を防ぎ、廃棄ロスを減らし、無駄なコストの削減にもつながります。
低温(定温)倉庫のデメリット
低温(定温)倉庫にはいくつかのデメリットも存在します。まず、コストが高いという点です。温度管理システムや湿度管理設備の運用には多大なコストがかかり、設備費や電力消費も増大します。特に、大規模な低温倉庫を維持するには、経済的な負担はかなり大きいものになるでしょう。
また、低温環境での作業は作業員にとって大きな負担となります。さらに長時間の作業は体調を崩すリスクが高まるため、従業員の体調管理や安全対策が大切です。そのため、最近ではこうした負担を軽減するために、自動倉庫の導入が注目を集めています。自動化により、作業員が低温倉庫で長時間働く必要がなくなり、労働負担の軽減が期待されています。
低温(定温)倉庫の用途別選び方
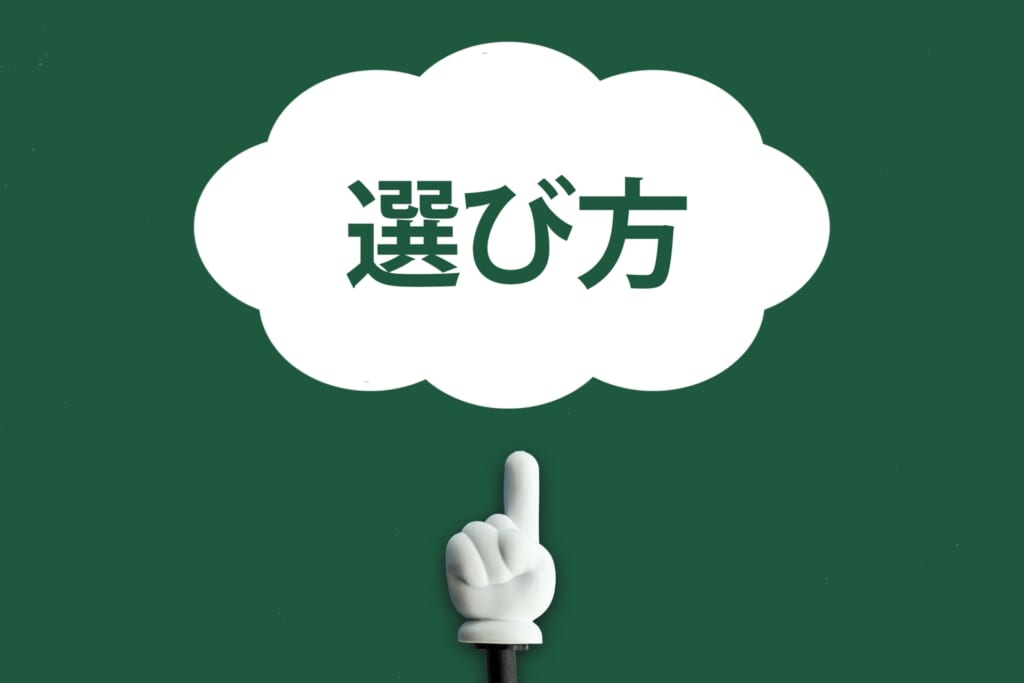
倉庫の温度帯ごとの違いと特徴で紹介したように、低温倉庫は保管する商品の特性に応じて最適な温度帯を選ぶことが重要です。ここからは、商品ごとに適した温度帯をどのように選ぶべきか、具体的に見ていきましょう。
食品の保管に適した低温(定温)倉庫の選び方
食品を保管する際には、商品ごとに適切な温度管理をおこなうことが品質を維持するポイントとなります。
生鮮食品は鮮度が命であり、腐敗を防ぎ、鮮度を保つためには、10℃以下の冷蔵倉庫が最適です。肉や魚、乳製品などはこの温度帯で保管することで、品質を維持できます。
一方で、冷凍食品の場合、長期保存が求められるため、-18℃以下の冷凍倉庫が最適です。
これにより、細菌の活動が抑えられ、食品の品質が劣化することなく保たれます。
さらに、果物や野菜のように温度変動に敏感でありながら冷凍する必要のない食品は、10~20℃の低温(定温)倉庫での保管が適しています。この温度帯ならば、食品の風味や質感を損なうことなく、品質を安定して維持することが可能です。
医薬品の保管に適した低温(定温)倉庫の選び方
医薬品は、製品の安全性や有効性を保つために、厳密な温度管理が必要です。多くの医薬品は一定の温度での保管が推奨されています。温度が少しでも変化すると、薬の成分が変質し、効果が薄れる可能性があるため、適切な温度帯を選ぶことが非常に重要です。
また、特定の医薬品に関しては、10~20℃の低温(定温)倉庫での保管が適している場合があります。医薬品の品質を維持するためには温度管理だけでなく、湿度や光の管理も重要です。取り扱う製品に合わせた適切な倉庫を選びましょう。
精密機器の保管に適した低温(定温)倉庫の選び方
精密機器の保管には、温度や湿度が製品に大きな影響を与えるため、安定した環境が不可欠です。特に、10~20℃の低温(定温)倉庫は、電子機器や精密部品を長期的に保管するのに適しています。湿度管理も欠かせないため、適切な湿度レベルを維持できる倉庫を選びましょう。
低温(定温)倉庫の導入前に確認すべきポイント

低温(定温)倉庫の導入を検討する際、押さえておくべき重要な点がいくつかあります。これから紹介するポイントをチェックし、効率的な運用につなげましょう。
立地条件とアクセスのよさ
まず、低温(定温)倉庫の立地は非常に重要なポイントです。仕入れ先や納品先に近い拠点を選ぶことで、物流の効率を最大限に引き出し、配送コストの削減にもつながります。特に輸入品の保管や輸送においては、港や空港に近い立地がコスト削減の大きなポイントです。
また、気候や災害リスクの少ない地域に倉庫を設置することも、商品を安全に保管するために欠かせません。気温の変化や自然災害によって、倉庫内の商品に影響が及ぶリスクを軽減するためには、立地選びに慎重な判断が求められます。
サービス内容
次に、低温(定温)倉庫の提供するサービス内容を確認しましょう。まず、温度や湿度の管理がどの範囲まで対応できるかを確認する必要があります。温度の細かい調整が可能か、湿度の管理がどの程度までおこなわれているかは、保管する商品の品質維持に直結します。
さらに、流通加工サービス(例:シール貼り、タグ付けなど)や、保管中の商品を柔軟に受渡しできるサービスが提供されているかも確認しましょう。特に、海外向けの発送や他社との連携がスムーズにおこなえるかどうかは、ビジネス全体の効率にも大きく影響します。
セキュリティ対策の確認
最後に、セキュリティ対策の確認です。
高価な商品やデリケートな商品を取り扱う場合、万全なセキュリティ対策は欠かせません。
監視カメラの設置、入退室管理システムの導入、セキュリティスタッフの配置など、総合的なセキュリティプランがしっかりと整っているかを確認しましょう。
低温(定温)倉庫のコストを抑える方法

低温(定温)倉庫のデメリットにも挙げたように、低温(定温)倉庫の導入・運用には、多くのコストがかかります。しかし、コストを削減しつつ、作業効率を向上させる方法があります。ここからは、コスト削減と作業効率の向上がどのように実現できるのかを見ていきましょう。
自動化技術を導入する
まず、自動化技術を導入することで、低温倉庫における人件費を削減することが可能です。
ロボットや自動搬送機器を活用することで、手作業の部分を大幅に減らし、作業効率を向上させます。低温(定温)倉庫における作業を自動化することにより、ミスや作業時間の短縮、さらに従業員の負担軽減にもつながります。
自動倉庫とはどのような倉庫なのか、自動倉庫の解説や導入することで得られるメリットについては別の記事で詳しく解説しています。自動倉庫の効率的な運用方法や、さらなるコスト削減について参考にしていただけます。
「自動倉庫とは?導入事例とメリットや気になる選び方を解説」はこちら
また、自動温度管理システムを導入することで、温度管理を完全に自動化し、手動での調整や管理の手間を大幅に減らせます。その結果、正確かつ安定した温度管理が実現し、商品に適した温度を常に保つことが可能です。
作業プロセスの自動化でおすすめツール「i-Reporter」
作業プロセスを効率化し、コストを抑えるために、報告書作成の自動化ツールとして「i-Reporter」が非常に効果的です。
「i-Reporter」は、現場での報告書作成を効率化するためのツールで、ペーパーレス化を推進します。これにより、紙の使用を減らし、コストを削減できます。
さらに、「i-Reporter」では、現場で収集されたデータをリアルタイムで共有できるため、迅速な意思決定をサポート。現場での報告がすぐに反映されるため、状況に応じた素早い対応が可能です。また、直感的に使える専用のデジタルインプットを用意しているため、現場作業者の負荷にならず、簡単に入力できます。導入後の定着率も高いのが特徴です。
導入実績4,000社以上
商品の品質を守るために、低温(定温)倉庫を上手に活用しましょう

低温(定温)倉庫は、温度や湿度を一定に保つことで、商品を適切な状態で長期間保管するための設備です。
特に、食品や医薬品、精密機器などの温度変化に敏感な商品にとっては、適切な温度帯での保管が品質維持のポイントとなります。そのため、倉庫を選ぶ際には、保管する商品の特性に合った温度環境を正確に理解し、それに対応した倉庫を選ぶことが重要です。
そして、低温(定温)倉庫の運営コストを抑えるためには、自動化技術の導入も効果的です。自動化システムを活用することで、作業の効率化を図り、管理コストや人件費を削減しながら、効率的な低温(定温)倉庫の運用を目指しましょう。
株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
現場帳票のシステム化を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか」といった課題や不安がつきものです。
そのような企業様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。
お話を伺いたい方は、無料の『ちょこっと相談室』(Teams:オンライン)で、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。