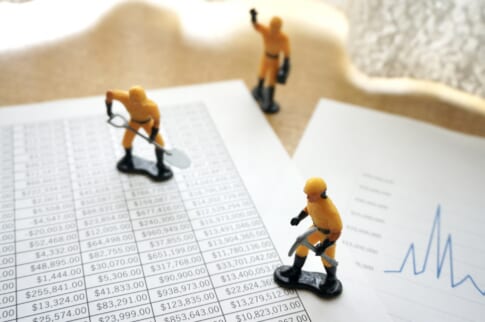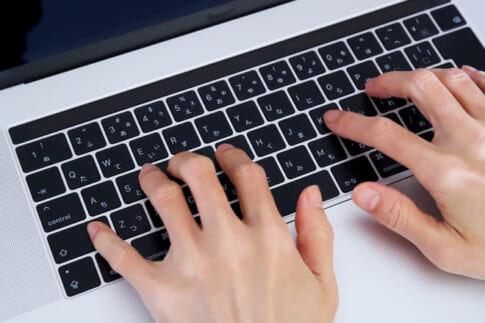製造業や建設業など日々、作業日報を作成する企業も多いのではないでしょうか。
企業ごとに作業日報の作成方法は異なりますが、Excelファイルを紙に印刷して紙媒体で管理する場合がほとんどです。
しかし、紙を使用した作業日報の作成・運用は何年も経過すると膨大な量のファイルを取り扱うことになり、必要な情報を必要なときに確認できないことも少なくありません。
そこで、日々の作業日報を電子化すれば、さまざまなコストの削減や業務の効率化が期待できます。本記事では、作業日報を電子化する目的やメリット・デメリット、電子化する際の注意点について解説します。
「i-Reporter」は導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)、国内トップシェアを誇る現場帳票システムです。
導入することで、紙の現場帳票の「記入・報告・管理」すべてのペーパーレス化を実現し、さまざまな業務の効率化やDX促進につなげることができます。
また、弊社株式会社サンソウシステムズでは、要件定義から設計・導入、その後の運用管理まで、お客様に寄り添った伴走支援が可能です。
ぜひ、ご一緒に現場の業務課題を整理していきましょう。サービス資料を用意しましたので、併せてこの機会にこちらから無料でダウンロードしてみてください。
導入実績4,000社以上
目次
作業日報とは

作業日報とは、当日おこなった作業内容を上司や責任者に報告するための文書です。
1カ所の現場において1つの作業日報を提出する企業もありますが、基本的には作業員一人ひとりが作成します。ちなみに、原則として作業日報を作成しなければいけない訳ではありません。
しかし、作業日報を作成して上長が業務の進捗状況を把握できれば、業務上でのアドバイスや現場の労働環境の把握が可能になり、生産性の向上が実現できます。
作業日報の目的

作業日報は、ただの記録や日記ではありません。日々作成する作業日報は生産性を維持・向上する上で貴重なツールです。
業務の振り返り
作業日報は1日の業務終了後に作成しますが、業務状況を上長に報告するだけが目的ではありません。
作業をおこなうのは現場の人間であり、業務効率化や生産性の向上など現場の努力なくては成り立ちません。
そのため、日々の業務を作業員に振り返らせることで「業務が計画的におこなえていたのか」「解決できる点や新たな課題は見つかったのか」などを見出すことも、目的の一つです。
業務の進捗把握
作業日報の目的には、業務の進捗状況を見える化することも含まれます。
現場の作業員だけが業務状況を把握し、上長や会社が状況把握できていないと、万が一トラブルが起きた際に適切な対処ができません。
作業日報で日々業務の進捗を把握できれば、仮に計画通り進んでいなくても、人員の補強や適切なアドバイスなどによって、事前に対応が可能です。
労働環境の把握と改善
現場での作業は常に事故のリスクが潜んでおり、正しく整備されていなければ思わぬ事故へとつながることも少なくありません。
作業日報で労働環境を見える化することで、事故の可能性が高い場所や障害になりうる問題などを把握できます。
仮に事故が起きたとしても今後同じことを繰り返さないように原因を明確にできるでしょう。
手書きの作業日報における課題

これまで手書きで作成してきた作業日報を電子化することに抵抗がある企業もあるでしょう。しかし、手書きの作業日報にはさまざまな課題があります。
記入に時間がかかる
そもそも作業日報の作成は業務の一部ではあるものの、コア業務ではありません。
そのため、作業日報の作成にリソースが取られていると、本来の業務への注力が難しくなります。
また、手書きによる作業日報は記載後、パソコンで入力し直すことがありますが、これも非効率な作業と言えるでしょう。
ミスにより正確なデータを把握できない可能性がある
手書きによる作業日報の作成は、記入漏れや記載ミスを起こすことも少なくありません。
作業日報は、業務の進捗状況を把握する重要な役割があり、正確な情報を記載しなければ作成の意味がないのです。
正確な情報を把握できず誤った情報のまま業務が進行すると、後々問題が起きた際に対処できなくなるリスクもあります。
情報をリアルタイムで把握できない
作業日報は業務の終了時に記載するものではあるものの、上長や会社としては業務の進捗状況を常に把握しておきたいでしょう。
しかし、手書きによる日報では業務終了時にしか現場の状況を把握することができません。
作業日報を記載するために会社に戻って提出したとしても、担当者や課長、部長などに回覧されれば全員が情報を把握するのに1〜2週間程度かかることもあり、情報の把握が大幅に遅れます。
過去のデータ検索が難しい
手書きの日報は、作業員が多いほど膨大な量となります。その分、一人ひとりの日報内容を把握するのは困難です。
また、必要な情報が欲しいときには「一枚ずつ作業日報を確認する」「日報を記載した作業員に直接確認する」など非効率な手段を取らなければなりません。
日報を日々書いている作業員としても「何のために作業日報を書いているのかわからない」といった不満へとつながる恐れもあります。
作業日報を電子化するメリット

作業日報を電子化することでさまざまなメリットがあります。
ペーパーレス化によってコストが削減できる
紙媒体による作業日報の作成・記載は紙代だけではありません。
保管場所の確保や共有するのであれば印刷代などもかかります。1日あたりは少量の金額かもしれませんが、中長期的に見ると膨大なコストです。
しかし、作業日報を電子化すればかかる費用は初期の導入費用と月額費用のみになります。
ノウハウや知識の共有がスムーズにできる
作業日報の電子化はノウハウや知識の共有をスムーズにおこなえます。
手書きの作業日報は会社に戻らなければ情報の共有ができませんが、電子化によって端末が一つあれば現場と会社の距離が離れていても情報共有が可能です。
入力ミスを減少できる
作業日報を電子化すれば統一したフォーマットで記入漏れや記載ミスを防ぐことができます。
中には選択形式や必須の入力項目設定など、入力作業を簡略化することができるツールもあります。
また、作業日報を電子化すれば現場で日報の作成が可能になるため、時間が経過して日報を作成するよりも正確な日報の作成が可能です。
社内コミュニケーションが活発になる
手書きの作業日報はテキストのみになる傾向があるため、情報が伝わりにくい面もあります。
他にも、コミュニケーションがうまく取れていないことでアクシデントや事故を起こすリスクも高まります。
しかし、作業日報アプリはテキストだけでなく写真や動画も共有可能です。
また、コメント機能やスタンプ機能などによって気持ちが表現しやすくなるため、部下は気軽にコミュニケーションをとりやすくなります。
特にSNSを使い慣れている世代にとっては、オンラインでのやり取りの方が気軽にコミュニケーションを取りやすいと感じる人も多く、チームワークの向上が図れるでしょう。
作業日報を電子化するデメリット

作業日報を電子化することはメリットだけではありません。デメリットを理解した上で導入を検討しましょう。
導入コストがかかる
作業日報の電子化は、長期的に見ればコスト削減につながりますが、導入しはじめには初期費用や運用のために人材を確保する必要があります。
急な出費はこれまで計画しておいた予算内に収まらないことが多く、事業に影響を及ぼしかねません。
導入する前には自社の予算と作業日報のツール費用を把握し、費用対効果が高いのか試算しておきましょう。
現場に定着するまで時間がかかる
作業日報を電子化するにあたり、定着までにはある程度の時間がかかります。
初めは日報の作成に時間がかかり、スムーズにコミュニケーションを取れないこともあるでしょう。
そのため、まずはスモールスタートで導入をはじめ、定着してきたら他部署へ横展開していきましょう。ツールによっては定着まで伴走支援してくれる企業もあります。定着までの期間を短縮できるため、サポート体制を確認しておきましょう。
セキュリティの脆弱性による情報漏洩のリスクがある
紙媒体の作業日報は社内で保管することが一般的のため、情報が漏洩するリスクは少ないでしょう。
しかし、電子化による情報保管はハッキングなどを受けると企業の内部情報が漏洩し、最悪の場合取引先の情報を盗まれるリスクもあります。
情報漏洩のリスクを低減させるためには、ツールのセキュリティを強化できる人材を確保し、定期的に見直しをおこなうことが重要です。
また、パスワードを定期的に変更しハッキングされないよう日々対策をおこないましょう。
作業日報を電子化する際の注意点

作業日報を電子化する際は、社内全員で取り組む必要があります。上長や役員だけですべてを決定するのは避けましょう。
ツールの導入は使いやすいさを重視する
ツールを選定する際は以下のような選定ポイントがあります。
- 価格
- 使いやすさ
- 口コミや評価
- サポート体制
- セキュリティ
- 機能・サービス
どれも考慮した上で最適なツールを選ぶのが望ましいですが、すべての条件が揃っているツールを見つけるのは困難です。
そこで最も考慮すると良い点が「使いやすさ」です。
例えば、多機能であるツールを選ぶとしましょう。多機能であることは良いことですが使いこなせなければ意味がなく、多機能であるがゆえに情報がノイズになってしまい、作業日報の効率化ができない場合もあります。
なるべく自社に必要である機能だけを搭載しており、シンプルな画面で使いやすいアプリを重視しましょう。
現場へ呼びかけ協力体制を整える
ツールの導入時、役員だけで決めてしまう企業も少なくありません。
しかし、ツールを使用するのは現場の作業員です。そのため、現場へツールを導入することを周知し協力を仰ぎましょう。
また、単に導入するのではなく「導入するキッカケ」や「導入することでどのような効果が見込めるのか」が説明できると、作業員のモチベーション向上にもつながります。
作業日報を電子化するなら「i-Reporter」

作業日報は現場の業務状況を把握し、労働環境の改善や業務効率化、会社の売上向上にもつながる業務です。
紙による作業日報の作成・管理は、記載ミスや漏れによって正確な状況を把握できないリスクもあります。
しかし、作業日報を電子化することによってさまざまな課題を解決できます。本記事を参考に、作業日報アプリの導入を検討してみてはいかがでしょう。
そして、作業日報アプリを導入するなら株式会社シムトップスが提供する現場帳票作成ツール「i-Reporter」の導入がおすすめです。
株式会社サンソウシステムズでは、導入社数No.1(富士キメラ総研 2023年8月8日発刊)の現場帳票システム「i-Reporter」の導入を支援する『ちょこっと相談室』という無料のオンライン相談窓口を設けております。
現場帳票のシステム化を検討する際、「時間がなくて調査ができない」「導入しても運用できるか不安」「他社製品と比較してどうなのか」といった課題や不安がつきものです。
そのような企業様も安心してください。コンサルティング実績の多い弊社であれば、課題のヒアリングから業務効率化に向けた、目標設定・試験導入、その後の本導入から運用まで伴走支援いたします。
まず、やるべきことを整理するだけでもメリットになります。
お話を伺いたい方は、無料の『ちょこっと相談室』(Teams:オンライン)で、お気軽にご相談ください。現状課題のヒアリングから丁寧に対応させていただきます。